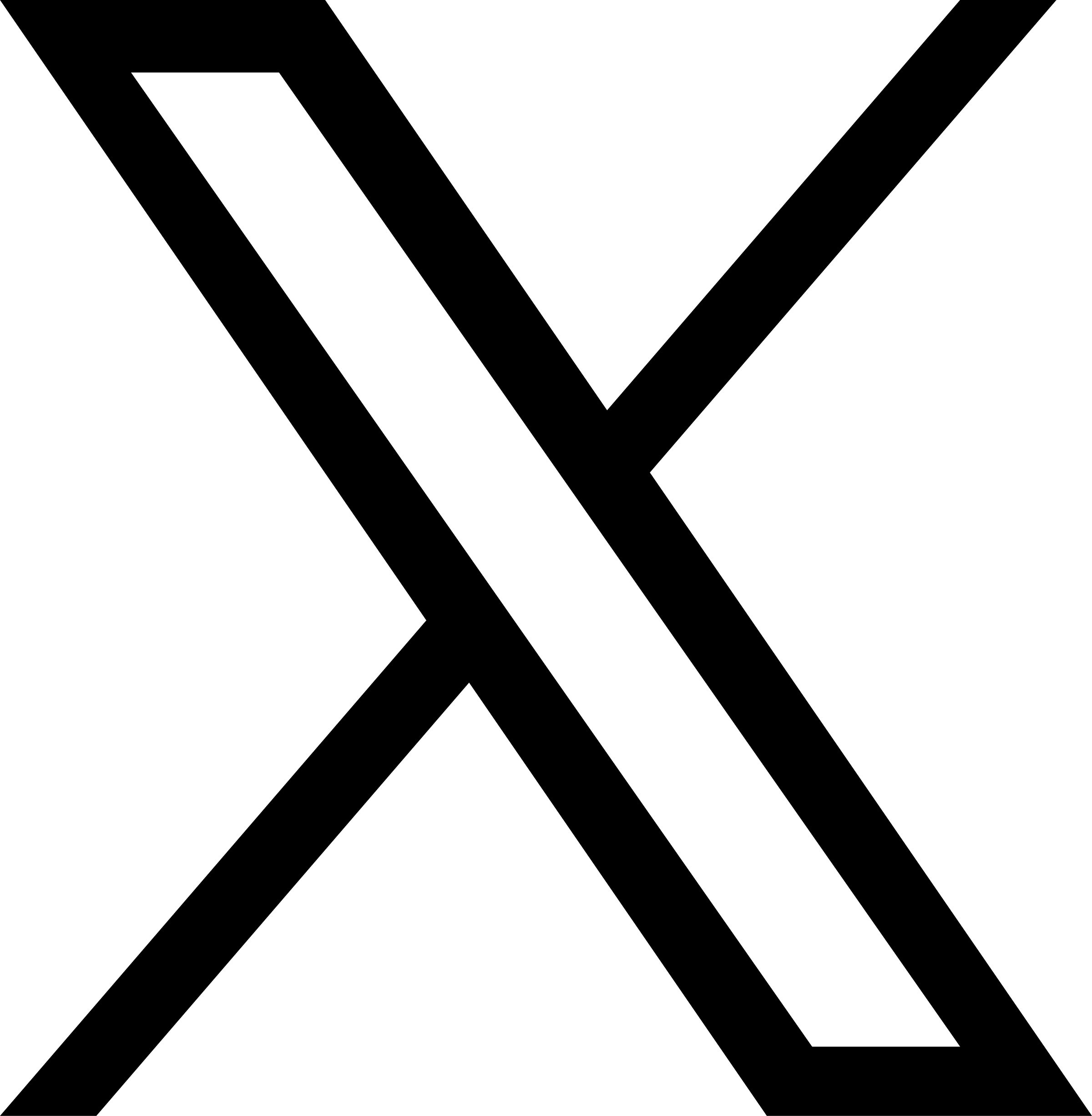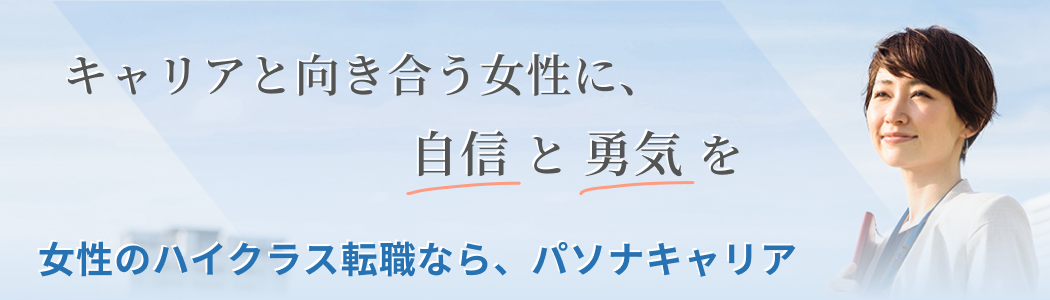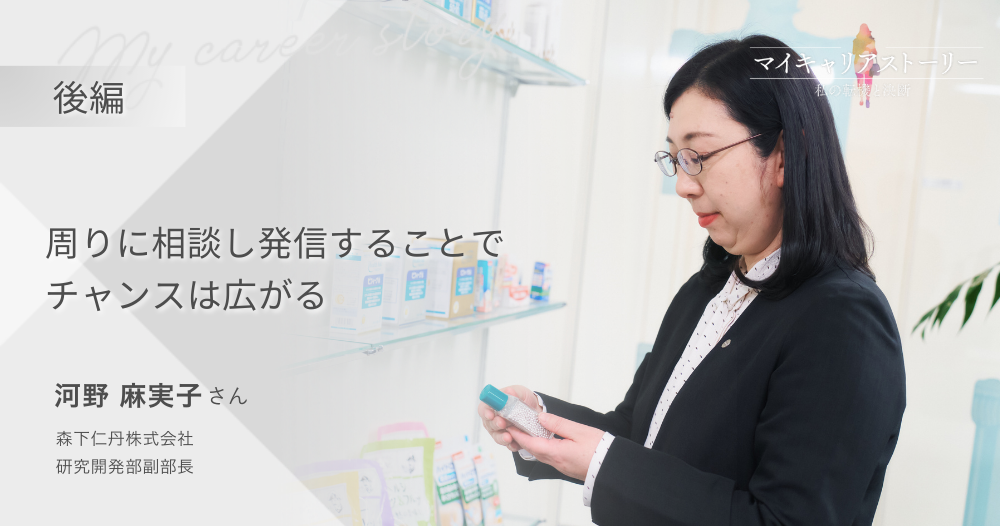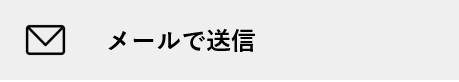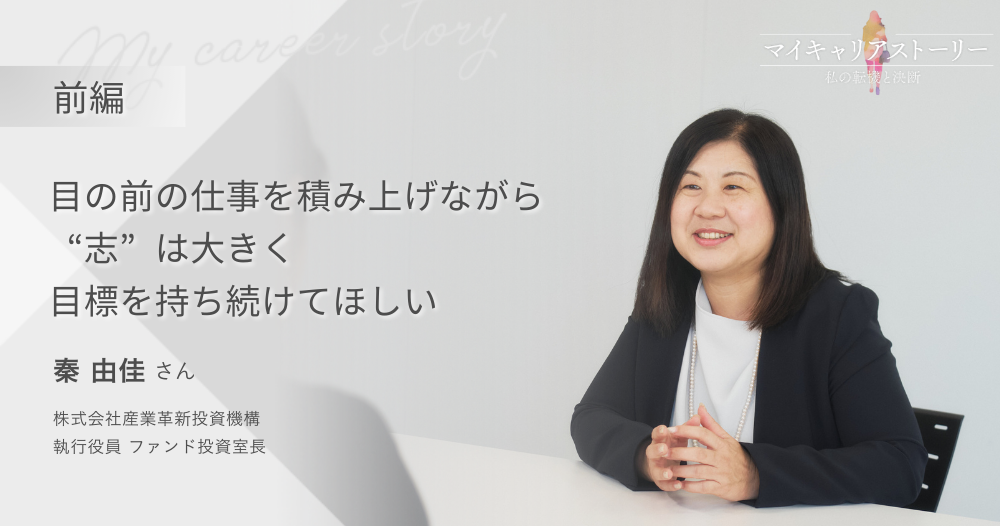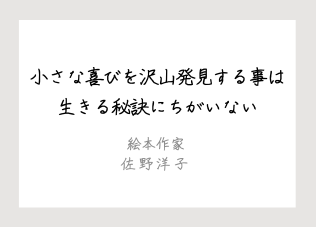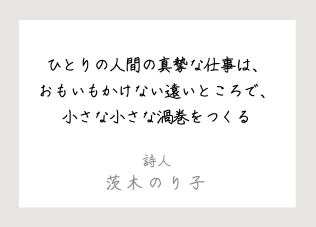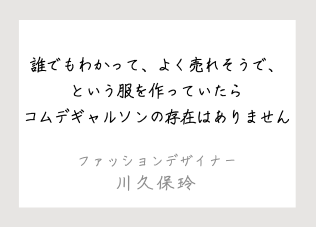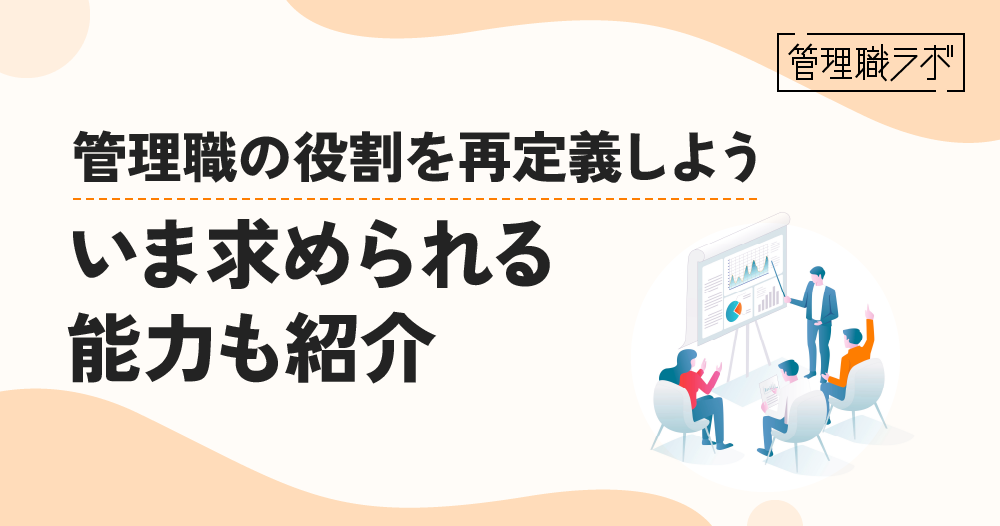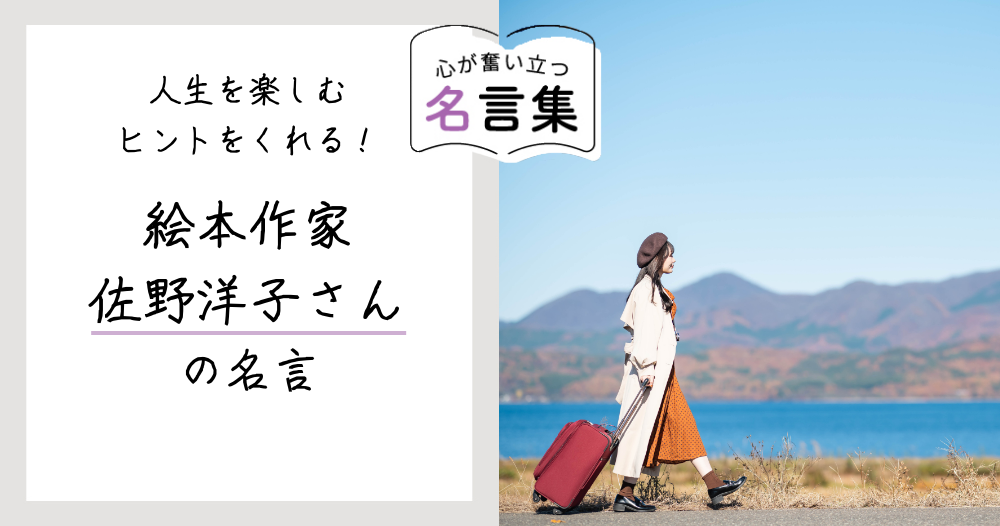『周りに相談し発信することでチャンスは広がる』
森下仁丹 研究開発部 河野麻実子さん【後編】
誰しも迷うキャリアの決断。管理職として活躍する女性はいつ、何に悩み、どう決断してきたのか。キャリアの分岐点と、決断できた理由を語っていただきます。
今回は前回に引き続き、森下仁丹株式会社で研究開発部副部長を務める河野麻実子さんにお話を伺いました。
※所属部署・肩書・制度は取材当時のものとなります。

河野 麻実子(こうの まみこ)さん
博士(応用生命科学)
事業統括本部 研究開発部 副部長 兼 研究グループ グループリーダー 兼 腸内環境研究チーム チームリーダー
こちらも
おすすめ
【PIVOT動画】「2026年の転職市場」をプロが超予測
遠隔からのマネジメント、何でも言い合えるチームを目指した

- 産休・育休からの復帰し、しばらくした後に、河野さんは研究チームのリーダーを任されます。東京オフィスに勤務しながら、研究開発拠点である大阪テクノセンターのメンバーマネジメントを担うという、社内でも初めての試みでした。
- 「当時はリモート会議が当たり前ではない時代だったんです。『コミュニケーションは対面が基本だよね』というのが社会的にも一般的な価値観で、ツールもそれほど充実していませんでした。
一方で、私自身、長く大学で共同研究を続けていた経験から、『一人よがりの研究開発になってはいけない』という思いが強くありました。『良い製品を作っていくために、メンバーみんなでディスカッションをしながら課題を解決していくチームでありたい』、そう思い、とにかく遠隔でも言いたいことを言い合える、風通しのよいコミュニケーションを追い求めていました」
- リモートでコミュニケーションを取りながら仕事をする、という前例がなかった中でリーダーを任された河野さん。“抜擢”の理由を聞くと、「柔軟な社内カルチャーがあったからでは」と話します。
- 「東京に異動したのは夫の転勤に伴う家庭の事情でしたが、『東京でも研究職を続けられるように』といち早く環境を整えてくれました。また、子育てとの両立の面でも、上司が『何よりも子どもが一番大事。仕事を続けやすい方法を考えよう』と常に一番の理解者でいてくれました。」
- チームのメンバーは比較的若く、研究者として実績のある河野さんの経験を頼ってくれたそう。そんな中、河野さんがリーダーとして実践したのは、毎朝オンラインで顔を合わせてミーティングをすること、そして、全員でディスカッションする機会を増やすことでした。
- 「どんなことでも相談できるチーム間の”心理的安全性“を担保しようと、チャットツールを使って『小さなことでもチャットしてきてほしい』と伝えました。心がけたのは、新人からベテランまで誰とでも同じようにコミュニケーションを図ることです。
また、課題が出たときに個別に対応するのではなく、時間がかかったとしても、チーム全員でディスカッションすることを徹底しました。議論に加わることで、課題解決に対して当事者意識が生まれます。推進していく人、フォローしていく人という関係性が生まれ、チーム一丸となる土台ができると考えました」
- オープンなコミュニケーションを心がけていくと、メンバーから様々な提案が出てくるようになりました。
- 「例えば、『こんなツールを使って効率化したらどうですか』、『オンラインミーティングではこんなやり方をしませんか』と、チーム運営に対する意見もどんどん出てくるようになりました。もちろん、研究開発に関する提案も増えました。私自身、新しいやり方は何でも楽しみたい、と思うタイプなので、『いいね!試してみよう!』、『合わなかったら辞めればいい』とすぐに取り入れていきます。そんな対応が、提案したらより良くなっていく、というメンバーの実感につながっていったのかもしれません」
- 河野さんの描くマネージャー像には、これまで出会ってきた多くの上司たちの存在が影響しているといいます。
- 「上司の皆さんはそれぞれ持っている強みが違いました。研究成果を外部にアピールすることに長けた方、メンバーのモチベーションを上げることが上手な方、社外から得た情報を研究開発に応用するアイデア力にあふれた方、研究開発をスムーズに進めていく調整力に優れた方。それぞれのいいところを学ばせてもらい、今の私があるので、私もメンバーに”真似したい“と思ってもらえるような何かを一つでも多く残したいですね」
「自分の人生を優先しよう」と前を向けた

- 入社以来、一貫して研究開発に携わってきた河野さん。そのモチベーションの源泉には、「お客様の健康に少しでも役立ちたい」という変わらない思いがあります。
- 「仕事でも、それ以外でも、誰かのためになることが自分の喜びにつながっているんです。研究開発によって製品がより良くなり、お客様の健康につながっていくと信じられるので、ずっと続けてこられたのだと思います」
- 一時期は、ライフイベントとの両立で、研究の仕事をセーブしなければいけないのではないか、と悩んだ時期もあったそう。もやもやとした気持ちを友人に吐き出したとき、かけられた一言に背中を押されたと話します。
- 「研究に自分の時間を注いで没頭し、30代も後半になってきたころは、『今、妊娠・出産したら、この研究に支障が出てしまうから、なかなか踏み出せない』という思いもありました。そのときに、友人から『自分の人生を優先しなくちゃ』とアドバイスをもらい、スッと気持ちが楽になりました」
- 森下仁丹では、2023年に女性の産休・育休の取得率、復職率11年連続100%を達成しています。有給での看護休暇制度や、子どもが小学4年生になるまで時短勤務を続けられる制度があるなど、年々、改善しながら働きやすい環境づくりを進めています。その背景には、河野さんをはじめ子育てと仕事の両立を続ける社員からのさまざまな提案があったといいます。
- 「私自身が、上司や会社の理解を得て、新しい働き方をさせてもらえたように、多様な働き方をインクルージョンして、ライフワークバランスを適切に取りながら、メンバーみんなが生き生きと働けるようなグループ作りが大切だと思っています。小さなことでも自分で抱えずに、まずは周りに相談してみることがすごく大切です。
メンバーにも、ライフイベントなどで、何かを諦めてほしくありません。様々な立場の人の意見を聞きながら、巡ってきたチャンスを掴んでいってほしいと思っています」
→「前編記事」
~あわせて読みたい記事~ |
写真:MIKAGE
取材・執筆:田中 瑠子