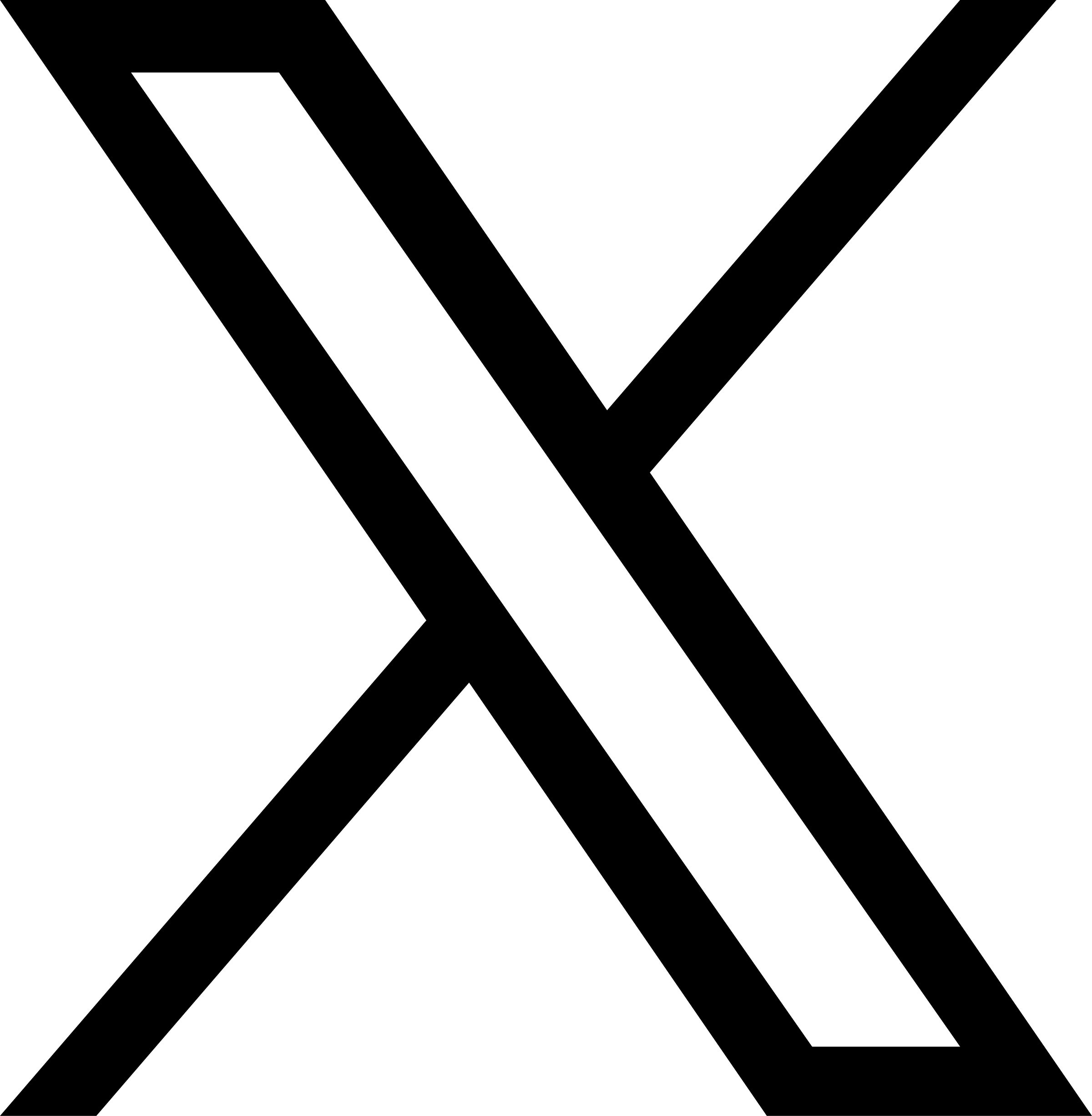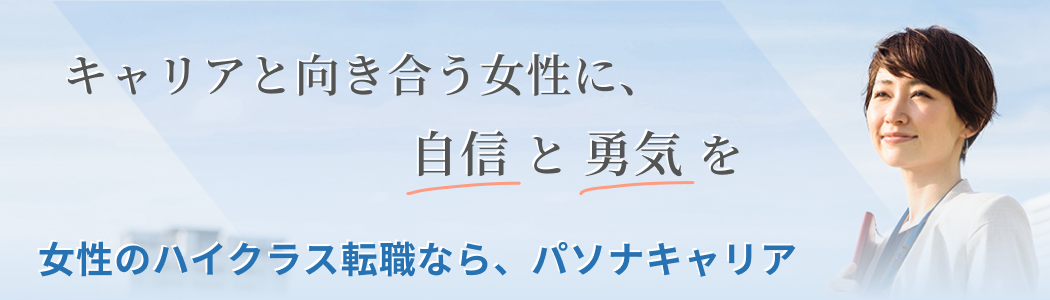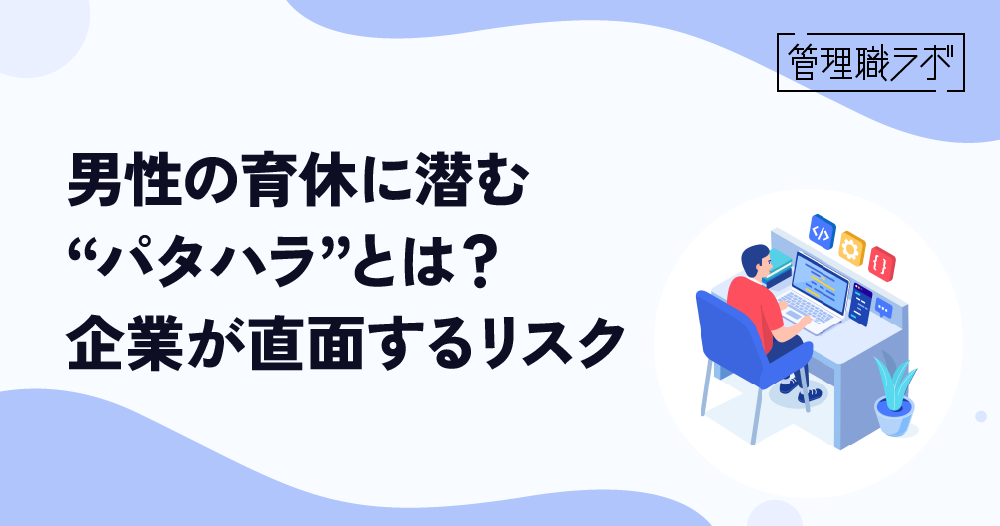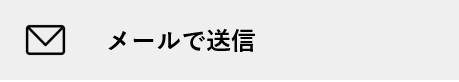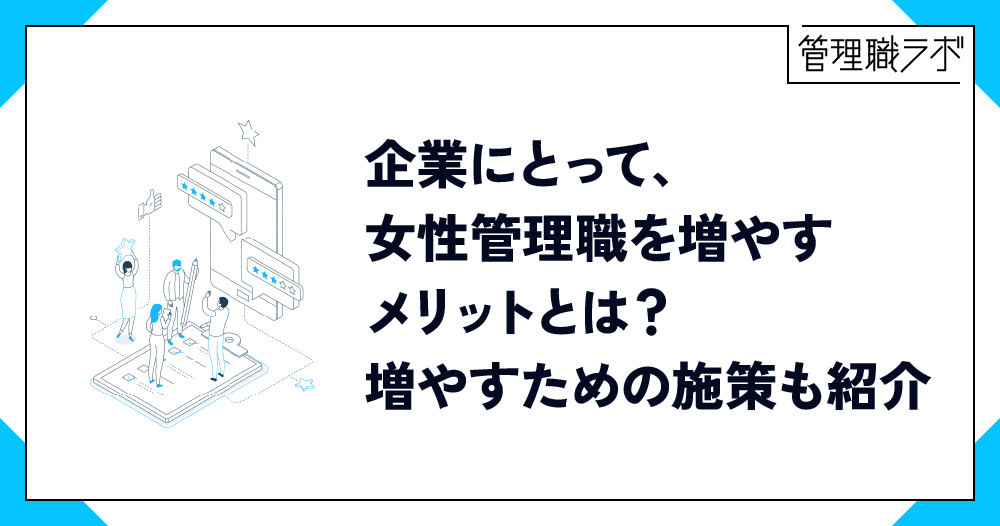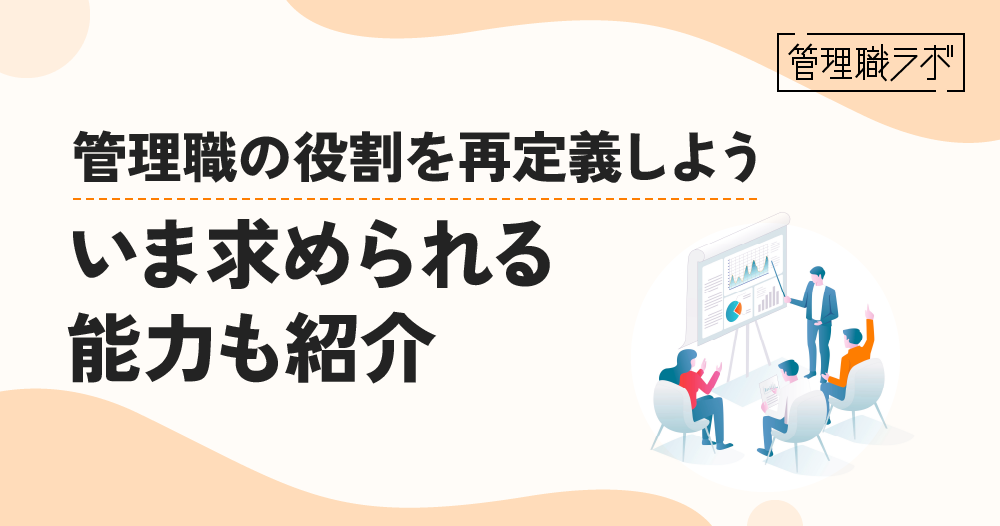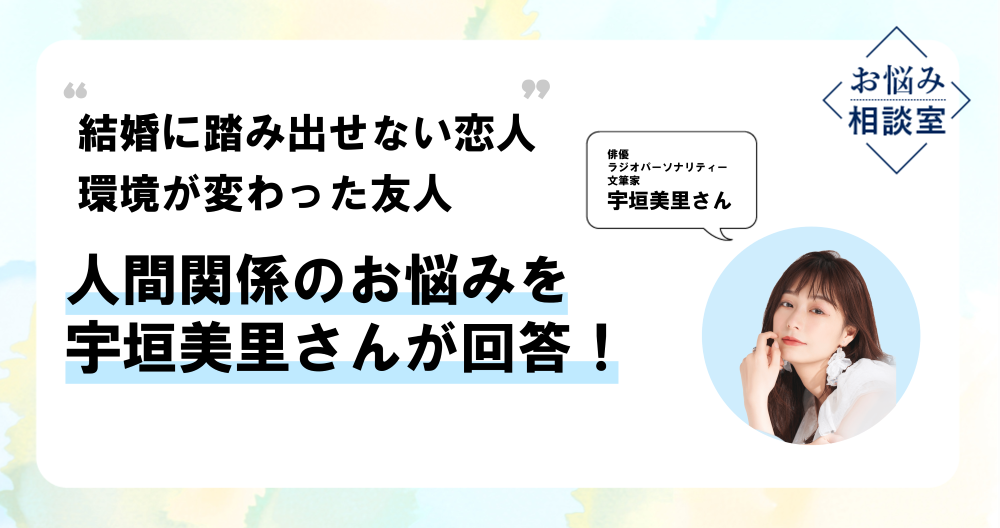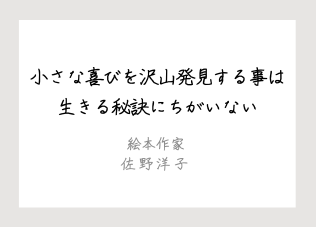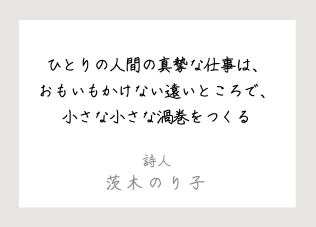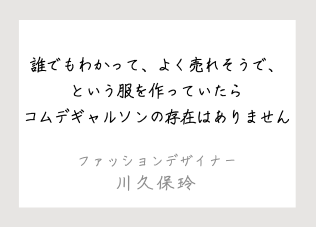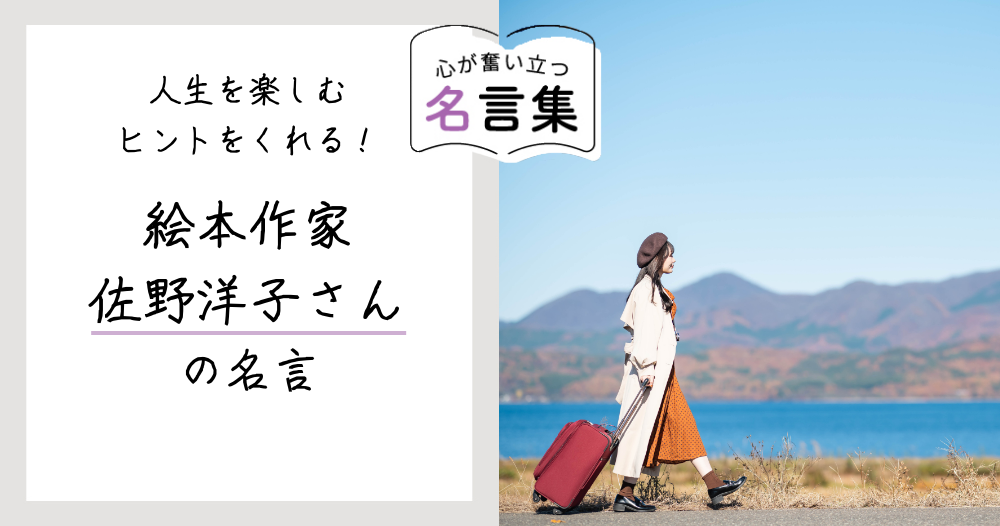パタハラとは?男性の育児参加を妨げるハラスメントの実態と企業の対策
近年、男性の育児参加が推進される中、育児休業や時短勤務を利用しようとする男性従業員に対する嫌がらせや不利益な扱い「パタハラ」が問題視されています。
この記事では、パタハラの定義や具体例、影響、関連する法律、企業が取るべき防止策、被害を受けた際の対処法まで詳しく解説します。
目次
パタハラとは?

パタハラとは、男性従業員が育児休業や時短勤務などの制度を利用する際に、上司や同僚から嫌がらせや不利益な扱いを受ける「パタニティ・ハラスメント」の略称です。
近年、男性の育児参加が推進される一方で、このようなハラスメントは依然として存在し、制度の利用をためらわせる要因となっています。
パタハラは「育児は女性が担うもの」という固定観念や、育児休業取得に対する理解不足から生じます。
こうした行為は、男性の育児参加を阻害するだけでなく、従業員のモチベーション低下や人材流出を引き起こし、企業にとっても重大な問題となります。また、育児・介護休業法で禁止されている不利益取扱いに該当する場合もあり、法的責任を問われる可能性もあります。企業にとってパタハラ防止は、社会的責任と法令遵守の両面で欠かせない課題です。
ハラスメントの種類についてはこちらの記事で詳しく紹介していますので、ご覧ください。
https://bemyself.pasonacareer.jp/skill/skill-1737/
パタハラの具体例
パタハラは様々な形がありますが、その多くは育児休業や時短勤務の利用を妨害したり、取得後に不利益な扱いをする行為です。ここでは代表的なケースを紹介します。
育児休業の取得を認めない
男性従業員が育児休業を申請しても、「前例がない」「業務が回らない」といった理由で申請を拒否されるケースです。これは法律で認められた権利の侵害であり、明らかなパタハラに該当します。
復職後の仕事に不利益を与える
育児休業から復帰した男性社員に対し、意図的に責任ある仕事を与えない、不本意な部署に異動させるなどの扱いが行われる場合があります。このような行為はモチベーションを大きく損ねるだけでなく、法的にも問題となります。
職場内での嫌がらせや圧力
「男なのに育休を取るのか」「他のメンバーに迷惑だ」といった嫌味や陰口、同僚からの孤立化もパタハラです。精神的な負担が大きく、業務・育児への意欲や職場での居心地に悪影響を及ぼします。
減給や降格を行う
育児休業の取得を理由に、昇進を見送る、給与を減額する、降格を命じるといった人事上の不利益は法律で禁止されています。これらは企業にとって重大な法的リスクとなる行為です。
パタハラがもたらす影響
パタハラは、男性個人のキャリアや家庭生活に悪影響を与えるだけでなく、組織全体の健全性や企業価値にも深刻な影響を及ぼします。ここではパタハラがもたらす主な影響について解説します。
男性の育児参加への悪影響
パタハラが起こる職場では、男性社員が育児休業の取得をためらい、積極的な育児への参加が困難になります。
こういった職場ではワークライフバランスの改善が進みづらく、家族との時間が減ることにより家庭での不和も誘発します。その結果、従業員の満足度の低下や精神的な健康も損なわれる可能性が増加します。
職場環境の悪化と従業員の離職
ハラスメントが横行する職場では、信頼関係が崩れ、職場の雰囲気も悪化するでしょう。パタハラの被害者はもちろん、周囲の従業員も将来的な不安を抱え、モチベーションの低下を招きます。結果的に、優秀な人材の離職率が上がる可能性が高くなります。組織力の低下は企業の成長にも直結する由々しき問題です。
社員の離職を防ぐための取り組みについてはこちらの記事もご覧ください。
https://bemyself.pasonacareer.jp/skill/skill-2305/
企業が負う法的リスク
育児休業を理由とした不利益な扱いは、育児・介護休業法に違反する可能性が高く、企業にとって行政指導や訴訟といったリスクも上がります。加えて、社会的評価の低下や採用活動への悪影響も避けられません。企業はもちろん、現場を管理する管理職もパタハラを防ぐ体制づくりが必要です。
パタハラに関連する法律と企業の責任
パタハラは単なる職場トラブルではなく、法律で禁止されている不利益取扱いに該当します。企業は法令遵守の観点からも、パタハラ防止に向けた責任を果たさなければなりません。
ここではパタハラに関連する法令について詳しく解説します。
不利益取り扱いの禁止
育児・介護休業法 第十条では、育児休業の取得もしくは申出を理由とした解雇、降格、減給などの不利益取扱いを禁止しています。
違反が認められれば、行政指導や企業名公表、さらには損害賠償請求につながる可能性もあります。男性も女性と同様に、育児休業は法的に守られた権利です。
マタハラ・パタハラの防止措置義務
育児・介護休業法 第二十五条では、企業は妊娠・出産に関連するマタハラだけでなく、男性の育児参加を妨げるパタハラに対しても防止措置を講じることが義務づけられています。
厚生労働省の指針では、相談窓口の設置、研修の実施、適切な対応体制の整備が求められています。対応を怠れば、企業は労働環境改善の指導を受けるほか、社会的信用の失墜にもつながります。
パタハラを防止するための企業の取り組み
パタハラを防止するためには、制度の整備だけでなく、職場全体の意識改革が不可欠です。ここでは、パタハラ防止に向けた企業の取り組みをいくつか紹介します。
男性社員の育児休暇を浸透させる
男性も育児に積極的に関われるよう、企業が率先して制度利用を奨励する取り組みを行うことが重要です。上司自身が積極的に育休を取得するなど、模範的な行動を示すことで従業員の利用への心理的ハードルが下がります。
他にも育児休暇中の社員の声を社内報にのせる、従業員が口に出す前に上司の方から育児休暇の声かけをする、復帰後のキャリア支援を行うなど、企業全体に男性社員の育児休暇を当たり前に思えるような空気感を作っていくための取り組みが必要です。
部下のキャリア支援についてはこちらの記事もご覧ください。
https://bemyself.pasonacareer.jp/skill/skill-1906/
パタハラ防止の社内周知・教育の実施
パタハラ防止には、社員全体への周知と教育が欠かせません。特に昔ながらの価値観が根強い企業こそ、研修やガイドラインを通じて、ハラスメントの定義や禁止事項を共有し、無意識の偏見をなくす取り組みを進めることが重要です。
価値観のアップデートは、社員が自らキャッチアップを行うことを期待するのではなく、企業が主体となって行うことが大切です。
相談窓口の設置
パタハラを受けた社員が安心して相談できる窓口の設置も重要です。
人事部門や外部機関との連携により、被害を受けた社員が声を上げやすい環境を整えることで、早期対応と再発防止が可能になります。
パタハラを受けたときの相談先と対処法
パタハラを受けた場合、泣き寝入りせず適切に対応することが大切です。夫が被害に遭った場合も、家族として支えるとともに正しい相談先を把握しておきましょう。
・社内での相談先(人事部・相談窓口)
まずは社内の相談窓口や人事部に相談しましょう。客観的に状況を判断してもらえるよう、事実を記録したメモや証拠を準備し、具体的な状況を冷静に伝えることで、会社に改善を促すことができます。相談した記録を残すことも重要です。
・外部機関(労働局・弁護士等)への相談
社内で解決が難しい場合は、労働局の総合労働相談コーナーや弁護士など外部の専門機関に相談しましょう。行政指導や法的措置を通じて、企業に改善を求めることができます。また、家族が一緒に相談に同行することで心理的な支えとなります。
まとめ|パタハラ防止で育児と仕事の両立を支援しよう
パタハラは、男性の育児参加を阻害し、個人や家族だけでなく職場全体や企業の信頼性にも悪影響を及ぼします。被害を受けた際は社内外の相談先を活用し、早期に対応することが大切です。
職場全体でパタハラをなくし、育児と仕事の両立を支える企業づくりを実現しましょう。