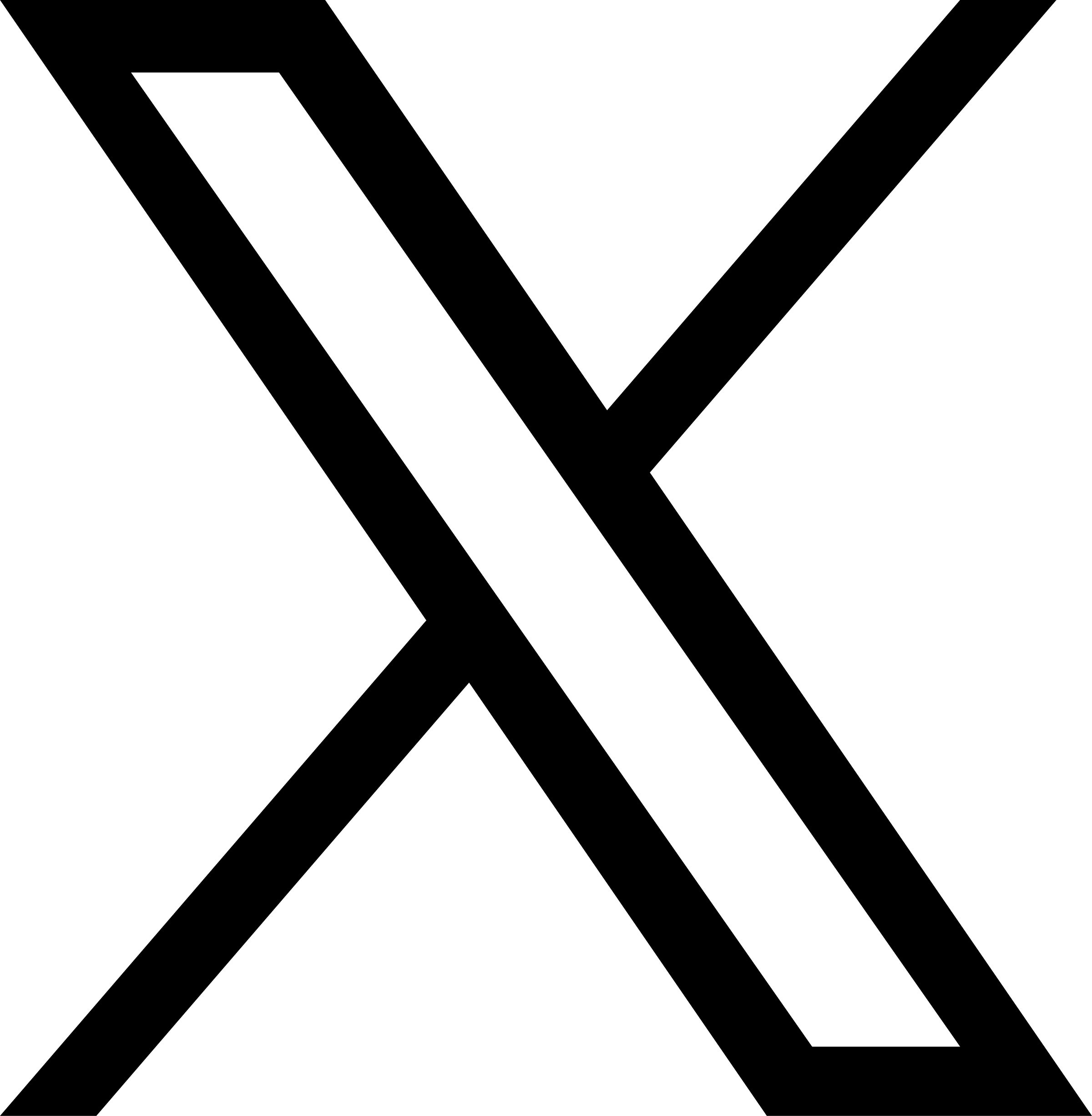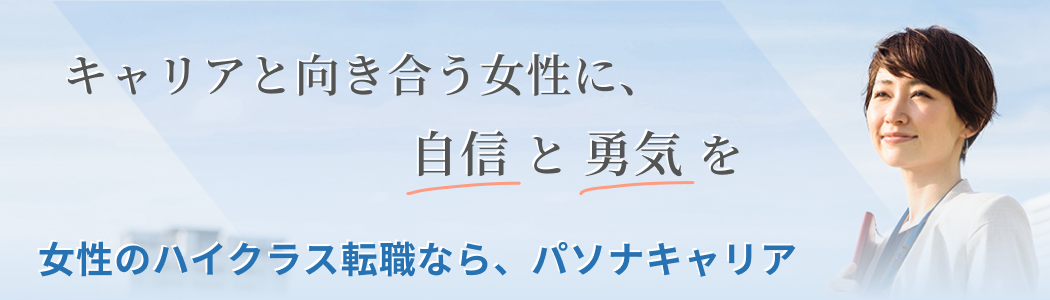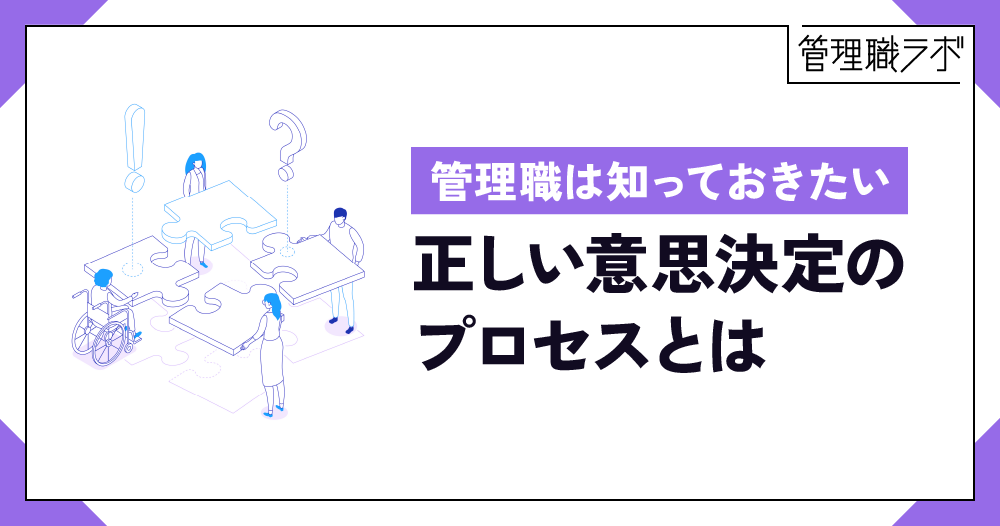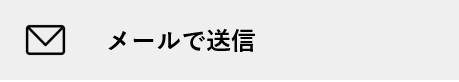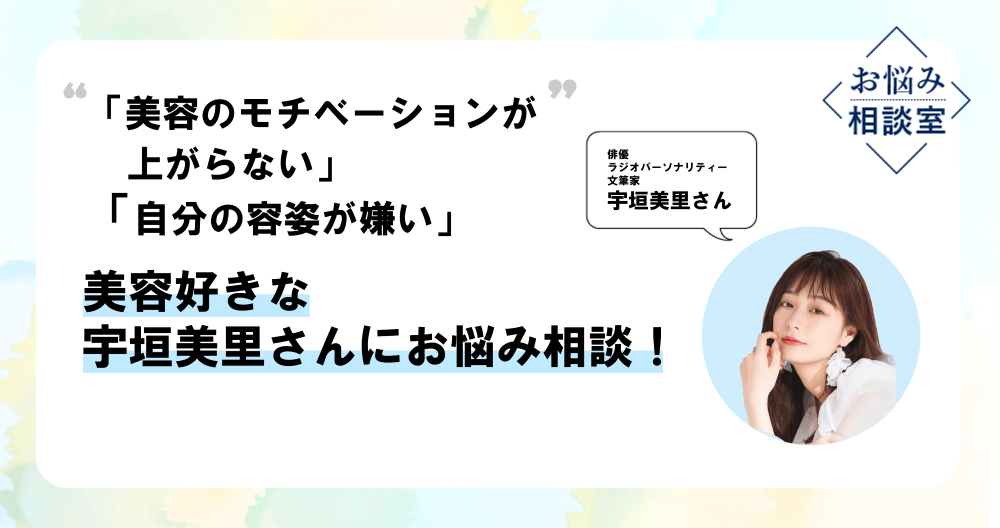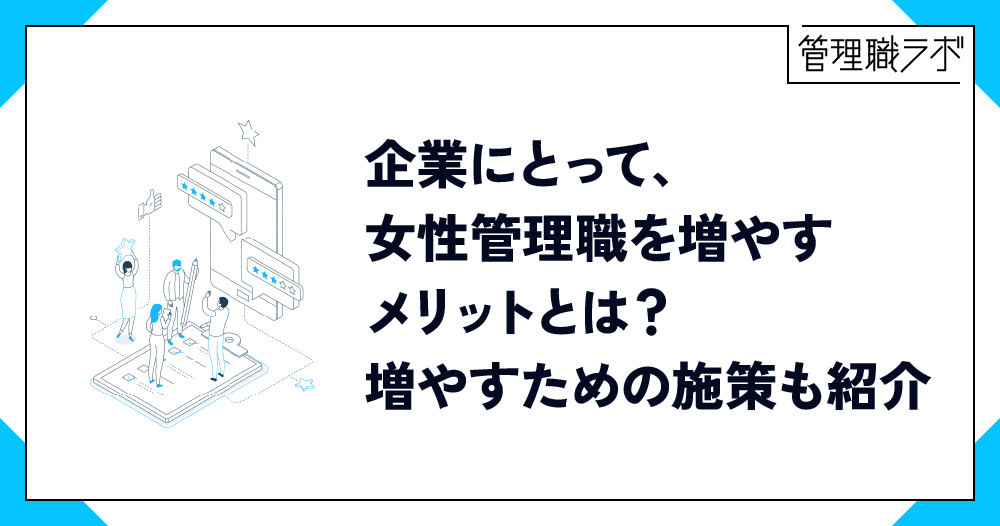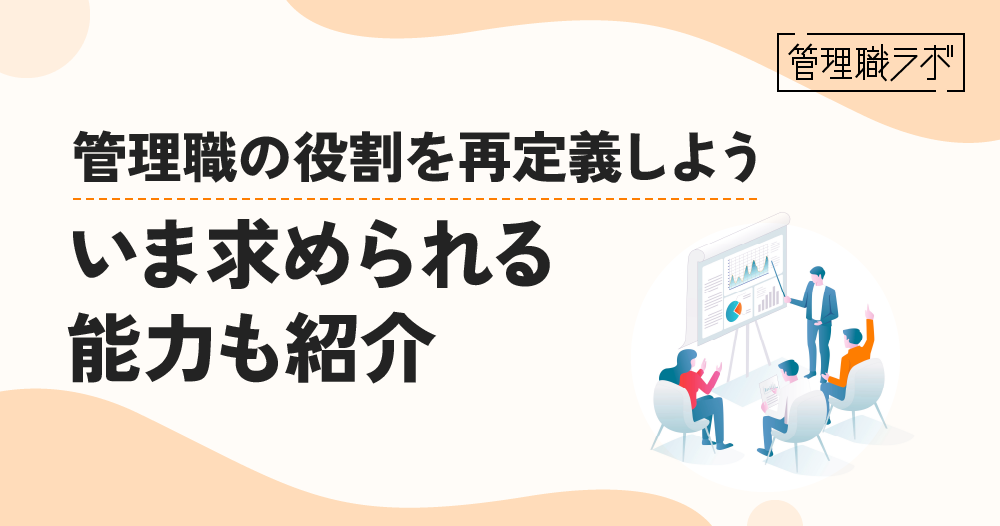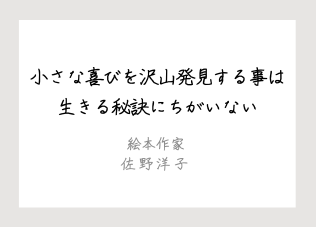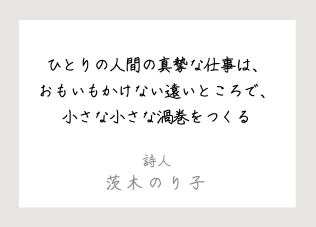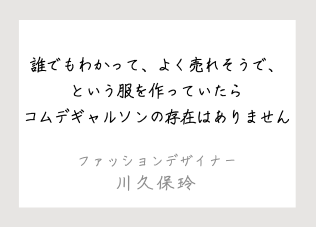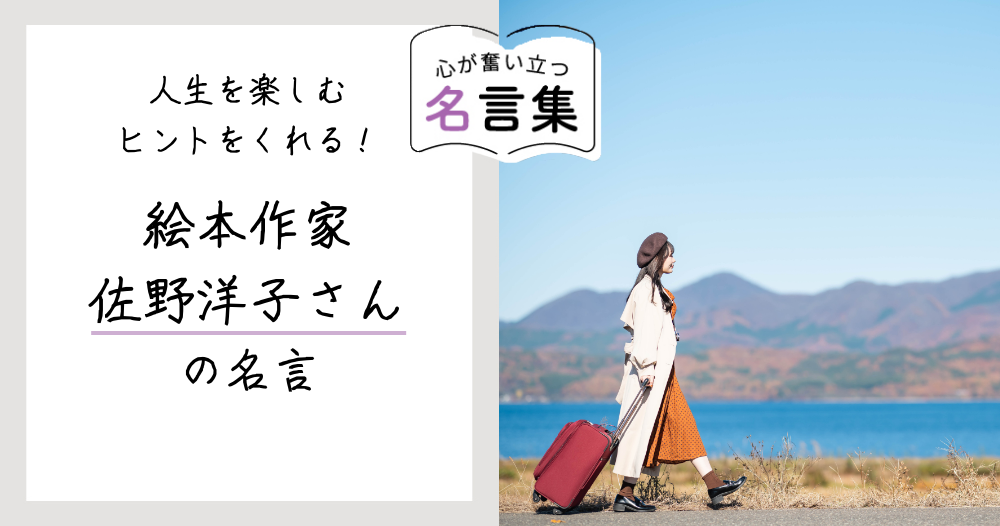ビジネスに必要な意思決定のプロセスとは?7つのプロセスと3つのモデルを紹介
ビジネスにおいて、どのような意思決定を行うかはプロジェクトや企業の成功を左右する重要な鍵です。リーダーや管理職にとって仕事は意思決定の連続であり、重大な責任を感じる場面も多いでしょう。
この記事では、ビジネスに必要な意思決定とは何か、意思決定のプロセスとはどのようなものかを解説します。
目次
ビジネスにおける意思決定とは
意思決定とは、組織の目標達成や問題解決のために複数の選択肢の中から最適なものを選ぶことです。ビジネスにおける意思決定は、企業の成長戦略策定から日常的な業務運営まで、様々な場面で行われています。
社会は常に変化しているため、意思決定者には時に迅速かつ柔軟に判断する能力が求められます。適切な意思決定を行うためには、情報を収集し、仮説を立て、検討し、最終的に決断をするというプロセスが必要になり、これを「意思決定プロセス」といいます。
また、意思決定は、企業の目標を達成するための全体設計、つまり経営戦略を前提とすることもあります。経営戦略について詳しく知りたい方はこちらの記事をご覧ください。
経営戦略とは何か?経営戦略の概要やポイントをわかりやすく解説
意思決定の3つのモデル
意思決定にはいくつかのモデルがあります。ここでは主要なアプローチとして、3つのモデルをご紹介します。
合理的意思決定モデル
「合理的意思決定モデル」は、過去のデータや既存の情報を元に論理的に選択肢を分析して決定する方法です。意思決定者の感情や直感ではなく客観的な分析を根拠としているため、周囲の同意を得やすく、意思決定モデルの中でも最も一般的です。
ただし現実的には、判断に必要な情報がすべて揃っていることは稀です。また、意思決定には期限やリソースの制約が伴うため、情報収集や分析にも一定の限界があります。そのため他のアプローチも必要となるのです。
直感的意思決定モデル
「直感的意思決定モデル」は、データや情報だけに頼らず、意思決定者の経験や直感によって決断する方法です。いわゆる「長年の勘」による判断です。
複雑なデータ分析や理論的な推論を必要とせず迅速に判断を下すことができるため、緊急性が高い状況や不確実性が高い環境において有用です。例えば、医療現場などの緊急対応が必要な場においては特に有効でしょう。ただし、これは経験豊富な人材が意思決定者であることが前提になります。
また、直感に頼るあまり、偏見や誤った前提に基づいた判断が行われる可能性があるため、注意が必要です。周囲の同意を得る際には、その判断を客観的に評価するように心がけましょう。直感的意思決定モデルを重視する意思決定者は、自身のバイアスに捉われすぎず、自らの感覚をアップデートし続けることが大切です。
創造的意思決定モデル
「創造的意思決定モデル」は、問題に関する情報を元に、既存の枠組みにとらわれず新しい発想やアイデアを生み出し、選択するアプローチです。
このモデルは、これまでになかった問題に直面した時や、革新的な解決策が求められる状況で有効です。従来の枠にとらわれない発想を前提とするので、思考を柔軟にし、多様な考え方を可能にします。「VUCAの時代」と呼ばれる変化が多く不確実性の高い現代の社会では、特に必要とされるアプローチ方法だといえます。
注意すべき点は、創造性を追求するあまり、実現性を度外視してしまうことです。このモデルによって出された案は、その後実現可能性を十分に評価するプロセスが必要です。いわゆる「絵に描いた餅」にならないように注意しましょう。
意思決定の7つのプロセス
では、具体的に意思決定はどのように進めていけばよいでしょうか。ここでは意思決定に必要な7つのプロセスについて解説します。
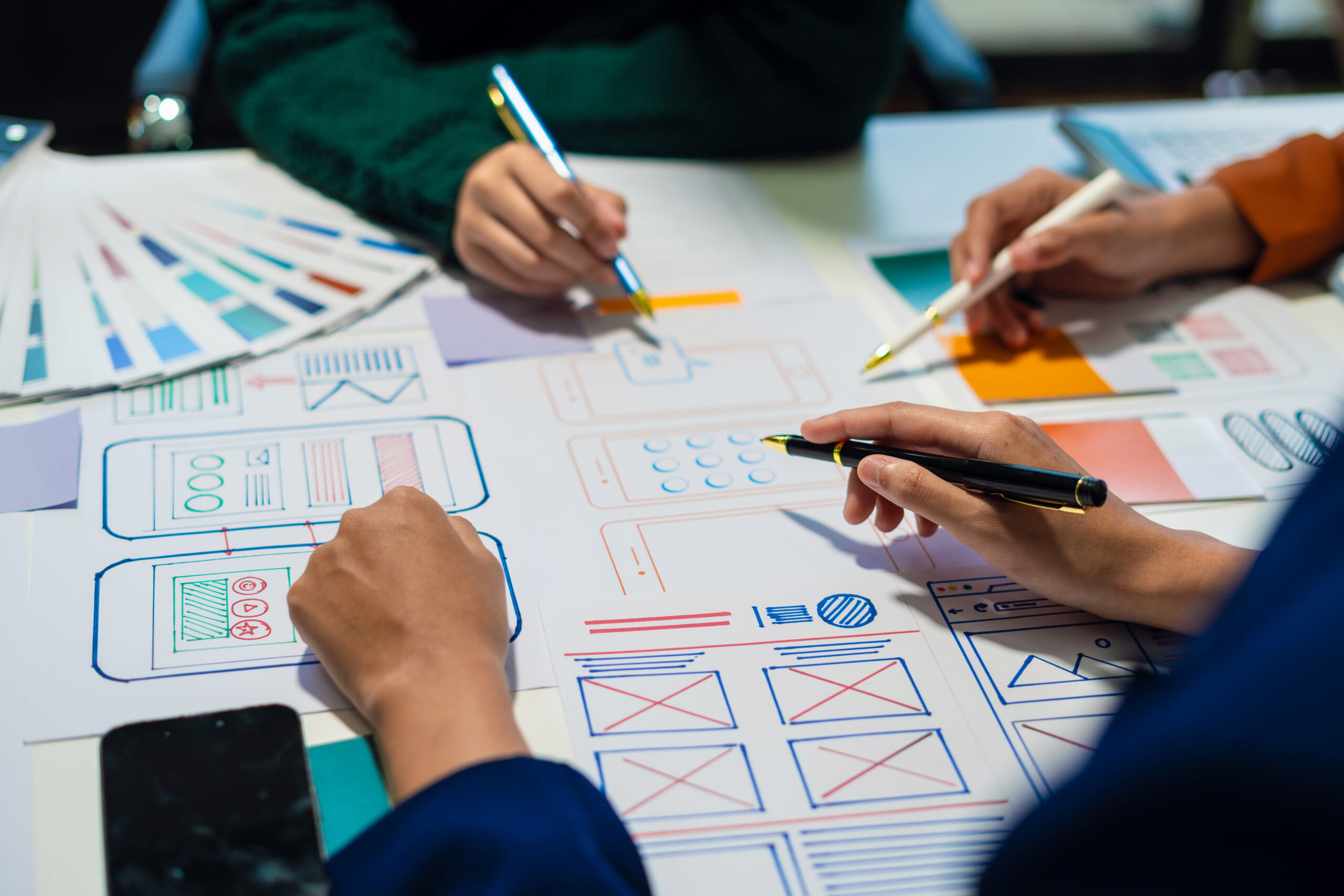
1.意思決定の目的を明確にする
まず、意思決定の目的を明確にします。通常、意思決定とは何らかの目的を達成するために行われます。しかし、この目的が曖昧では意思決定に何が必要かも判断できません。
現状の分析を行い、どこに問題や課題があるのかなどを事前に特定する必要があります。問題や課題を正確に理解すればするほど、後のステップで効果的な解決策を見つけやすくなります。
2.情報の収集
次に、必要な情報の収集です。社内のデータに限らず社外のデータ、専門家の意見など、広範囲で情報を集めることが大切です。場合によっては市場調査やコンサルタントなどの外部協力を求めることも必要です。
また、集める情報の量だけでなく質も大切です。質の程度は問題や課題によっても異なるので、都度定義しましょう。
3.複数の解決策の用意
さて、ここまで収集した情報を基に、複数の解決策を考えましょう。解決策のアプローチ方法は前項で解説した通りです。
今後のプロセスで考案した解決策がうまくいかない可能性もあるため、ここでは一つの解決策に特定せず、複数案を用意しましょう。
4.エビデンスの分析
続いて、ステップ3で用意した解決策のエビデンス(証拠・根拠)を分析します。分析方法には以下のようなものがあります。
・用意した解決策のメリットとデメリットを洗い出す
・フレームワークを用いて分析する(SWOT分析など)
・社内の過去事例(失敗・成功事例)と照らし合わせる
それぞれの解決策についての実現可能性や、どの程度の成果が期待できるかなどを明らかにし、選択肢を絞り込んでいきます。
5.解決策の決定
エビデンスに基づき、最終的な解決策を決定します。ビジネスにおける意思決定には複数の関係者がおり、ニーズはさまざまです。決定段階でも、複数の代替案を用意しておく方が良いでしょう。
6.実行
そして選ばれた解決策を実行に移します。実行段階では、進捗をモニタリングし、また問題が発生した場合には迅速に対応します。
7.見直し
最後に意思決定の結果を評価し、プロセス全体を振り返ります。
・最初に明らかにした解決すべき問題や課題は達成できたか
・それぞれの関係者にとっての評価はどうか
・この意思決定によってどのような良い影響があったか
・この意思決定によって悪影響があったのか
など、成功した点や改善すべき点を明確にすることで、今後の意思決定に活かすことができます。
意思決定プロセスのポイント
ここでは、意思決定を行う上で、注意したいポイントについて解説します。
プロセスの順番を守る
まず、原則として意思決定のプロセスの順番は守りましょう。特に「意思決定の目的を明確にする」「複数の解決策の用意」については順番が前後しないように気をつけます。
意思決定の際、話し合いが解決策の提示に終始してしまうことはよくあります。しかし、解決策というのは、問題や課題によって大きく異なる部分です。そのため、まずは意思決定の目的を明確にし、何のために意思決定をするのかという認識を関係者の中で揃える必要があります。
とは言えいくつか例外はあり、迅速な判断が必要な場合「情報の収集」や「複数の解決策の用意」「エビデンスの分析」などをスキップすることもあります。特に「直感的意思決定モデル」では、スピード感を重視し、これらを省いて即座に判断を下すこともあります。
ロジカルシンキングで考える
意思決定プロセスでは、収集したデータや事例が役立つか、策定した解決策が効果的かを論理的に判断する必要があります。周囲の合意を得なければいけない場合、意思決定を客観的に判断するにはロジカルシンキングが重要です。
「合理的意思決定モデル」や「創造的意思決定モデル」はもちろん、「直感的意思決定モデル」に関しても、他者に説明する時にはロジカルシンキングを用いることで、チーム内の合意形成が取りやすくなります。
リスクを把握する
意思決定を進める際には、リスクを把握することも非常に重要です。
エビデンスの分析の際には、起こり得るリスクについても考えるようにしましょう。過去の成功事例が現在の状況と完全一致していることはあり得ません。現在の社会状況に照らし合わせ、どんなリスクがあるか再考することが重要です。
また、プロジェクトごとに関わる人間も変わります。たとえ合理的な説明をしたとしても、意見の不一致や反発といったリスクは起こり得ます。どのような反論が起きそうか想定しておくと良いでしょう。
リスクは完全に排除できるものではありませんが、リスクを想定した上で影響を最小限に抑えるための準備は必要です。
まとめ:意思決定プロセスを使ってスムーズに意思決定を行おう
意思決定はビジネスをする上で避けては通れません。特に管理職やプロジェクトマネージャーなど、社員を統括する立場になればなるほど、意思決定の比重は増します。
ただ漫然と意思決定を行うのではなく、プロセスを継続的に見直し、改善していくことで、組織の意思決定力を向上させていきましょう。
管理職やプロジェクトマネージャーについては以下でも解説していますので、詳しく知りたい方はご覧ください。
中間管理職の役割とは?求められる能力やストレス対策を解説
プロジェクトマネージャー(PM)の役割とは?取得したい資格や必要なスキルを解説