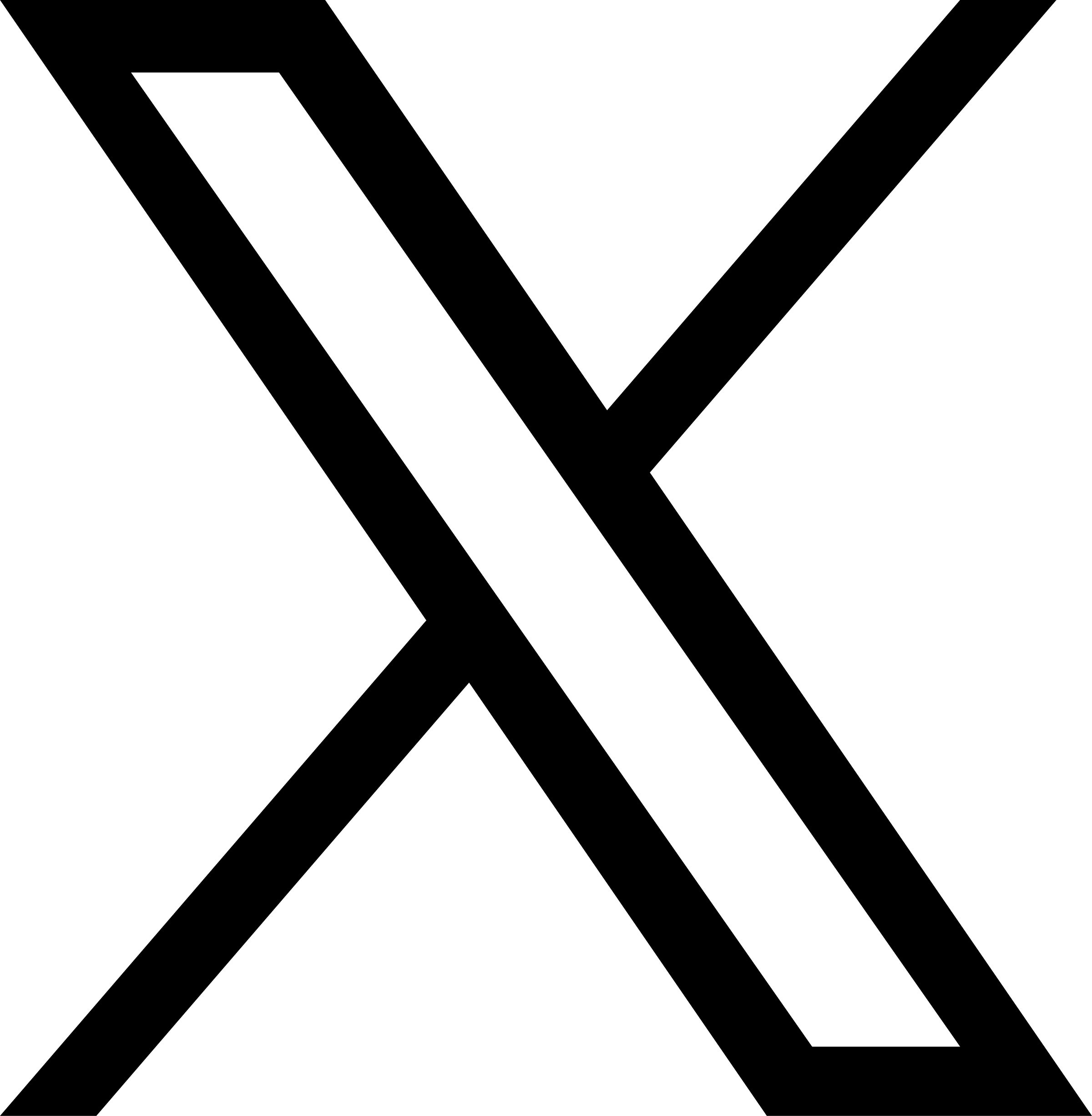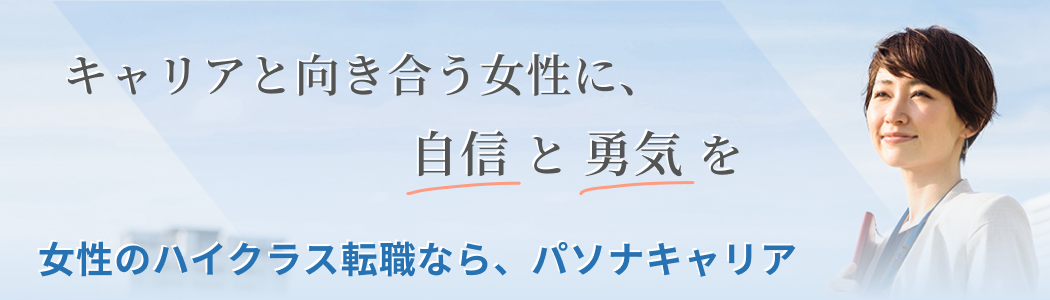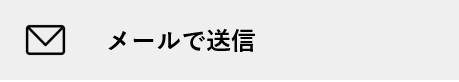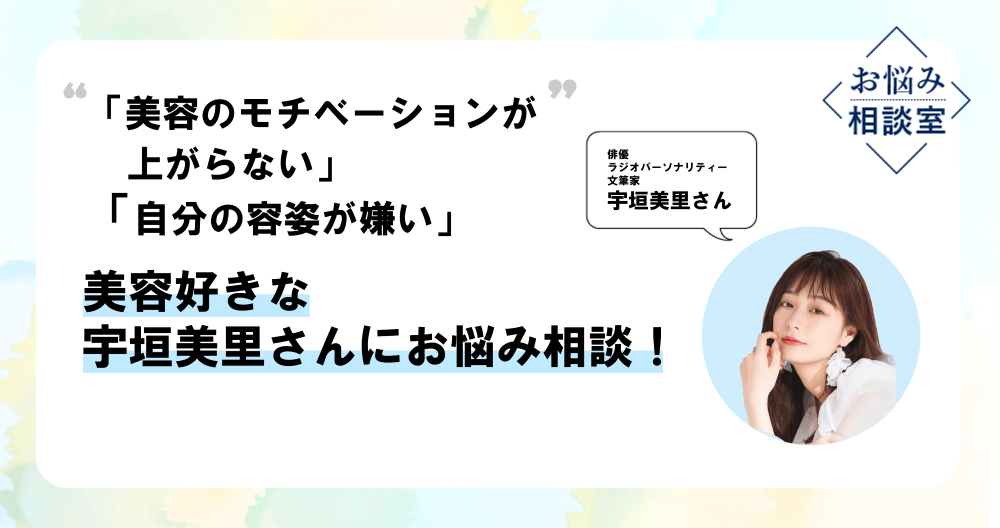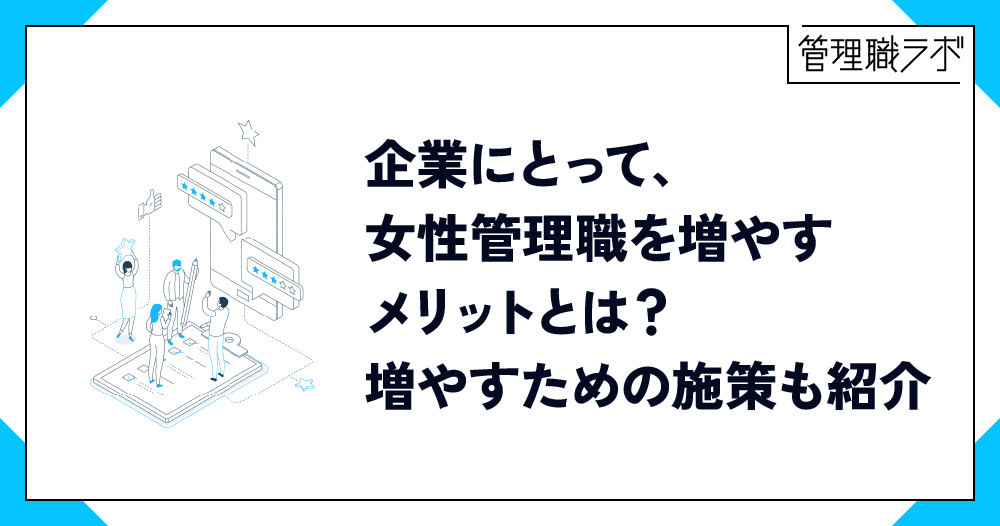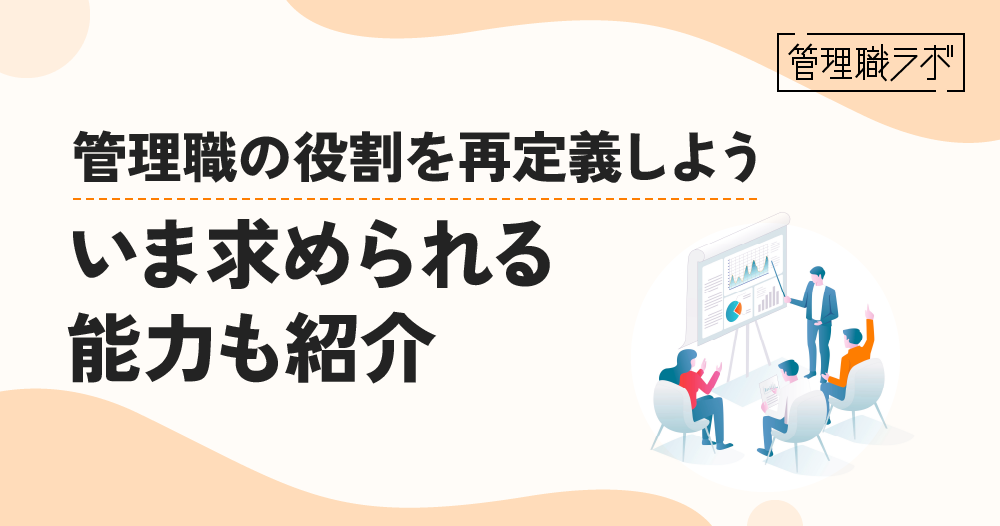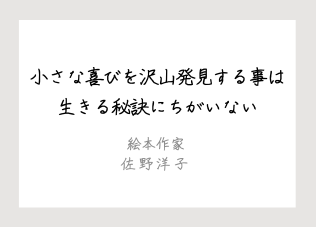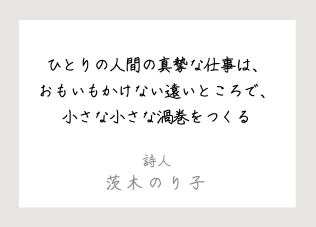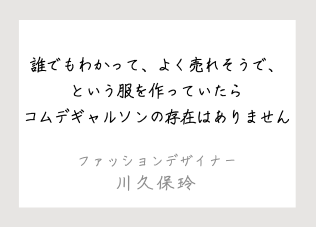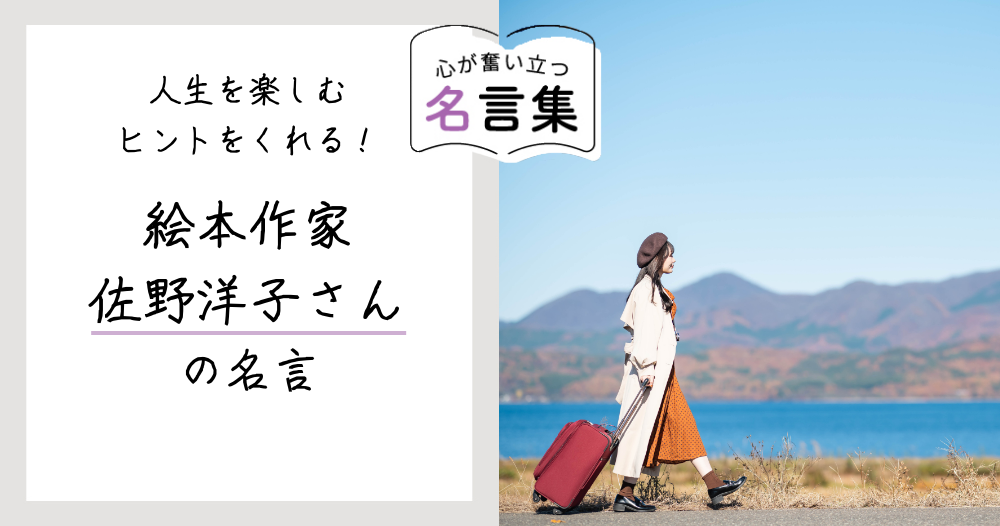生理痛・メンタル不調・気象病…「頑張らない養生」で心と身体を整えよう
『心と体を整えるおいしい漢方〜季節の食養生で不調を改善』(扶桑社)の著者であり、鍼灸師、国際中医専門員の田中友也さんに、働く女性の未病に対処する方法を伺う特別インタビュー。後編では、症状別の養生をお聞きしました。頑張りすぎずに体と心を労わるためのヒントが詰まっています。

田中友也さん
鍼灸師、国際中医専門員、国際中医薬膳管理師、登録販売者資格保持。関西学院大学法学部卒業後、北京中医薬大学、上海中医薬大学などで研修。現在、兵庫県にあるCoCo美漢方(ここびかんぽう)で日々、健康相談にのる傍ら、鍼灸師として施術も行う。著者に『心と体を整えるおいしい漢方〜季節の食養生で不調を改善』(扶桑社)、『不調ごとのセルフケア大全 おうち養生 きほんの100』(KADOKAWA)、『体とココロが喜ぶごほうび漢方』(主婦の友社)、『こころと体がラクになる ツボ押し養生』(Gakken)など。
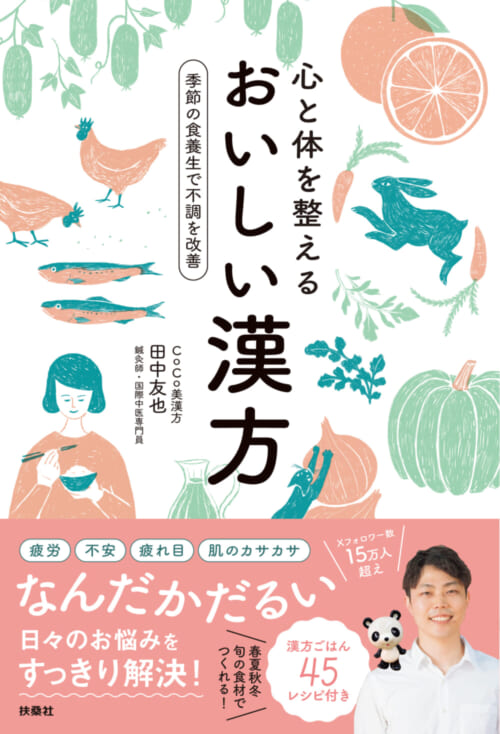
生理痛、メンタルの不調、気象病。症状別の養生は?
- ー今回は女性の悩みで特に多い不調の養生についてお聞きします。まずは生理痛の原因と対処法から教えてください。
- 田中:中医学は原因によって対処を変えるので一概には言い切れないのですが、生理痛は冷えやストレスによって血の巡りが悪いことが原因となることが多いです。血の巡りが悪い時の生理痛の特徴として、特に生理初日や2日目など生理の前半に痛みがひどいことや、動けなくなるほどの痛み、血の塊が出る、血の色が暗いなども挙げられます。
特に、夏場は冷たい食事を摂取する機会が増え、服装も薄着になり、冷房にあたる機会が増えるので、身体が冷えやすく生理痛の相談が増えます。
対処法としては、やはり冷たいものを避けて身体を温めること。とはいえ夏場に長袖を着るのは難しいので、冷房の効いた部屋ではブランケットを使うとか、薄い夏用の腹巻でお腹周りだけ温めるとかですね。
特に日本人はお寿司やビールなど、冷たいものが大好きですよね。実は中医学が浸透している中国や韓国は、夏場でも温かいお茶を好む方が多いんですよ。なので、普段飲むものを常温にしてみるとか、お味噌汁を飲むようにするとか、無理ない範囲で冷え対策を行ってください。あとはこまめにストレスを発散させることも大切です。
- ー夏でも食べれるような体を温める食材はありますか?
- 田中:夏の食材は体を冷やすものが多いのですが、紫蘇、ミョウガ、ネギ、唐辛子、山椒などの薬味は体を温めてくれます。他にも海老やラム肉、鶏肉などの肉類も身体を温める食材です。
- ーメンタルの不調はいかがでしょうか?
- 田中:メンタルの不調は、落ち込むタイプとイライラするタイプで対策が異なります。
落ち込むタイプの場合は、「血」が不足している状態なので、それを補うこと。「血」は寝ている間に作られるものなので、質の良い睡眠をしっかりとるようにしましょう。また「血」を使うことになるスマホやパソコンの見すぎにも注意してくださいね。あとは脳も「血」を使うので、考え事が多い人も「血」不足して落ち込んでしまいがちです。
ただ、女性は生理があるので、どうしても「血」が不足してしまうんです。食材などで補うことも良いですね。血を補う食材は、赤いものや黒いもの。例えばレバーやいちご、クコの実、黒ゴマ、黒豆、ひじき、きくらげなど。他にもブルーベリー、小松菜、ほうれん草も血を補います。
ちなみに中医学では、血と汗は同源だと考えます。なので汗をかきすぎることで足りなくなった水分は、血で補うことになります。すると血も不足するわけです。なので、最近流行りのサウナも血不足の原因になり得るのでは?と、個人的には思っています。
一方、イライラするタイプの場合は、「気」の巡りが滞ってガスが溜まっていることが多いです。なのでイライラするとお腹が張ったり、胸が張ったり、ゲップやおならが増えることがあります。そういった症状が出ている場合、ストレスを発散することが重要です。誰かに話を聞いてもらったり、鼻歌を歌って口から溜まっているものを出してくださいね。
あとはストレッチをするのも効果的ですね。身体の横側に「気」の通り道があると言われているので、脇や身体の側面を意識して伸ばしたり、揉んだりすることもオススメです。

- ー低気圧の時に身体がだるくなったり、頭痛がしたりする気象病の対処法も気になります。
- 田中:気象病と関係してくるのが五臓の「脾」で胃腸のこと。胃腸は身体の中心で食べ物を消化吸収するだけでなく、水を全身に運ぶ役割もあります。皆さんも経験があるかと思うのですが、梅雨や夏場は食欲がちょっと減るのは、胃腸が湿気に弱いからなんです。低気圧の時も、天気が悪くなり湿度が高くなりがちですよね。だから胃腸の働きが弱まり、身体の重だるさが生まれるのです。
対策としては、身体の水はけをよくして胃腸を元気にすること。内臓は体温よりも少し高い37度だと言われているので、ここでも冷たい物の摂取しすぎは禁物です。
また、胃腸を元気にする食べ物として、かぼちゃ、さつまいも、トウモロコシ、きのこ類、米、豆類などがあります。他にも、体に溜まった湿を追い出す、利尿作用のある食べ物も気象病には有効です。もやし、レタス、はと麦、海藻類、小豆、バナナなどですね。
自分らしくいることで、元気や血も巡る
- ー飲酒、喫煙、カフェインは、中医学的にはNGなのでしょうか?
- 田中:やはり喫煙は五臓の中でも「肺」を弱らせるので控えた方が良いと思います。肺の呼吸で吸収した酸素と「脾(=胃腸)」から消化吸収した栄養が合わさり「気」が作られます。なので、肺が弱ってしまうと、元気が作られにくくなるんです。
お酒は飲みすぎると体に良くありませんが、適量であれば血流を良くする効果もありますよ。ただ、適量が難しいんですよね(笑)。あくまでほどほどを意識してください。
コーヒーや緑茶は、薬膳の考え方だと頭をシャキッとさせる効果があると言われてます。また、コーヒーと紅茶は身体を温める食材ですし、緑茶は身体を冷やす食材です。これからの季節、頭に熱がこもってのぼせやすい方は緑茶が良いかなと思います。
- ー最後に、Bemyself読者にメッセージをお願いします。
- 田中:「頑張りすぎないこと」を頑張りましょう。皆さん本当に頑張りすぎです! 余白をつくることって、勇気がいることですし、不安を感じてしまうこともあるかと思います。特に今の時代、SNSでみんなが活躍しているように見えて「自分はこれで良いのかな」と思ってしまいますよね。でも、人それぞれの役割は違うので。人は人、自分は自分です。周りに合わせて焦ってしんどくなるのではなく、自分を大切にしてほしいですね。
自分らしくいることで、身体の元気や血も巡るんですよ。「楽しい!」「やりがいがある!」と感じ、生き生きすることって中医学の視点でもとても大事。人それぞれ活躍できる場所はあると思うので、自分の好きなことややりがいのあることを見つけてください。そして無理をせずに自分の不調に目を瞑らず、早めのケアを心がけましょう。