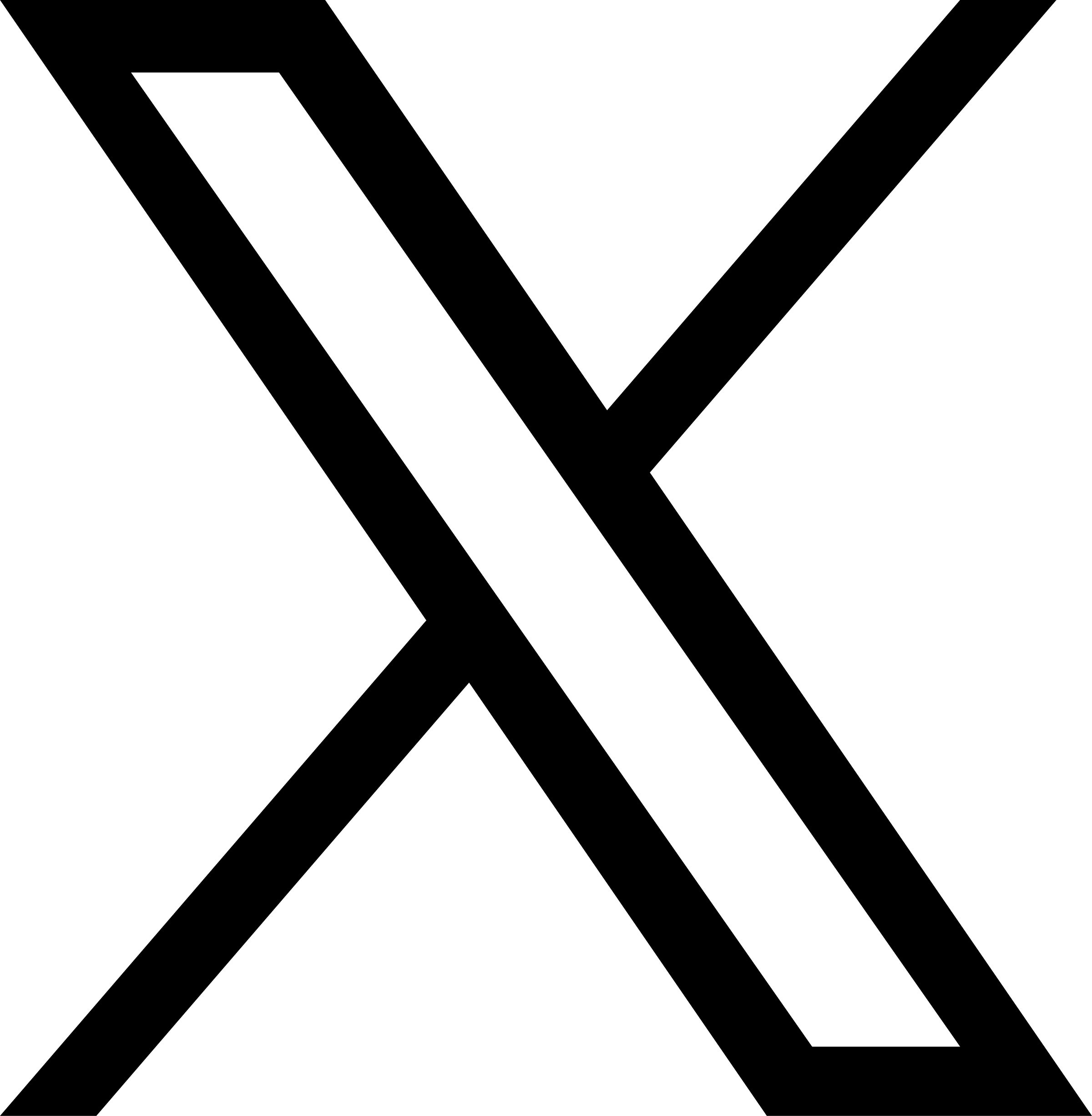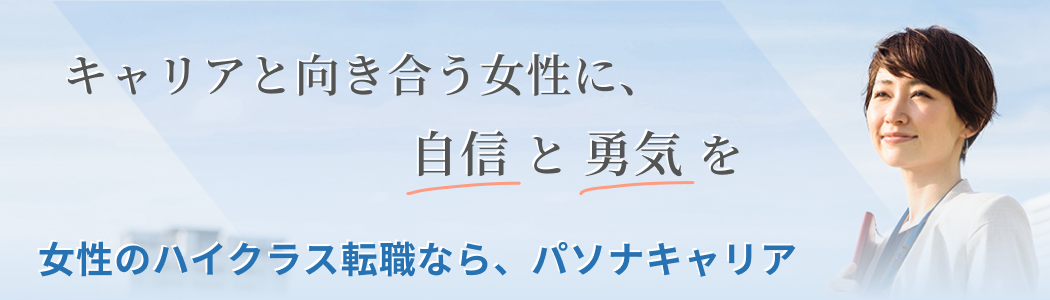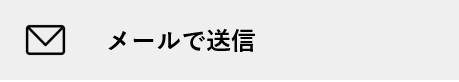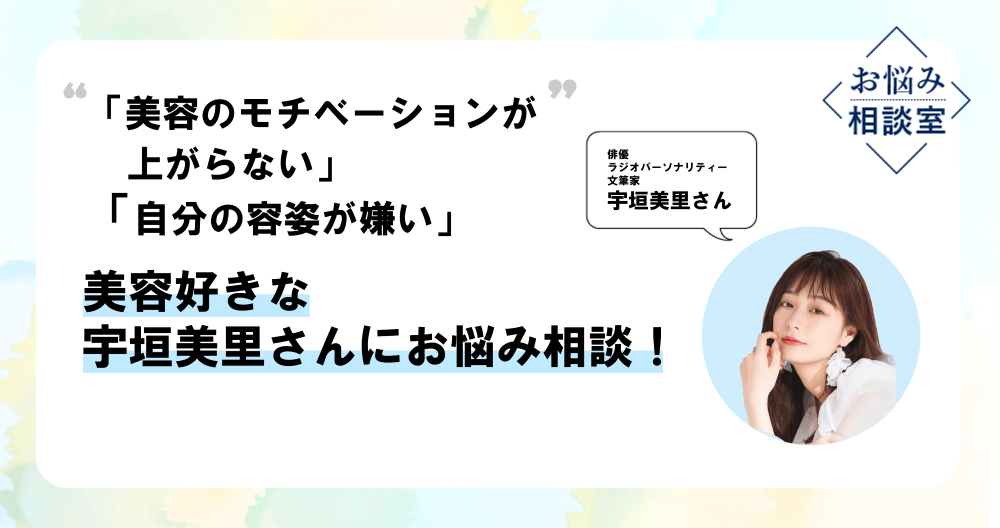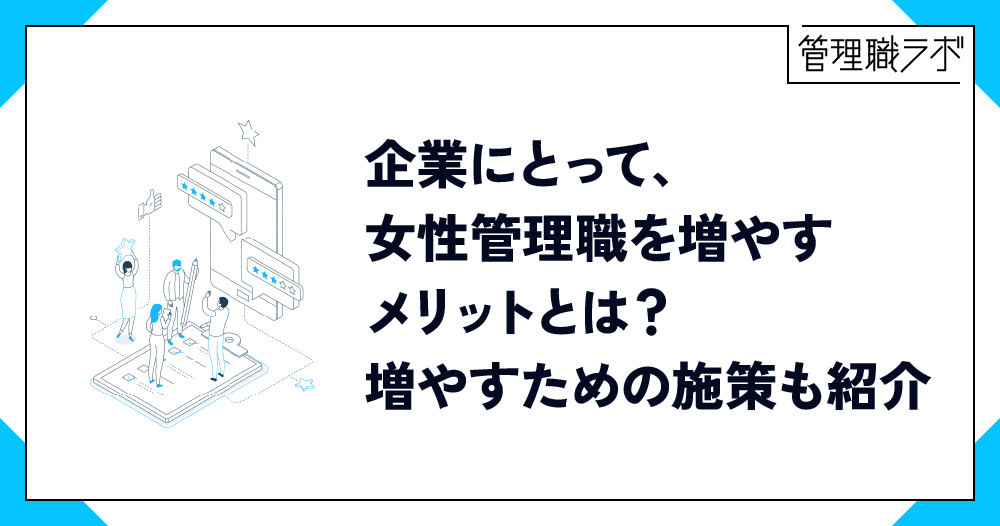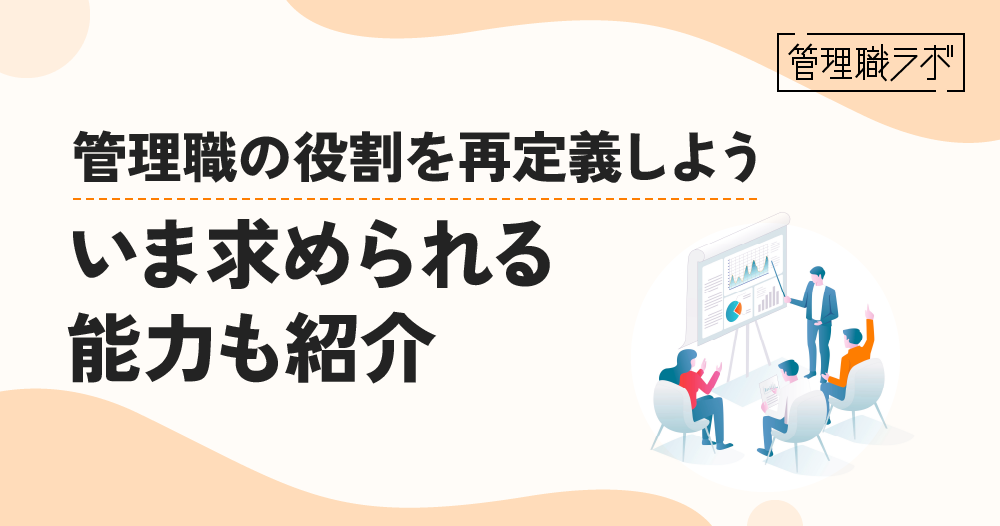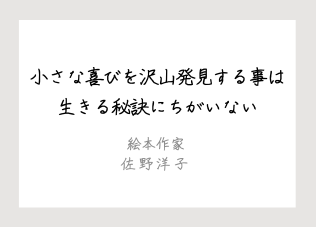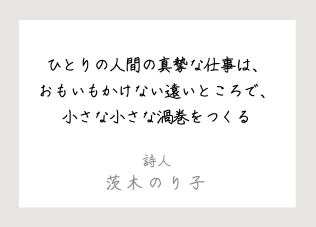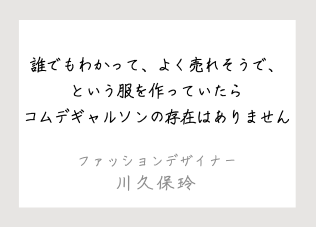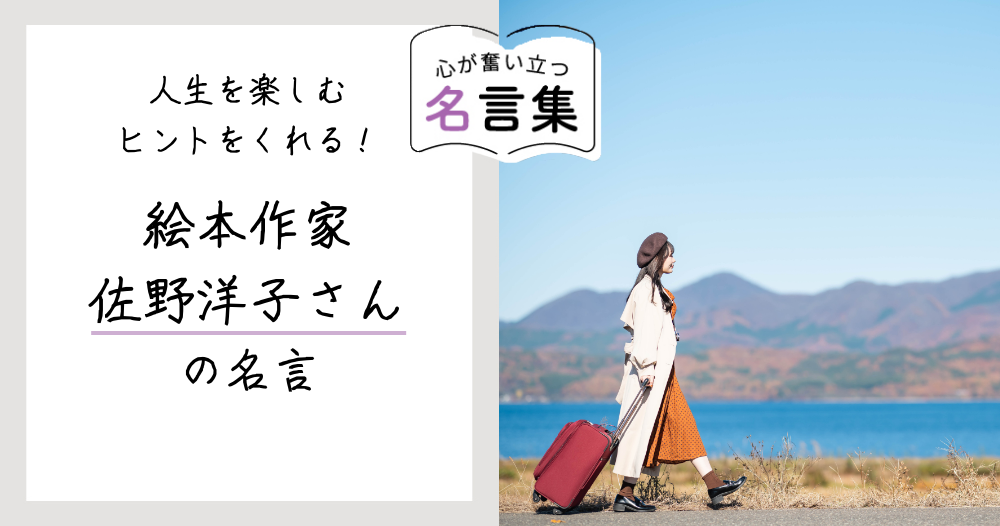【千葉佳織さんインタビュー】話し方が評価に直結する時代。良きリーダーのための話し方
会議や商談、部下の指導など、何かと人前で話す機会が多い管理職。しかし、「話し方」について学んだことがある方は少ないのではないでしょうか? 今回は、『話し方の戦略「結果を出せる人」が身につけている一生ものの思考と技術』(プレジデント社)の著者であり、スピーチライターの千葉佳織さんに、働く上で身に付けるべき「話し方」について教えていただきます。前編では話し方を改善する上で押さえるべき基本を伺いました。

千葉佳織さん
株式会社カエカ代表/スピーチライター
1994年生まれ。15歳から「弁論」を始め、2011年から2014年までに内閣総理大臣賞椎尾弁匡記念杯全国高等学校弁論大会など3度の優勝経験を持つ。慶應義塾大学卒業後、新卒でDeNAに入社。2019年、株式会社カエカを設立。AIによる話し方の課題分析とトレーナーによる指導を組み合わせた話し方トレーニングサービス「kaeka」の運営を行う。
リーダーに求められるスキルに「話し方」が含まれるように
- ―まず「スピーチライター」とはどういった職業なのでしょうか?
- 千葉:スピーチライターの仕事は、経営者の方や政治家の方が使用する「スピーチ用の原稿」を一緒にブラッシュアップすることです。加えて私の場合、スピーチトレーナーとして話し方を改善するトレーニングも行っています。トレーニングでは、言葉の抑揚や話す際の動作も指導しています。
- ―千葉さんはなぜ、スピーチライターになったのでしょうか? ご自身のキャリアを簡単に教えてください。
- 千葉:元々は高校生の頃、弁論という日本語スピーチ競技の部活に入っていたことがきっかけです。大会に出るために周囲の方から話し方のフィードバックをもらうことを繰り返していました。中高一貫校に通っていたので、高校生だけど中学1年生からフィードバックをもらうこともしょっちゅう。部活動を通して、話すことに向き合うという経験をしました。
弁論の全国大会で優勝して大学に進学したこともあり、自分が変わるきっかけとなった「話し方の学習」のサポートを通じて恩返しがしたいと思っていました。そこで、新卒で入社したDeNAでも社内向けに話し方のトレーニングを行いたいと声をあげました。その後、独立し、今に至ります。
- ―ありがとうございます。スピーチトレーニングは、一般の社会人も受講されているのでしょうか?
- 千葉:実は、私が代表を務める株式会社カエカが提供している「話し方トレーニングkaeka」の利用者の多くは、一般の社会人の方です。例えば営業職、人事、エンジニア職、また学校の先生など、職種は多岐にわたります。
- ―管理職にとっても、「話し方」はやはり大切なスキルなのでしょうか?
- 千葉:上手に伝えたり、話したりできることが、リーダーに必要なスキルの一部になってきているのではないでしょうか。チームをまとめたり、メンバーを鼓舞したり、自分の頑張りを他の人に波及させたりするのにも、話し方が大切です。個人的には、話し方が評価に直結する時代になったと言っても過言ではないと感じます。
実は私たちの平日の平均話量(1日のうち話している時間)は6.1時間とも言われているんです。つまり、人生の4分の1の時間は話しているということ。そう考えると、その質を高めることの重要性をより感じられるかと思います。
- ―たしかに、思った以上に話をしていることに驚きました。
- 千葉:ただ、学校や社会でも、話し方を教えてもらう機会ってあまりないですよね。だからつい後回しになってしまう。話し方をよくしたいと思っても、そもそもの方法論がわからない方がほとんどだと思います。
海外だと学校教育の中に話し方を学ぶプログラムもあるのですが、日本はまだまだ足りていない状況だとも感じてます。
管理職が忘れがちな「話す目的」
- ―では、話し方を改善するために、まず何から始めれば良いのでしょうか?
- 千葉:まず大前提として、「話す目的」を明確にすることです。とても当たり前のように感じますが、話す場面がルーティン化してくると、ここが薄れてしまうことって結構多くて。例えば、自己紹介をする際、その目的まで考えられていない方が多いと思います。特に管理職の方は、話す場面が多くなるため、とりあえず「いつものフォ-マット」でその場を乗り越えようという気持ちが強くなってしまうのだと思います。
- ー「話す目的」とはどう設定すれば良いのでしょうか?
- 千葉:目的は、定量的でも定性的でも問題ありません。定性的な目的だと、「自分のことを信頼できると思ってもらいたい」「このテーマに興味を持ってもらいたい」「話を聞いた部下に次の行動を起こしてもらいたい」など。これくらい粒度が粗くても大丈夫です。
定量的な目標は、「スピーチを聞いた方へのアンケートで9割の方に『満足』の評価をいただく」などの数字に落とし込んでもらえたらと思います。
まず目的を明確にした上で、そのための技術を磨こうとする。ここがスタートです。
- ―実際に話し方の技術を磨く上で、押さえるべきポイントは?
- 千葉:話し方を「コンテンツ」と「デリバリー」の二つの軸に分けて認識してください。
「コンテンツ」は、いわゆる「言葉」そのものです。話したい内容の言語化力や構成力などを指します。事実をわかりやすく伝えるための言葉選びや、話に引き込むための物語の流れをつくるスキルですね。
一方「デリバリー」は、声の抑揚や大小、高低スピードや、ジェスチャーなどの動作のこと。
この違いを理解した上で、自分はコンテンツとデリバリーのどちらに不安を抱えていて、その中でも何が課題なのかを見極めることが重要です。
弊社のサービスでも、一番最初にAIを使った話し方の診断をしています。なかなか自分の話し方の癖を分析することは難しいので、第三者からの指摘が効果的です。
■後編では、部下の指導、プレゼン、プライベートなど…、シチュエーション別の話し方のコツを伺います。