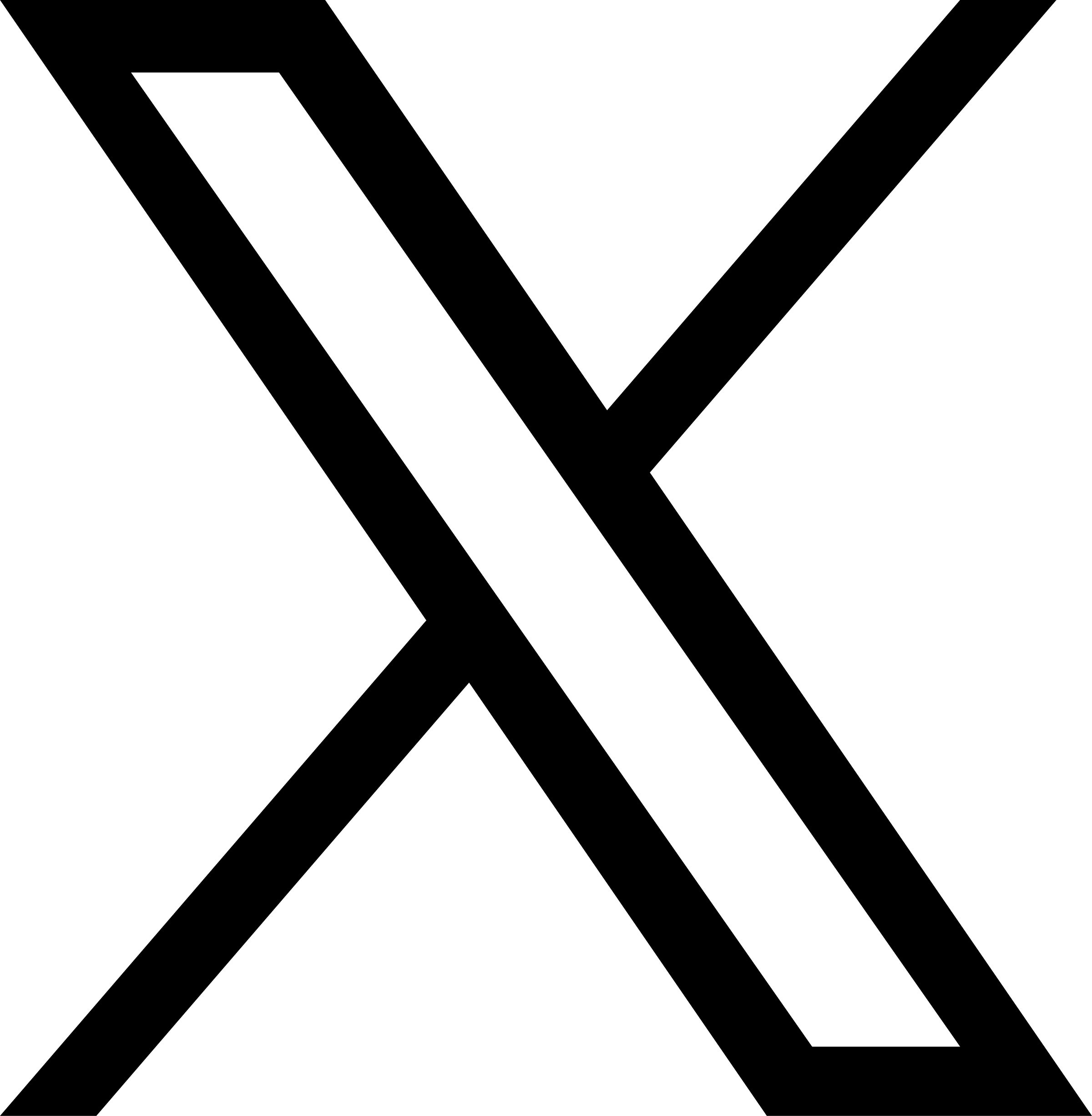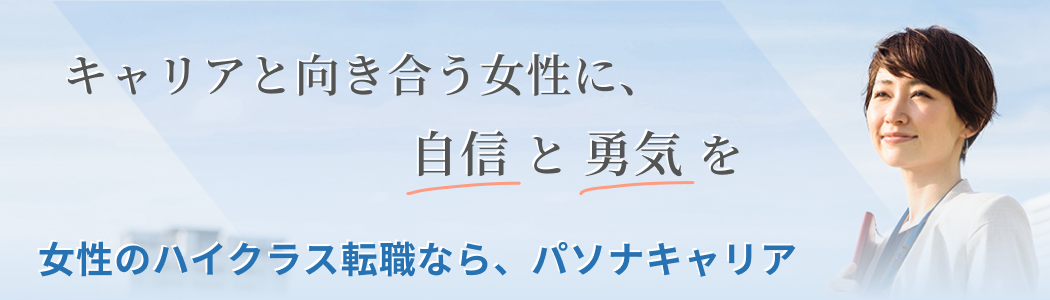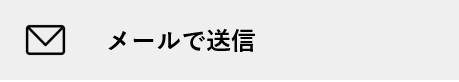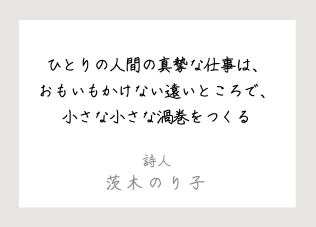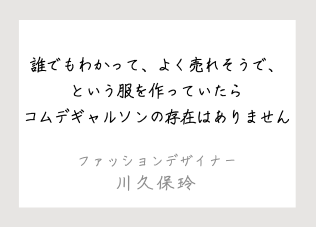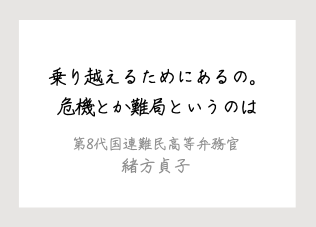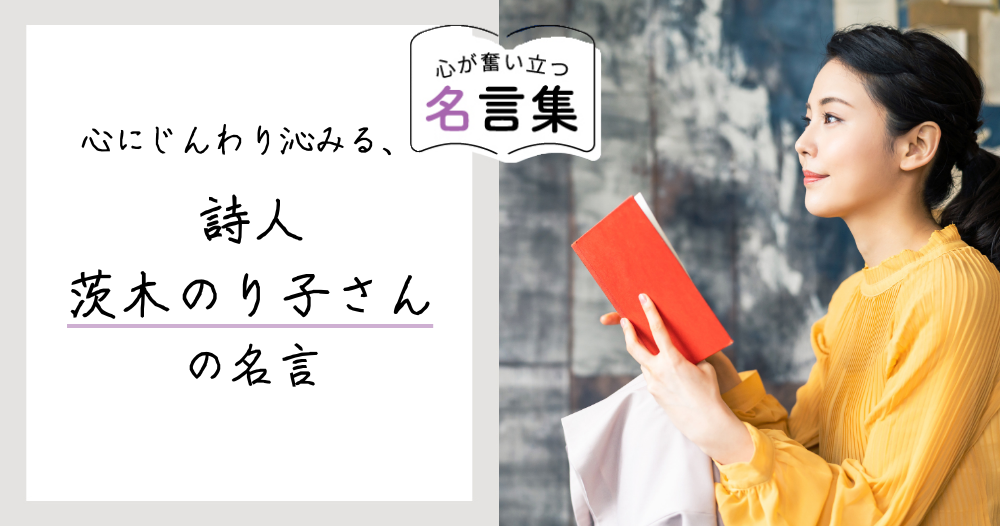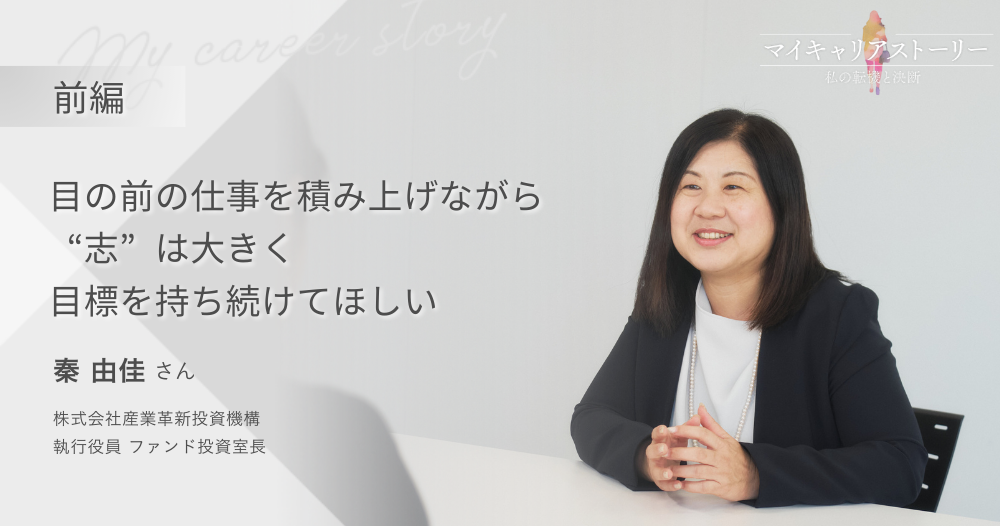職場のルールと心理的安全性 〜共通認識が生む安心感と生産性〜
職場におけるルールは、単なる決まり事ではなく、私たちが安心して働くための土台であり、心理的安全性を高めるための重要な要素です。ルールが明確であることで、従業員は自分の行動を予測しやすくなり、より良いパフォーマンスを発揮できるようになります。
しかし「ルール」と聞くと、どこか堅苦しく窮屈なものと感じる方もいらっしゃるのではないでしょうか。そこで本記事では、ルールと心理的安全性の相互関係について深掘りするとともに、ルールという共通認識がもたらすメリットや職場での取り入れ方について詳しくお伝えします。
目次

小野 みか(おの みか)さん
一般社団法人ライフデザイン・アカデミー代表理事
合同会社MYGIFT代表
1978年生まれ東京育ち。 牧師である父親が運営するプロテスタント系教会で育つ。 3歳から舞台に立ち、子役として多数のミュージカルに出演。表現力を磨く。22才で結婚・出産。うまくいかない子育てに悩み、そこで初めて「心理学」を学び始める。
クリスチャンが学ぶ「幸福論」と行動心理学などのメソッドを融合した「ライフデザイン教育」を生み出し、全国35を超える地方自治体や、上場企業の講師として全国を飛び回り活動している。プライベートでは4児の母。
一般社団法人 日本心理的安全教育機構HP
職場におけるルールとその役割
ルールと聞いて、皆さんはどのようなものを思い浮かべるでしょうか?中には、地域におけるゴミ出しの決まりや、学校の教室に掲げられていた「よく遊び、よく学ぶ子」といった標語、門限・お手伝いの担当などの家庭内での決まりごとを思い出す方もいるかもしれません。
一般的にルールとは、物事を行う上で守るように定められた約束事です。その中で、「職場におけるルール」は、就業時間や仕事の進め方といった基本的なルールや、チームの目標達成や成果を上げるために具体的にどんなことをするか、またはしないかという行動指針が定められています。
また、企業単位だけではなく、「営業部のローカルルール」、「総務部のローカルルール」といった具合に、部署などの小さな組織単位でのルールが定められていることもあります。こうした特定の組織、コミュニティにおけるルールは、ハウスルールやローカルルールと呼ばれます。
職場におけるルールは、チーム内での心理的安全性を高め、メンバーが各自の役割を理解し、目的を果たすための行動を明確にする助けとなります。ルールを設けることで、その組織に所属するメンバーに「何をすべきか」「どうあるべきか」が伝わり、望ましい行動を促すことができます。
ルールと心理的安全性の関係
ではなぜ、ルールを作ることが職場の心理的安全性を生むことに繋がるのでしょうか。その理由は2つあります。
1.予測可能性が心の安心を作る
1つ目の理由は「予測可能性」が生まれるためです。予測可能性とは、未来の出来事(危険・評価・相手の反応など)をあらかじめ予測できることを指します。
人間は、事前に予測ができると安心感を覚えやすい生き物です。たとえば、料理をする場合にレシピがあって作るのとレシピなしで作るのでは安心感が全く違う方も多いのではないでしょうか。ある程度のレシピが用意されていれば、作る手順や時間、材料などがあらかじめ分かっているため、自分が何をすべきか、そして結果も予想しやすいでしょう。
職場においても同様で、ルールが設定されていると、「会社でどう振舞えばよいのか」「自分の行動が上司にどのように評価されるのか」が理解しやすくなります。組織において何が評価されるのか予測できない場合、何にどれくらい取り組まなければいけないのかが不明確で、やみくもに力を使わなければなりません。予測可能性が生まれることで、安心して行動することができます。
2.脳に余計なストレスをかけないことが心理的安全性に繋がる
2つ目の理由として、職場が円滑に回るためのルールが決まっていることで、自分の脳のリソースを過剰に使わずに済むためストレスが少なく、心の余裕や安心感が生まれやすいことが挙げられます。
誰もが知る経営者であるスティーブ・ジョブズ氏やマーク・ザッカーバーグ氏が、脳に余計なストレスを与えないように、毎日同じ服を着ているという話は有名ですよね。人間の脳は選択をしたり、決断をしたりするときに大きなストレスがかかります。そのため、何をすればいいのかが決まっており、余計な脳のリソースを使わずに済めば、自分の時間効率を上げていくことに繋がります。また、何かトラブルが起こったときにルールや基準が明確にあれば、ノンストレスで判断することが可能です。
たとえば、9時出社・6時退勤といった基本ルールがあることで、そのルールの枠の中で計画を立てることができます。しかし、ルールが不明確で「何時に来て何時に帰ってもいいよ」と言われると、途端に自分で1からプランニングしなければなりません。つまり、自分自身で選択し、決断しなければならない事項が増えることになります。その結果、「どうやって計画を立てるのか」「他部署とどう連携を取るのか」など、悩んでしまう機会も増えるでしょう。
職場にルールがない場合のリスク
では、もし職場にルールが無かったらどのようなことが起きるのでしょうか。そのリスクを詳しく見ていきましょう。
1.ストレスや混乱を生む
職場にルールがなかった場合の一番のリスクとして挙げられるのは、ストレスと混乱に満ちた環境になることです。各自でマイルールを作っていくことになり、決断のストレスや責任の所在の不透明さから、従業員のモチベーションや生産性を大きく低下させます。
2.人間関係の悪化
組織の方向性が不明確になると、各自が自分の解釈に基づいて行動することになり、その結果、チーム内で摩擦が生じる可能性が高まります。意見の食い違いや行動の不一致は、人間関係のトラブルを引き起こし、職場環境を悪化させる要因となります。
3.業務効率の低下
判断のたびに脳にかかる負荷は、業務の効率を著しく低下させます。明確なルールが無ければ、何が正しいのかを判断するために余計な時間やエネルギーを費やすことになり、結果的に生産性を損なうことになるでしょう。
4.不満の蓄積
ルールがないことはチーム内での不満を生む原因にもなります。たとえば、あるメンバーが自分の価値観に基づいて行動する一方で、他のメンバーは別の基準で行動する場合、折り合いがつかずにチーム内に不満が蓄積される可能性があります。
このように、ルールが無い場合、組織全体の健全な運営が難しくなり、最終的には企業の成長にも影響を及ぼすことになるのです。
職場におけるルール作成のポイントとプロセス
次に、職場においてルールを作成する際のポイントを見ていきましょう。まず、ルールは「縛る」ものではなく、全員が守るべき共通の指針であるという意識改革が必要です。この意識を持つことでメンバーはルールを受け入れやすくなり、チームの結束力が高まります。
また、「何のためのルールか」を従業員へ説明することも重要です。目的や意義を理解することで、メンバーは納得感を持ち、ルールを守る意欲が湧きます。
具体的なルール作りのプロセスは、以下の通りです。
(1) 職場の目的やミッションを深掘りすることから始めます。会社における部署の立ち位置や存在意義、どのような役割を担っている組織なのかが明確になると、それが個々人の行動の源泉となります。このことは、リーダーシップの専門家であるサイモン・シネック氏の「WHYから始めよ」というプレゼンテーションの中でも提唱されています。このプロセスでは、チームの目指す方向性を共有し、全員が同じ理解を持つことが重要です。
(2) チームでルールの必要性や具体例を話し合い、意見を出し合います。メンバーの意見を尊重し、ルールに対する参画意識を高めることで、共通の理解を形成します。
(3) 他部署にもシェアをして、組織全体での共通認識を形成します。共通認識や共通言語を持つことで、円滑なコミュニケーションを促進します。
さまざまな立場や部署との情報交換を通じて、他のチームがどのようなルールを持っているかを認識し、自分たちのルール作りに生かすのも有効です。全員の意見に耳を貸し、納得できるルールを作成・実行することで、職場の秩序と円滑な運営が実現します。
職場のルールがもたらす効果
ルールが職場にもたらす効果を3つご紹介します。
1.行動の自由度と効率が両立する
明確なルールがあることで、メンバーは自分の行動に自信を持ち、ルールの範囲内で工夫して自由に業務を進めることができます。これにより、効率的な業務運営が実現します。
2.トラブル時に迅速な解決ができる
判断基準があれば、トラブル発生時に迅速な対応が可能です。問題解決がスムーズになり、業務の停滞を防ぐことができます。
3.個人の負荷が減り、パフォーマンスが向上する
ルールがあることで、メンバーは自分の役割に専念でき、余計なストレスが軽減します。業務に集中できる環境が整い、チーム全体のパフォーマンスも向上します。
このように、ルールを定めることは、職場全体の雰囲気や生産性に良い影響を与え、健全な組織文化を育むことに繋がります。
「共通の指針」が健全な職場文化を育む
今回は、職場のルールと心理的安全性の関係と、ルールが職場にもたらす効果、ルールの作り方などを詳しく紹介しました。
職場のルールは、従業員が安心して働くための重要な土台です。明確なルールがあることで、行動の予測ができ、安心かつ集中して仕事に臨めるため、組織のパフォーマンスが飛躍的に向上します。
ルールは従業員を「縛る」ものではありません。むしろ、共通の指針として機能することで、職場の雰囲気や生産性に良い影響を与え、健全な職場文化を育むことが可能です。
ぜひこの機会に、職場のルールの在り方や捉え方を見直してみてはいかがでしょうか?
~あわせて読みたい記事~ |