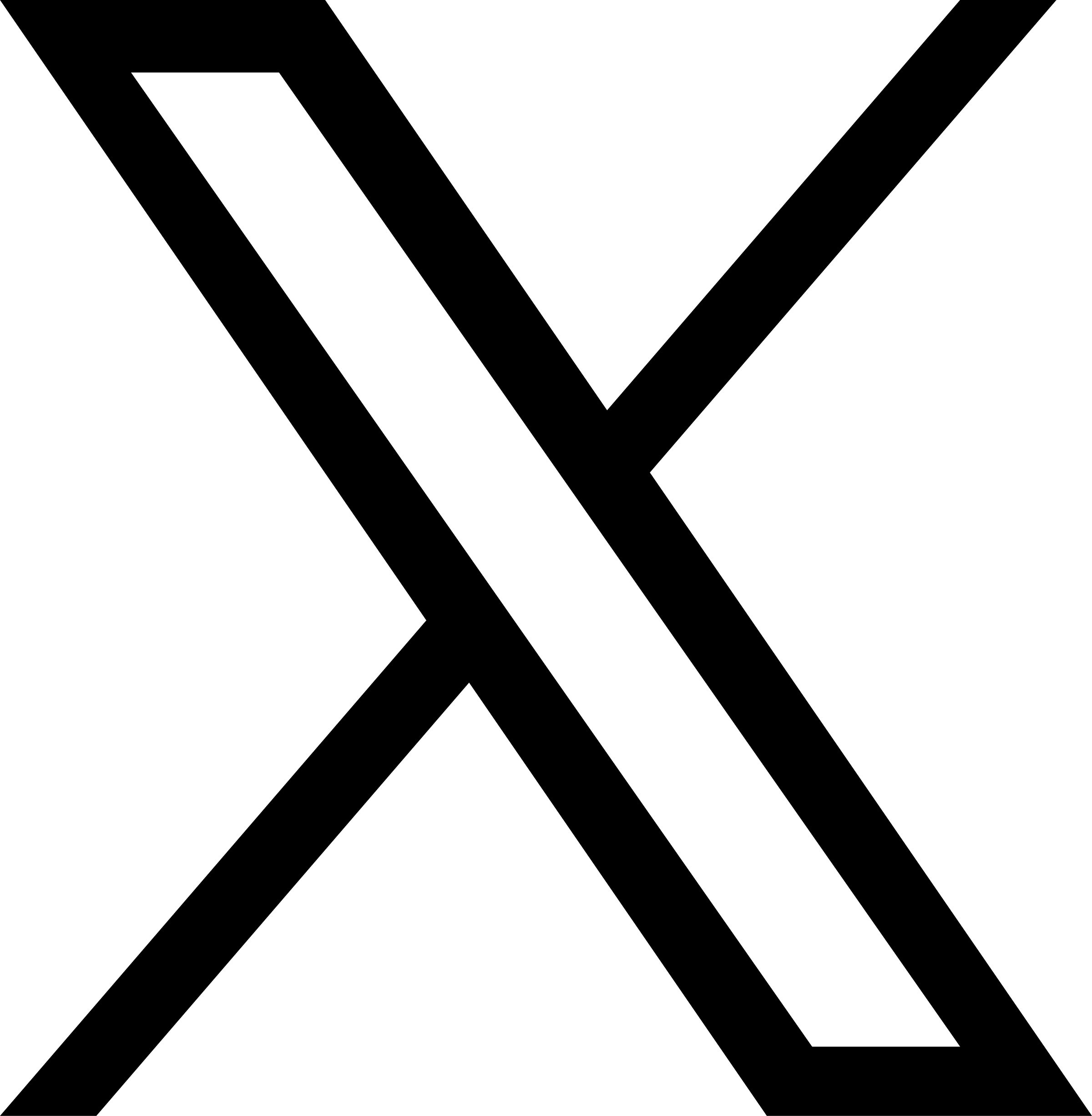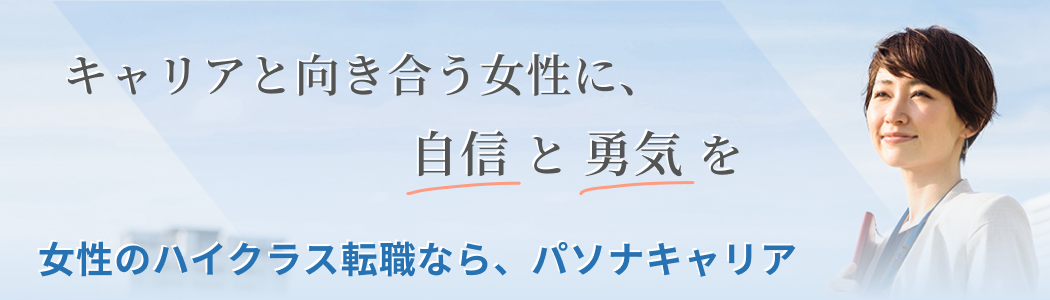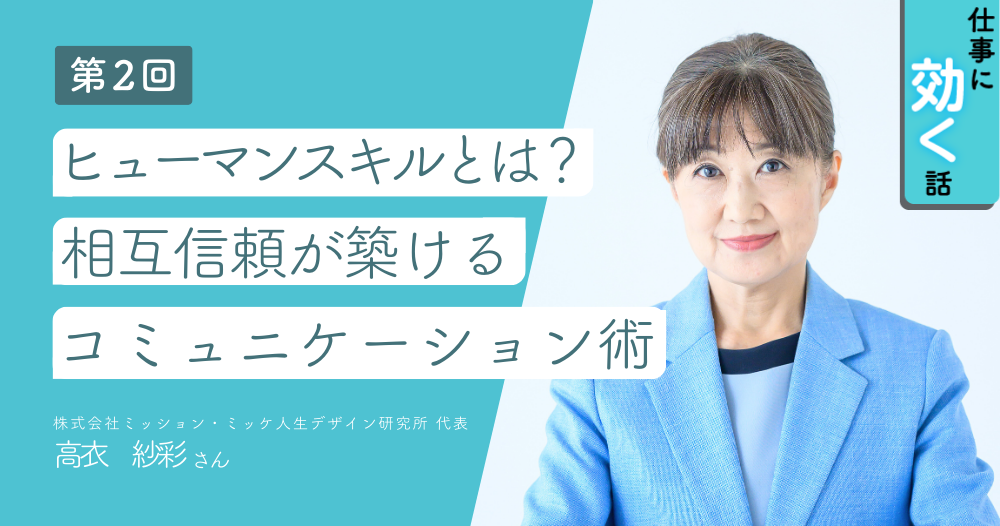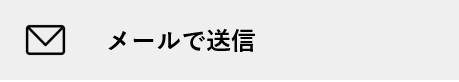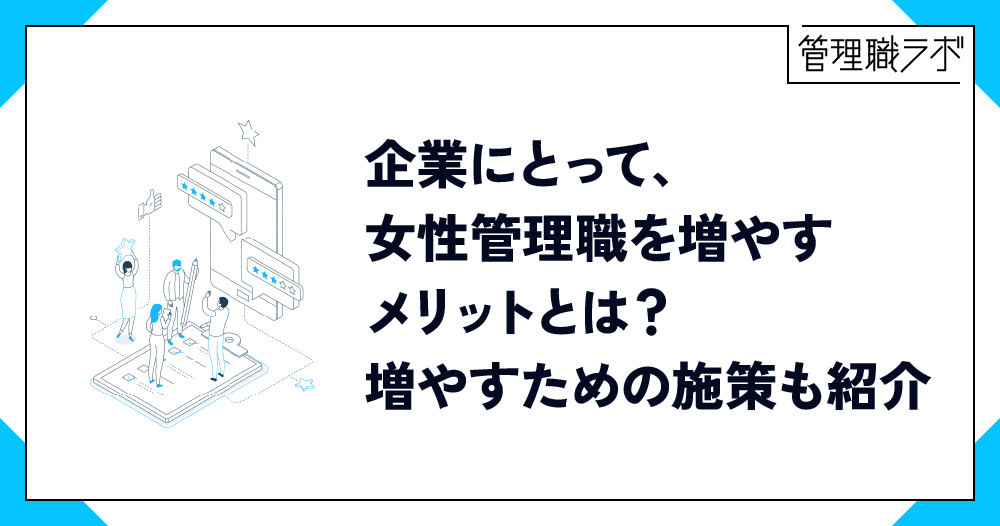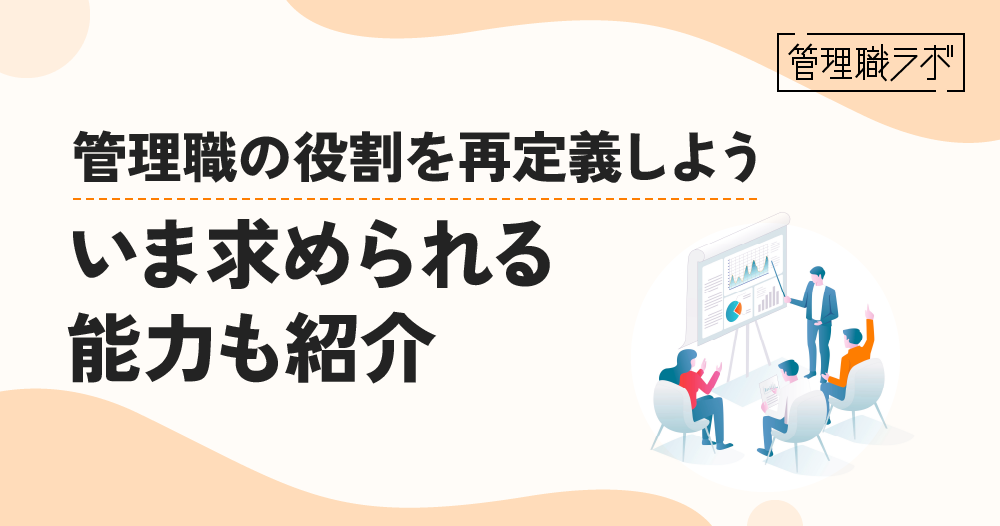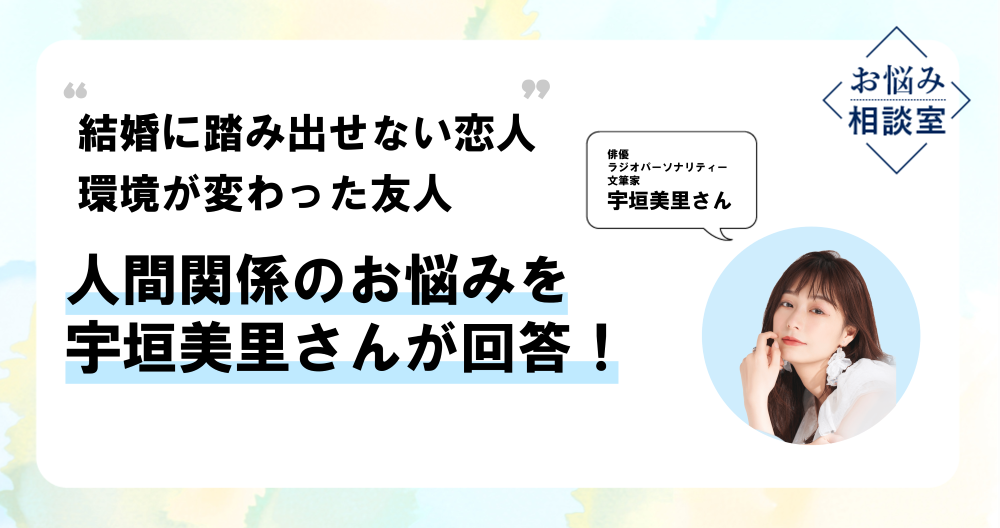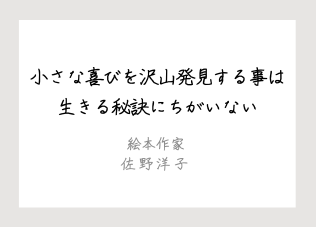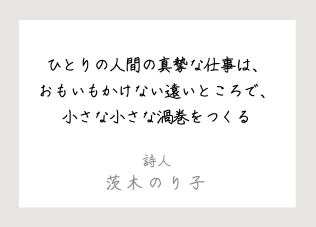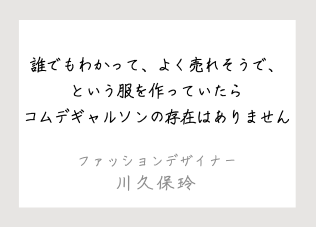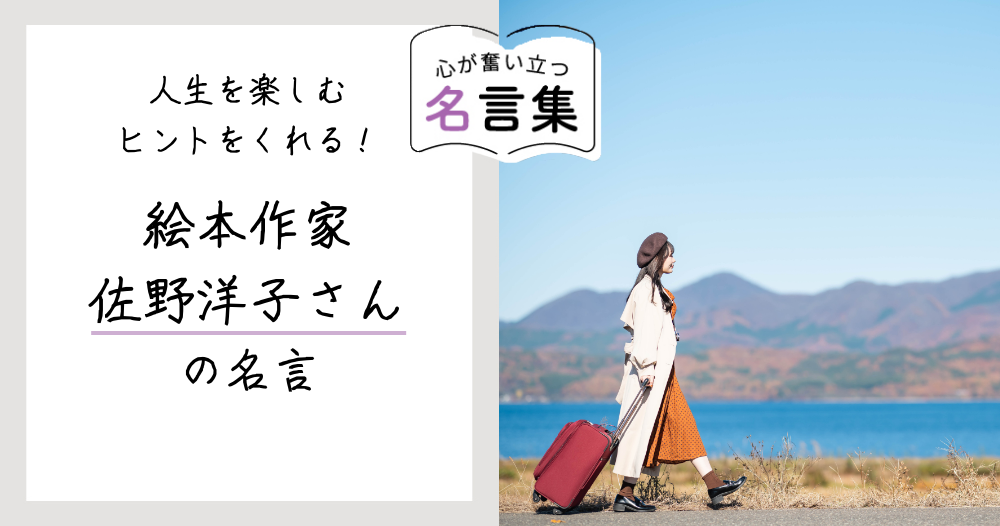「ヒューマンスキル」の本質とは?相互信頼が築けるコミュニケーションの技術
前回の記事では、カッツモデルが示す3つのスキルセットー「テクニカルスキル」「ヒューマンスキル」「コンセプチュアルスキル」ーをご紹介し、この3つを自分のキャリアや職位に応じて磨いていくことで、リーダーシップの質を高めていけることをお伝えしました。
その中でも特に重要なスキルがヒューマンスキルです。今回はその核となる「コミュニケーション」と「信頼構築」に焦点を当てて、実践的なアプローチを紹介します。
目次
- ヒューマンスキルの本質:共感と信頼の重要性
- 1. 傾聴し共感する力を磨く
- 2. 質問の質を高める
- 3. 非言語コミュニケーションを意識する
- 4. 感情的知性(EQ)を活用する
- 効果的なフィードバックでチームを成長させる
- 1. SBIモデルを活用する
- 2. 「サンドイッチ法」を超える
- 3. 上から目線のアドバイスにならないように「私メッセージ」 を使う
- 4. 即時性と継続性のバランスを意識する
- 5. フィードバックではなく、フィードフォワードを送る
- 多様性を活かすリーダーのマインドセット
- 1.「無意識の偏見」に気づく
- 2.「心理的安全性」を創出する
- 3. 全員の特徴を否定せずに活かすリーダーシップを実践する
- まとめ

高衣紗彩(たかごろもさあや)さん
株式会社ミッション・ミッケ人生デザイン研究所 代表
千葉県出身。英国University of Hullでファイナンス&インベストメント専攻のMBAを取得後、香港で銀行の産業調査部に7年間所属。その後、外資系投資銀行や資産運用会社で証券アナリストやポートフォリオ運用を担当。ステージIVの癌から回復した経験を機に独立し、2013年に「ミッション・ミッケ 」を設立。2015年には独自のメソッドをもとに『人生デザイン構築学校®』を創設し、600名以上の卒業生を輩出。2024年、初の著書『プロのポートフォリオ・マネジメントで一生お金に困らない人になる!』(すばる舎) を出版し、全国のビジネス書ランキングで1位を獲得するなど注目を集める。現在も「才能を輝かせる人生デザイン」の普及に尽力している。
・YouTube
・Apple Podcast
・コーチングメールのご登録
ヒューマンスキルの本質:共感と信頼の重要性
ビジネスの世界では「ハードスキル」が注目されがちですが、人と人との関係性を構築し、組織を動かす上で最も重要なのは「ヒューマンスキル」です。ヒューマンスキルの本質は「共感」と「信頼」にあります。まずは、人を動かすためのコミュニケーションの基本原則をご紹介します。
1. 傾聴し共感する力を磨く
真のコミュニケーションは「話す」ことではなく「聴く」ことから始まります。ここで活用できるのが、アクティブリスニングです。アクティブリスニングとは、単に受け取った言葉を耳で聞くだけでなく、相手の『感情』や『意図』をアクティブに理解しようとする姿勢のことを指します。
マネージャーやリーダーの皆さんからよくいただく相談が、「部下の言動の理解に苦しむ」というものです。行動自体、言葉自体が皆さんの常識の範疇を超えていても、その背景や状況を理解しようとし、聞き出すと、案外「それならその言動になるのも理解できる」となるケースも少なくありません。目に見える言動だけではなく、その背後にあるものを理解しようとしてみるだけで、共感力は高まります。
すると、会話中に「なるほど、そういうことだったのですね」など、相手の言葉を受け止める言葉が自然に出てきます。実際に思っていないのに、共感を示す相槌だけを打っても、本当はそう思っていないことが相手には手に取るようにわかってしまいます。そこは、部下であっても侮らない方が賢明です。
心の底から出た理解の言葉を素直に返すことで、相手は「自分のことを理解してくれている。」少なくとも「理解しようとしてくれている」と感じ、心を開いてくれます。あなたが伝えたいことを伝えるのは、そのあとです。この順番を間違えないようにすることは、とても重要です。
2. 質問の質を高める
「はい/いいえ」で答えられる閉じた質問ではなく、「どのように」「なぜ」「何が」で始まる開かれた質問を心がけます。例えば「このプロジェクトで困難はあるか?」の代わりに、「このプロジェクトで最も困難だと感じている点は何か?」という質問をします。こうすることで、相手は自分の心の中を探るので、本音を引き出しやすく、問題の核心に迫る機会を生み出しやすくなります。
3. 非言語コミュニケーションを意識する
研究によれば、コミュニケーションの55%は表情やジェスチャーなどの非言語要素、38%は声のトーンで伝わると言われています。オンラインミーティングであっても、カメラをオンにし、相手に向かって正面に顔を向け、ジェスチャーなどを交えて、相手への興味をしっかりと示しながら話すことを心がけましょう。「あなたは重要な人だ」というメッセージが非言語で伝わります。
4. 感情的知性(EQ)を活用する
上司として是非身につけたい能力の一つに、「自分の感情をまずは脇に置き、相手の感情を受け止める能力」があります。これは、特に強い信頼関係の構築に不可欠です。例えば、チームメンバーが落ち込んでいるとき、「今落ち込んでいる場合か、全く弱いやつだ。」と思うかもしれません。ですが、それこそが、あなたの感情です。あなたの感情は一旦脇に置いて、まずは、相手の感情を受け止めようとします。理解できなくても構いません。「落ち込んでいることを受け入れる」だけでOKです。
「受け入れる」がどのようなことかわからない場合は、「落ち込んでいる時間を批判せずに許可する」と考えてみてください。同意する必要もありません。落ち込んでいる部下は立ち直らせなければ、という意識を捨て、すぐに解決策を提示しようとせずに、まずは相手の感情を認めます。それから「それは大変な状況だ。どうすれば支援できるか一緒に考えよう。」といった言葉をかけ、「自分はあなたの味方である」ことを伝えます。これが相手に安心感を与え、自然に立ち直るきっかけを与えます。
落ち込みから救い出そうとするあなたの気持ちを手放す。これが、結果として、部下を落ち込みから救い出すことに繋がります。
効果的なフィードバックでチームを成長させる
フィードバックは相手の成長を促す最も強力なツールですが、伝え方によっては、相手を萎縮させ、パフォーマンスを悪化させることにも繋がってしまいます。そこで、効果的なフィードバックの伝え方をお伝えします。
1. SBIモデルを活用する
効果的なフィードバックを提供する方法の一つに、「状況(Situation)」「行動(Behavior)」「影響(Impact)」の順に伝えるという方法があります。この方法は、ネガティブなフィードバックを行う際にも、非常に有効です。むしろ、批判的なフィードバックを伝える際こそ、このような構造化されたアプローチが重要になります。
SBIモデルをネガティブなフィードバックに適用する利点:
1. 具体性と客観性を保てる
「あなたは遅刻癖がある」ではなく「先週の火曜日のチームミーティング(状況)で、20分遅れて参加された(行動)ため、議題を再度説明し直す必要があり、ミーティングが予定より延長しました(影響)」と伝えることで、具体的で反論の余地が少ない形で伝えられます。
2. 個人攻撃ではなく行動に焦点を当てられる
SBIは人格批判ではなく、特定の行動とその影響に焦点を当てるため、相手が防衛的になりにくくなります。
3. 改善への道筋が見えやすい
行動とその影響を明確にすることで、「では次回はどうすればよいか」という建設的な議論につながりやすくなります。
ネガティブなフィードバックでSBIを使用する際のポイント:
1. 「影響」部分を丁寧に伝える
特にチームやプロジェクトへの具体的な影響を説明することで、改善の必要性が理解されやすくなります。
2. 解決策や期待を追加する
従来のSBIに「E(Expectation:期待)」を加えて、「SBIEモデル」として使うこともできます。例えば「今後はミーティング開始10分前には参加できるようにしていただけると助かります」という形です。
3. タイミングと場所を選ぶ
特に改善が必要なフィードバックは、1対1の場で、相手が受け入れやすい状況で行うことが重要です。
最後に、ネガティブなフィードバックであっても、相手の成長を願う前向きな意図を持って伝えることが最も重要です。SBIモデルはその意図を適切に伝えるための効果的なツールとなります。
2. 「サンドイッチ法」を超える
良い点→改善点→良い点の順で伝えるという古典的な「サンドイッチ法」は時に効果的ですが、使い古されていて形式的に感じられることもあります。形式より、むしろ自分が相手の成長を真剣に願っている状態になっているかを確認することが大切です。あなたの気持ちがそうであれば、それは自然に相手が素直に受け取れるフィードバックになっているはずです。最後に、具体的で実行可能な提案をすることも忘れないようにしましょう。
例:「プレゼンの内容は素晴らしかったです。次回は、もう少しゆっくりと話すことで、聴衆の理解がさらに深まると思います。具体的には、各スライドの主要ポイントを3つに絞ると良いでしょう。」
3. 上から目線のアドバイスにならないように「私メッセージ」 を使う
「あなたのプレゼンはここがこうなってしまっている」という、相手を主語にした「あなたメッセージ」は、たとえ的確なアドバイスであっても、相手にとっては「批判された」「否定された」と捉えられる可能性があります。すると、防衛反応が出て素直に聞いてくれないどころか、心を閉ざされてしまうことにもなりかねません。「あなたは」ここをこうした方がいい、というアドバイスを、「私は」こう感じました、という「私メッセージ」で伝えることで、防衛反応を最小限に抑えることができます。
例:「この部分は、結論に飛躍し過ぎで突然感がある。」
⇒「私は、この部分についてもう少し詳しく説明があると理解しやすいと感じたけど、どうかな。」
4. 即時性と継続性のバランスを意識する
重要なフィードバックは、出来事からあまり時間を置かずに伝えることが重要です。間髪を入れずに上記のフィードバックを伝えることで、すぐに吸収される可能性が高まります。一方で、定期的な1on1ミーティングなどを設け、継続的なフィードバックの機会を作ることも、同じくらい重要です。その時、前回からの成長について触れることは、特に重要です。
5. フィードバックではなく、フィードフォワードを送る
相手に改善点を伝えることをフィードバックと呼びますが、日本ではフィードバックの場を「批判をしていい場所」と捉えられている節があります。そして、ここぞとばかりに日頃思っているけど口にできない批判を言ってしまい、関係が悪化することも良く起こっているようです。
その危険性がない方法として、フィードフォワードがあります。フィードバックとフィードフォワードの主な違いは、以下のとおりです。焦点を当てる時間軸と目的に違いがあります。
フィードバックは、主に過去の行動の評価に焦点を当てる過去志向のアプローチです。過去の出来事や行動に基づき、「何が起きたか」「何が良かったか/改善すべきか」を振り返ります。
例:「さっきのプレゼン、声が小さく、後ろの人には聞こえにくかったようだ。」
これは、ともすると、悪いところ探しに受け取られる可能性があります。
フィードフォワードは、未来の可能性や機会に焦点を当てる未来志向のアプローチです。「これからもっとうまくやるにはどうすれば良いか」を中心に考え伝えるので、具体的な提案や行動計画の提示が含まれるのが特徴です。
例:「次回は、マイクの音量をもう少し上げてみたら、後ろの人にも聞きやすいと思うよ。」
これは、より良いものに改善していくイメージになるので、素直に受け止めやすくなります。
このように、フィードフォワードは、過去の問題点を指摘するというより将来の成功に向けた建設的な提案を行うため、受け手も防衛的になりにくく、前向きに受け止めやすいという利点があります。また、無駄に落ち込むことをなくすことにも繋がります。使ったことがない方は、ぜひ使ってみることをお勧めします。
多様性を活かすリーダーのマインドセット
グローバル化とデジタル化が進む現代のビジネス環境では、多様なバックグラウンドや価値観を持つメンバーと協働する機会が増えています。リーダーは、この多様性を理解し活かすことで、組織の創造性や競争力を高めることができます。異なる価値観や背景を持つ人々と協働するための具体的なアプローチをご紹介します。
1.「無意識の偏見」に気づく
私たちは誰もが「無意識の偏見(アンコンシャス・バイアス)」を持っています。例えば「若い人はデジタルに強い」「女性は細かい作業が得意」といった思い込みです。厄介なことに、私たちは「自分は偏見なんて持っていない」と「思い込んで」います。偏見を持っているかもしれないと謙虚になり、それに気づき、意識的に修正していこうとする姿勢が大切です。
2.「心理的安全性」を創出する
Googleの研究によれば、高パフォーマンスチームの最大の特徴は「心理的安全性」−失敗を恐れずに意見を言える環境−だと言われています。リーダーが自らの失敗や不確かさを率直に認めることで、チームメンバーも安心して発言できるようになります。
例:「私もこの分野は専門外で、皆さんと一緒に学んでいきたいと思います。どんな質問や意見も歓迎します。」
3. 全員の特徴を否定せずに活かすリーダーシップを実践する
「会議では発言すべき」「発言しないのは貢献していないことと同じ」という考えも一種の無意識の偏見です。一つの価値観が良しとする方向に全員を持っていこうとすると、そのつもりはないのに高圧的になったり押し付けがましくなったりし、安心安全な場ではなくなってしまいます。
会議では「静かなメンバー」も、一日中パソコンに向かってデータを分析することにかけては右に出る者がいない、という特性を持っているかもしれません。一つの価値観でメンバーの貢献度を測ることを止め、全員のあり方を尊重することができると、全員が自然に個性と強みを発揮するチームになっていきます。
まとめ
こうして見ると、チームの問題の多くは、リーダーとしてのあなたのヒューマンスキルを高めることによって解決できることがお分かりいただけると思います。
幸いなことに、ヒューマンスキルは、「生まれつきの才能」ではなく、意識的な練習と振り返りによって磨くことが可能です。日々のコミュニケーションの中で今回紹介した技術を意識的に取り入れ、トライ&エラーを繰り返しながら、自分なりのスタイルを確立していくことで、あなた自身のリーダーシップ性を高め続けることが大切です。
次回の最終回では、コンセプチュアルスキルに焦点をあて、AIと共創する時代における人間ならではの「創造性とイノベーション」に繋がる創造的思考法について探ります。
~あわせて読みたい記事~ |