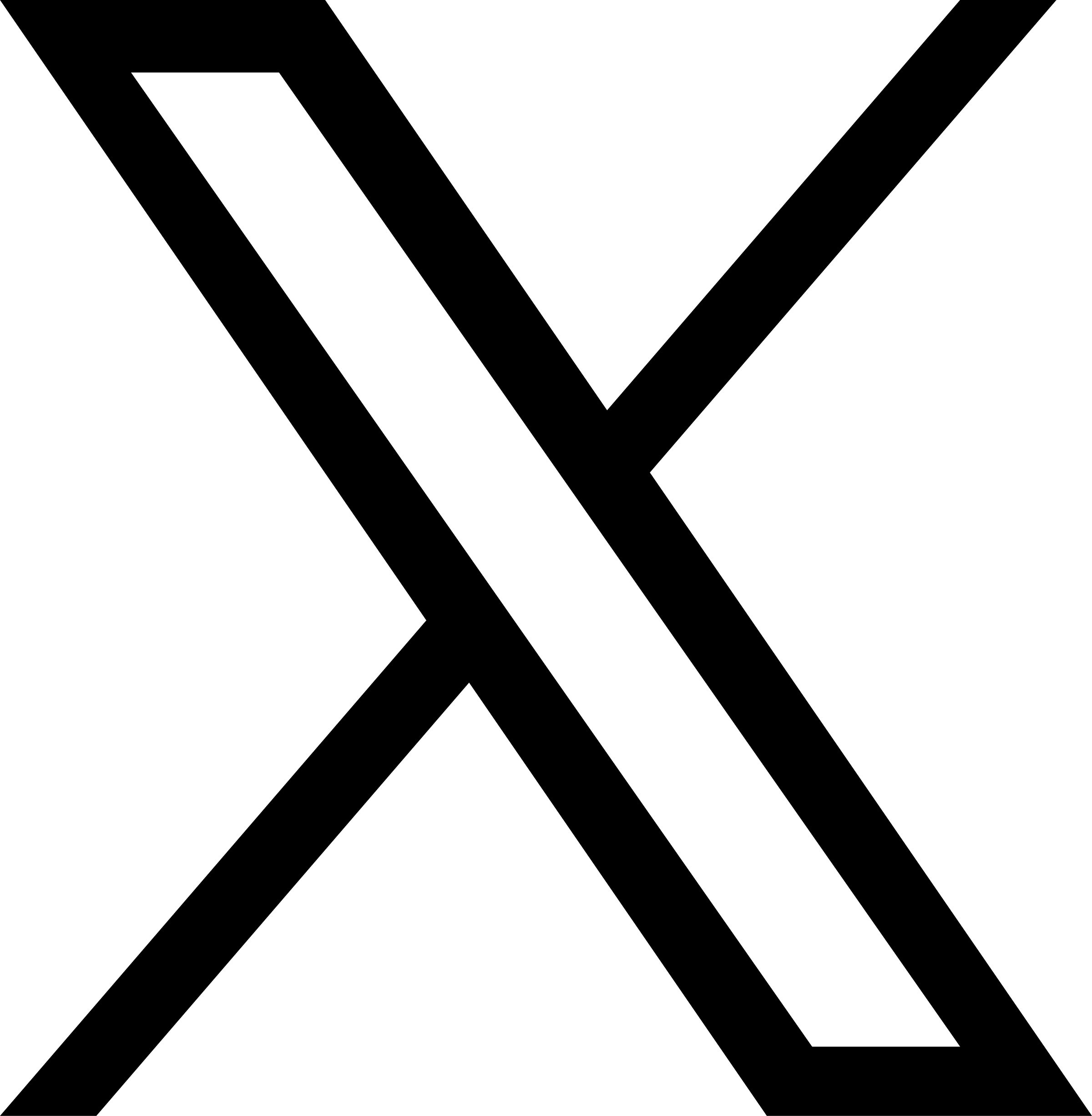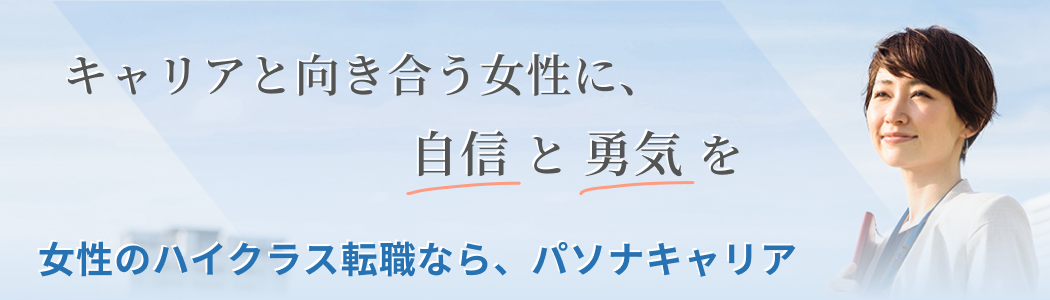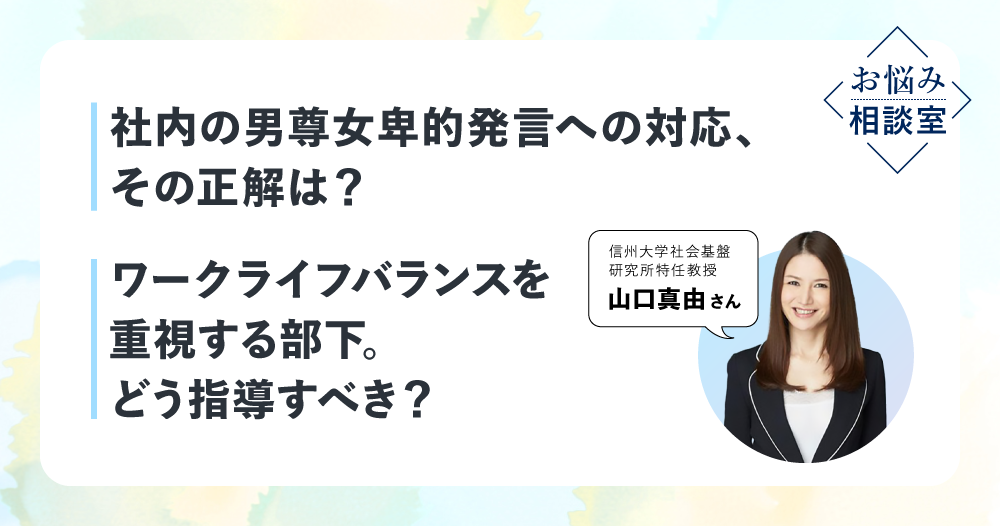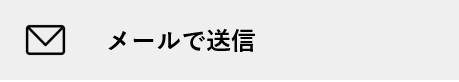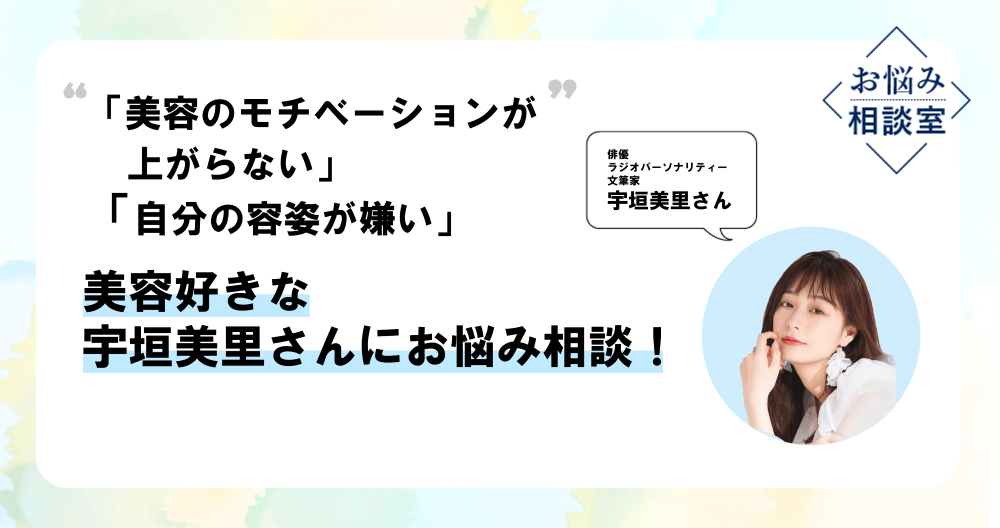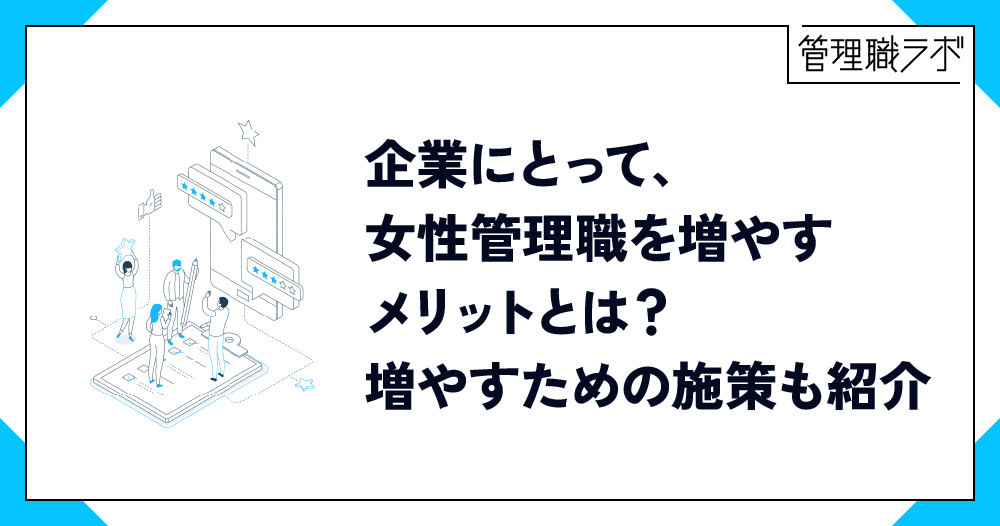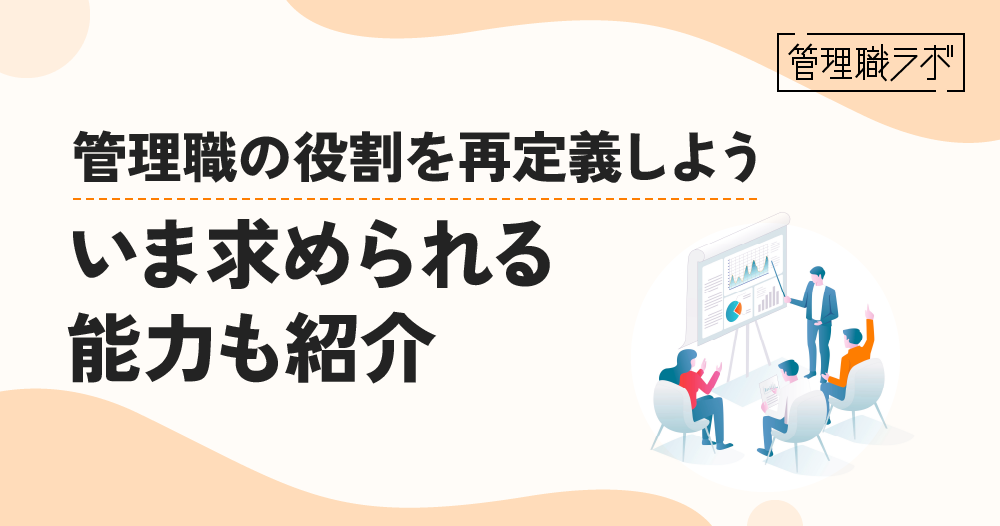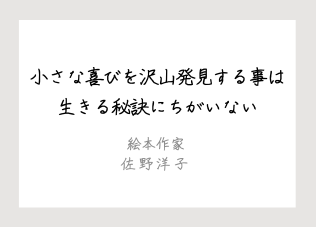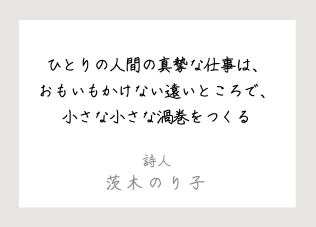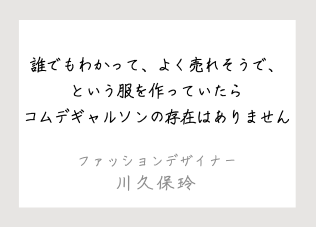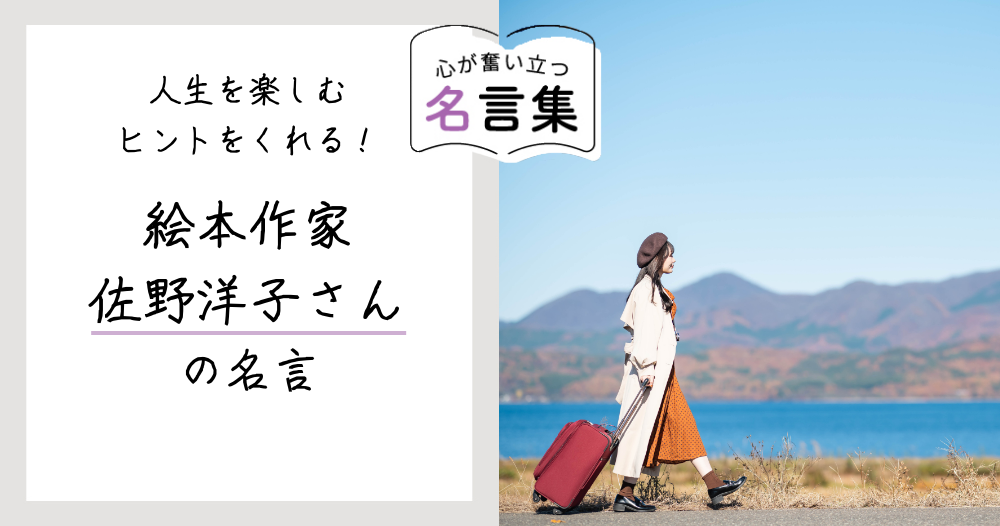山口真由さん「これからは管理職としての“品格”を身に付けよう」
キャリア、仕事、人間関係、健康、家族、恋愛…。悩み多き、現代女性たちに、信州大学社会基盤研究所特任教授で法学者の山口真由さんが寄り添います! 今回は「社内の人間関係」に関するお悩み2つに回答してもらいました。
目次

山口真由さん
1983年生まれ。信州大学社会基盤研究所特任教授・法学博士。
東京大学を総長賞を受け卒業。卒業後は財務省に入省。退官後、弁護士として主に企業法務を担当。その後、ハーバード・ロー・スクール(LL.M.)卒業。ニューヨーク州弁護士登録。
東京大学大学院法学政治研究科博士課程修了。
現在「羽鳥慎一モーニングショー」(テレビ朝日)「ゴゴスマ」(CBCテレビ)などに出演中。
社内の男尊女卑的発言への対応、その正解は?
≪相談者≫
Aさん(43歳):金属メーカー勤務。部下5人を抱える管理職3年目。小学生の子育て中。
|
山口さんの回答「自分の心地良い範囲を超えたら、潔く身を引く」
私もAさんと似たところがあり、嫌なことを言われても、波風を立てたくないから曖昧にやり過ごすタイプです。テレビ番組のコメンテーターをしているので、なるべく視聴者に嫌われないようにと、周囲に迎合する癖がついてしまっている自覚があります。そうすると、少しずつ自分がすり減っていくんですよね。
例えば日常生活の中でも、タクシーの運転手さんが男性には敬語なのに、私にはタメ口で話しかけてくるシーンなど、とても嫌だと感じます。でも受け流してしまうのは、多分、他人に好かれたいという気持ちが強いのかなと自己分析していて。
リーダーシップの取り方として、Aさんや私のように誰に対しても親切で、話しやすい雰囲気をつくることは大切です。ただ、Aさんも私も、「周りからどう思われるか」を気にするあまり、自分が心地良いと感じる範疇を超えて他人に迎合し続けてしまっているのです。
そうすると、いつまでも搾取され続ける側にいることになります。誰に対しても良く見られようとすると断りたい仕事も断れなくなって、「この人はこういう使い方をして良いんだ」と思われ、いつまでも不本意な仕事が振られ続けることになります。
だからこそ、管理職としてさらに上に行くためには、みんなにとって良い人であるだけではなく、自分の一定の基準を持ち、その範囲を超えるものについては関わらない「品格」が必要なのかなと思います。
その品格を身に付けるためには、「人からどう思われるか」という基準よりも「自分がどう思うか」という基準を大切にしなければなりません。
そして心地良い範疇を超えるような人とは無理に関係を作らない。具体的には、同じ空間にいたらその場から立ち去る、そういった人がいる飲み会などには参加せずに接触機会を減らすということです。もしそれで仕事が回ってこなくなっても、自分に与えられた仕事でパフォーマンスをきちんと出していればそれで良いんですよ。
嫌なことを言われた時、必要以上に闘って摩擦を生むのではなく、その場から身を引く。そういう人付き合いを、私も目指している最中なので、一緒にがんばりましょう!
ワークライフバランスを重視する部下。どう指導すべき?
≪相談者≫
Eさん(46歳):IT企業に務める。管理職歴は10年とベテラン。社内でも勤続年数は長い方。
|
山口さんの回答「部下とは、近すぎず遠すぎない距離感を」
自分が受けてきた指導をそのまま部下にすると、パワハラだと言われる…。この気持ち、わかります! もちろんパワハラ的要素は取り除きたいけど、仕事から学び、成長をしてきた自負があるからこそ、部下たちがその経験をしなくて良いのかという心配がありますよね。
先日、経済評論家の加谷珪一さんと話していた時に、「全ての人に対して同じ距離感を保つべき。人間を人間として尊重することがこれからの価値観だ」とおっしゃっていました。つまり、仕事の場面に当てはめると、たとえ上司や部下であっても迎合すべきではないし、踏み込み過ぎるべきではないという考えなんですね。
「自分の成功体験を同じように辿ってほしい」という親心は、部下に対して少し踏み込み過ぎているのだと、私自身も気付かされましたね。
これからはもっとユニバーサルに人を育てていかなければいけないと思います。この企業だから・この人だからと接し方を変えるのではなく、誰に対しても一貫した基準で適切に指導し、評価を下す。
そして、その人にとってどこまでが踏み込み過ぎになるのかは、話し合って合意をとっていくべき。
例えば、ハラスメントと指摘されるのが怖いから、極端に部下と距離を取ることも正しいとは言えないんですよ。実際、法的観点からいうと、一発アウトのセクハラ・パワハラは滅多に起こらないものです。いわゆるパワハラ防止法も「ここまでするとハラスメントなので“気を付けよう”」という境界線を示したものなので。万が一間違えてその境界線を越えてしまったら戻れば良いわけです。
自分の感覚で距離を取ったり詰めたりするのではなく、「こういう風に言われるのってどう?」「こういう指導はどう?」と、部下と話し合って適切な距離感を決めていくことが大事だと思います。
プライベートと仕事のバランスも「こういう働き方を今後していくと、こういった壁があると思うけど、その壁を乗り越えてでも働き続けたい?」とか。そこでプライベートを優先させたいか、困難があっても仕事を優先させたいのかを聞いて、その人にあったプランを提案してあげると良いと思いますよ。
回答まとめ
・周りに迎合するのではなく「自分が心地良いと感じる範囲」を大切にする品格を持とう
・全ての人に対して同じ距離感を保つよう心がけよう
・部下との適切な距離感は、話し合うことで見えてくる
|