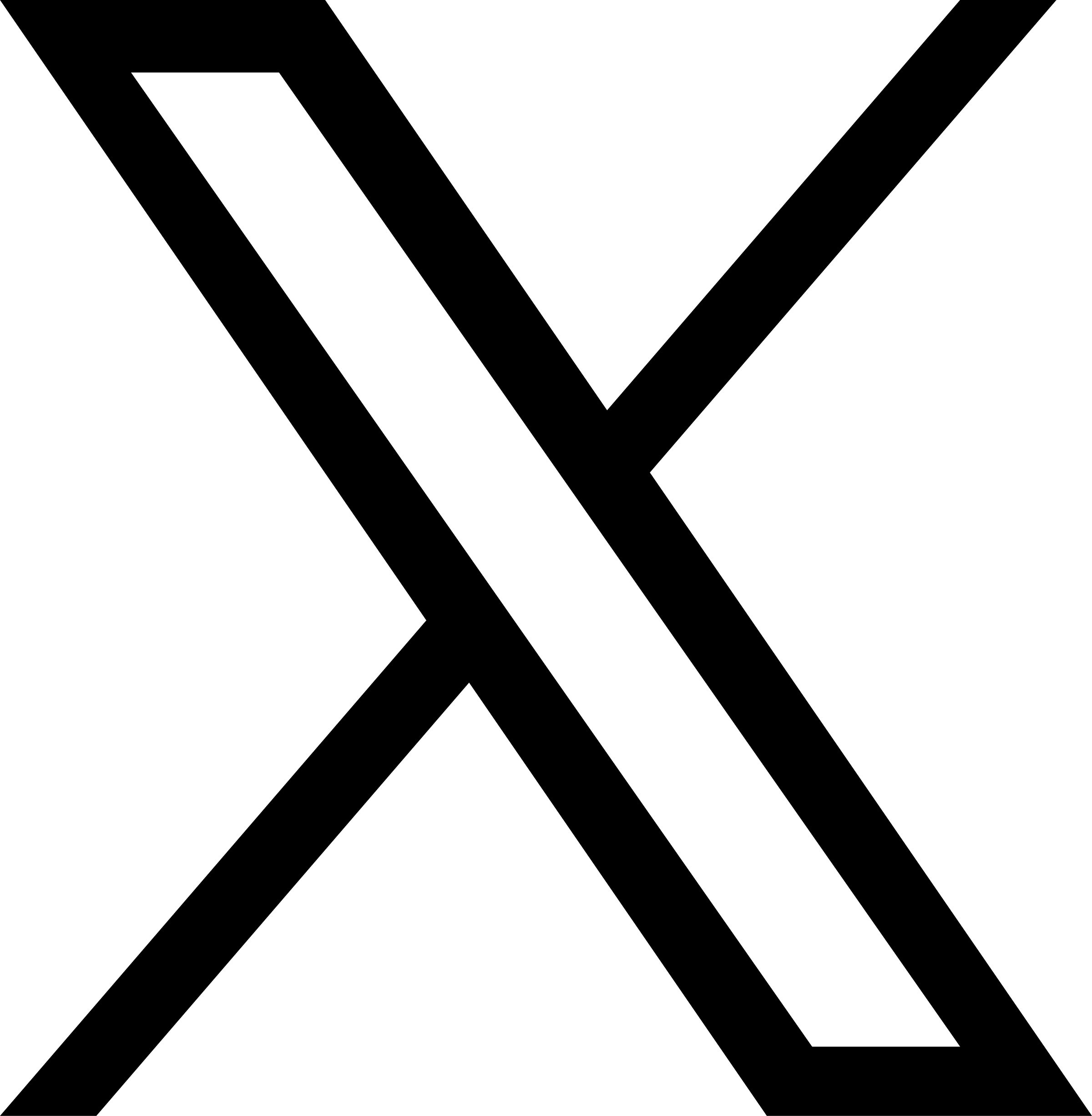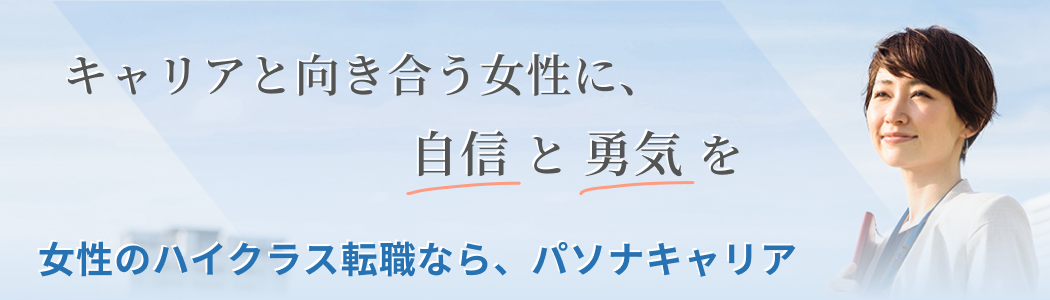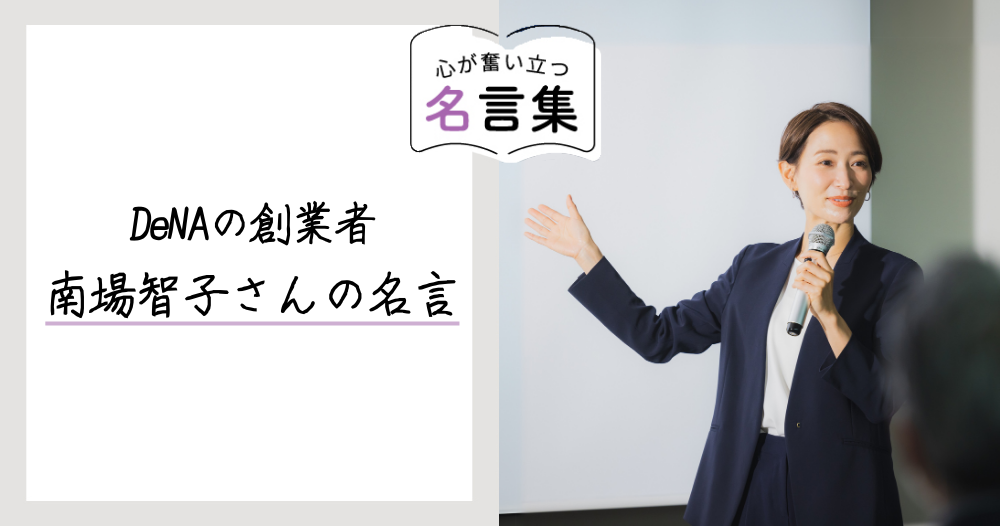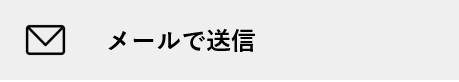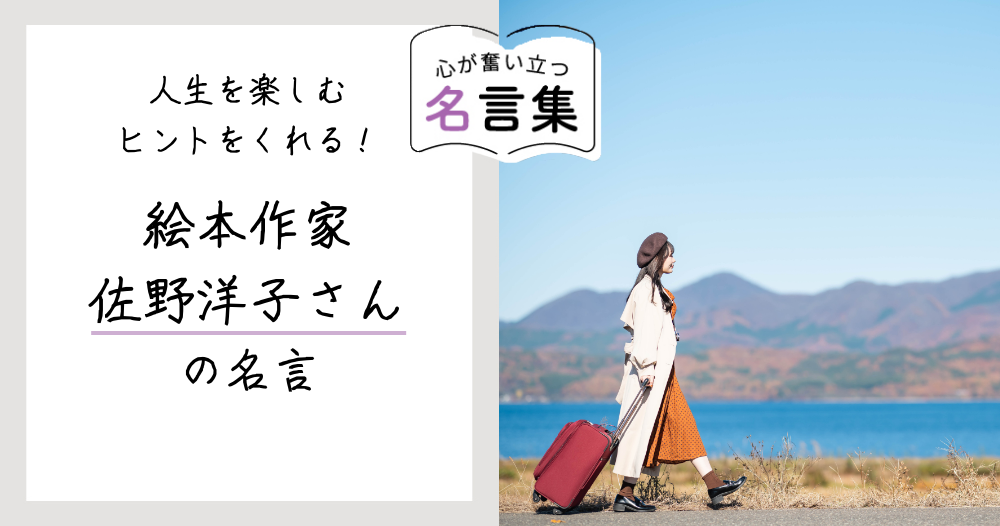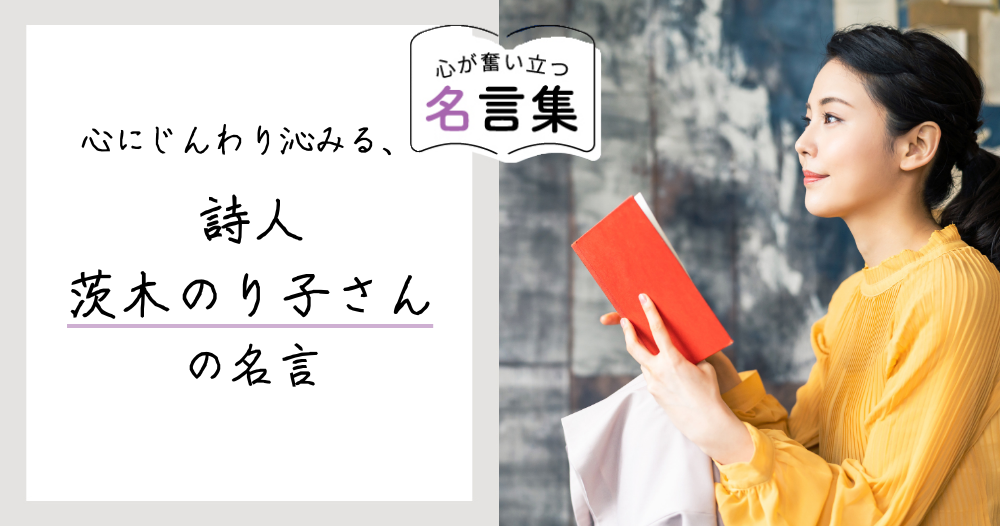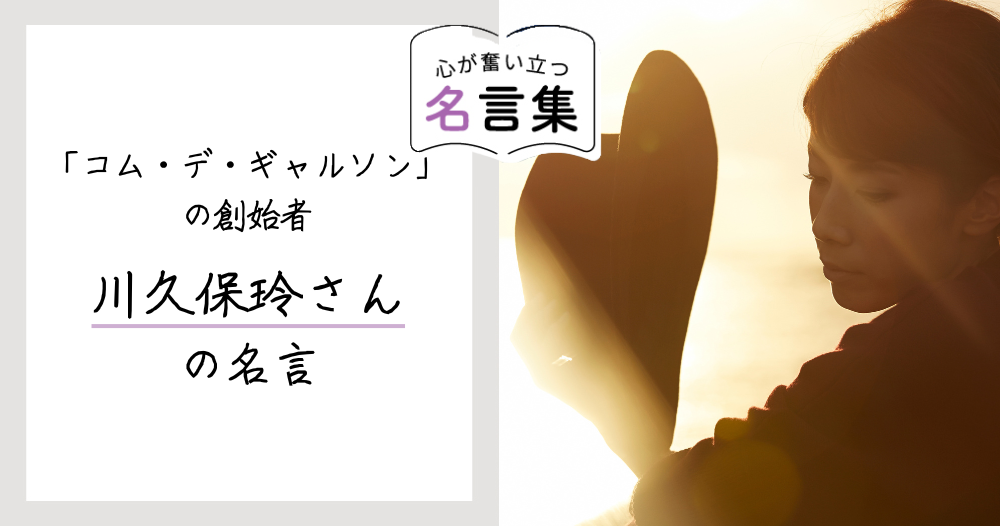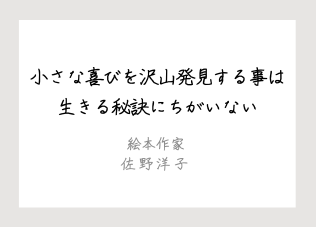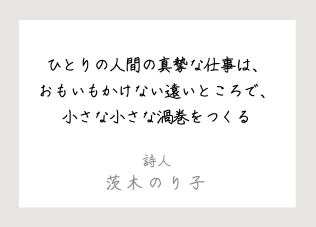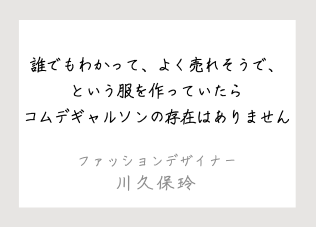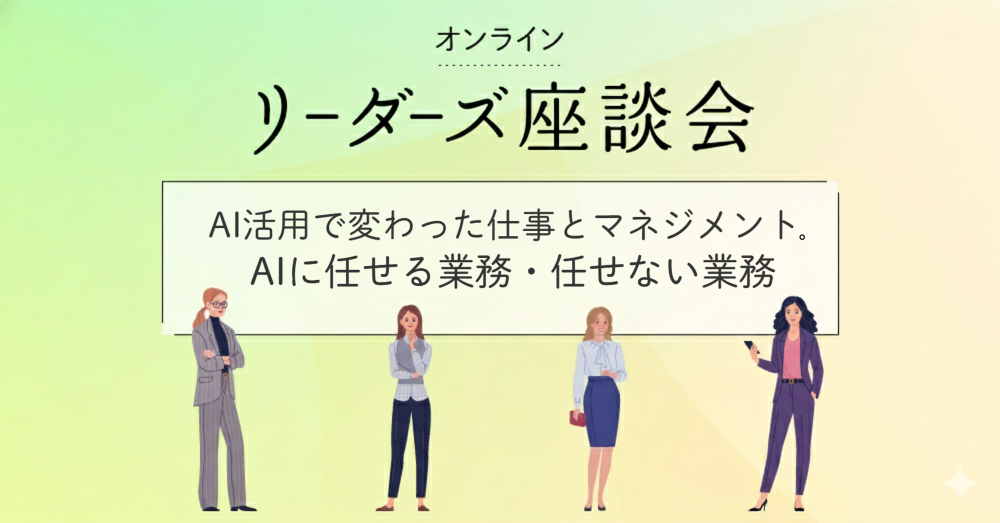DeNAの創業者、南場智子さんの名言
株式会社ディー・エヌ・エー(DeNA)を創業し、確かな経営手腕をもって成功へと導いてきた南場智子さん。
現在は、代表取締役会長としての職責を果たしながら、女性初の日本経済団体連合会副会長を務め、横浜DeNAベイスターズのオーナーとして昨年は日本一を経験するなど、その活躍は多岐に渡ります。
そんな南場さんは、仕事への向き合い方についての名言を数多く残しており、成功者になるためのビジネスマインドを学ぶことができます。
今回は、語られた数多くの言葉の中から、珠玉の3選をお届けします。
結果を出し続けるために大切な心得といえる名言
- 『成功のモデルは壊される前に壊さなければならない。』
≪南場智子≫
株式会社ディー・エヌ・エー(DeNA)の創業者、代表取締役会長。1962年生まれ、新潟県新潟市出身。地元の高校を卒業後、津田塾大学学芸学部英文学科に進学。1986年、マッキンゼー・アンド・カンパニーに入社する。しかし実力不足を感じ、学び直すために退社。ハーバード・ビジネス・スクールに入学し、1990年にMBAを取得する。その後、再びマッキンゼー・アンド・カンパニーに就職。1996年には、34歳の若さでマッキンゼー日本支社のパートナー(役員)に就任する。
1999年、マッキンゼー・アンド・カンパニーを退社し株式会社ディー・エヌ・エーを設立。2011年、夫の看病を理由に代表取締役兼CEOを一度退任するも、2015年に再び取締役会長に就任。同年には、横浜DeNAベイスターズのオーナーにも就任し、プロ野球初の女性オーナーとなる。2021年には、女性初の日本経済団体連合会副会長に抜擢。最前線で活躍を続けている。
株式会社ディー・エヌ・エーを全国区の知名度にまで育て上げた南場さん。eコマース、ゲームやライブストリーミング、ヘルスケア、スポーツなど、さまざまな分野で事業を展開し、成功を収めてきました。
『成功のモデルは壊される前に壊さなければならない。』 という言葉は、その場限りでの成功にとどまらず、結果を出し続けるために必要なマインドといえる名言です。
南場さんは、マッキンゼー・アンド・カンパニーに入社後、周りのレベルの高さや自分の力不足を感じるなど、大きな挫折を味わっています。それをきっかけに、当たって砕けろの精神を大切にし、さまざまなチャレンジをしてきたと南場さんは語っています。
事業成功のモデルができあがっても、いずれは誰かが真似をし、よりよい成功モデルへと変化させていきます。その当時はうまくいったモデルも、数年後に通用するとは限りません。 常にアップデートし続ける姿勢が大切です 。
結果を出したいという気持ちが強いほど、過去の成功体験に引っ張られてしまいがちですが、成功体験を捨て、新たな挑戦をし続けることが重要です。そうすることで、新鮮な見方で目の前の仕事と向き合うことができるでしょう。
決断力に課題がある人に贈りたい名言
- 『継続討議はとても甘くて楽チンな逃げ場である。』
- スピード感を持った経営判断で、失敗を恐れず多様な分野での事業を展開してきた南場さん。
『継続討議はとても甘くて楽チンな逃げ場である。』という言葉は、その意思決定の早さを言い表した名言です。
経営者として新たな挑戦を形にしようとするたび、さまざまなステークホルダーと調整が必要になり、納得する形を模索する必要があります。それぞれの立場が違えば、ものの見方や考え方は当然異なり、意見が対立する場面もあったはずです。
しかし、南場さんは「緊急でない事案も含め、継続討議にしないということが極めて重要だ」と語っており、会議の場での思い切った決断力の大切さを説いています。また、『調整ではなく決めるのが仕事である。』との名言も残しており、最終決定では「自分はこうしたい」という自身の判断を推し進めたのだそう。
重要な決定をするシーンほど、何度も会議を重ねたうえで、じっくりと決断したいと考える管理職の方が多いのではないでしょうか。一方で、議論を重ねるほど考えるべき観点が多くなり、本来の目的から議論がそれてしまうこともよくあります。
内容によっては、一度の話し合いで決断することが難しいケースもあると思いますが、この名言を胸に、できるだけ討議を長引かせずに思い切った決断をすることも大切かもしれません。
部下の育成方針に悩んだ時に思い出したい名言
- 『なぜ育つかと言うと、これまた単純な話で恐縮だが、任せる、という一言に尽きる。』
- 事業規模が大きくなるにつれて従業員数も多くなり、2024年3月末時点で連結で2,897名(単体で1,397名)もの従業員を抱える株式会社ディー・エヌ・エー。
南場さんは人材育成の考え方として、『なぜ育つかと言うと、これまた単純な話で恐縮だが、任せる、という一言に尽きる。』との名言を残しています。
人に仕事を任せることは、シンプルなことのようで、意外と任せきるのは難しいものです。「進捗状況に問題はないか」「アドバイスしたほうがスムーズに事が進むのではないか」といったフォローを入れるケースも多いでしょう。
仕事を順調に成功へと導くにはそうしたフォローが必要なシーンも当然ありますが、一方で、成功への道筋を示しすぎると部下の成長にはつながりません。時に失敗し、遠回りをしてしまっても、部下自身が考え行動することこそが成長への近道です。
管理職の立場としては成果を出すことも重要であるため、自身も深く介入しようと考えるのはごく自然なことです。「任せる」の塩梅が難しいこともあるかもしれませんが、ある程度は部下の主体性を尊重しつつ、寄り添う姿勢で見守ることも重要かもしれません。
~あわせて読みたい記事~ |