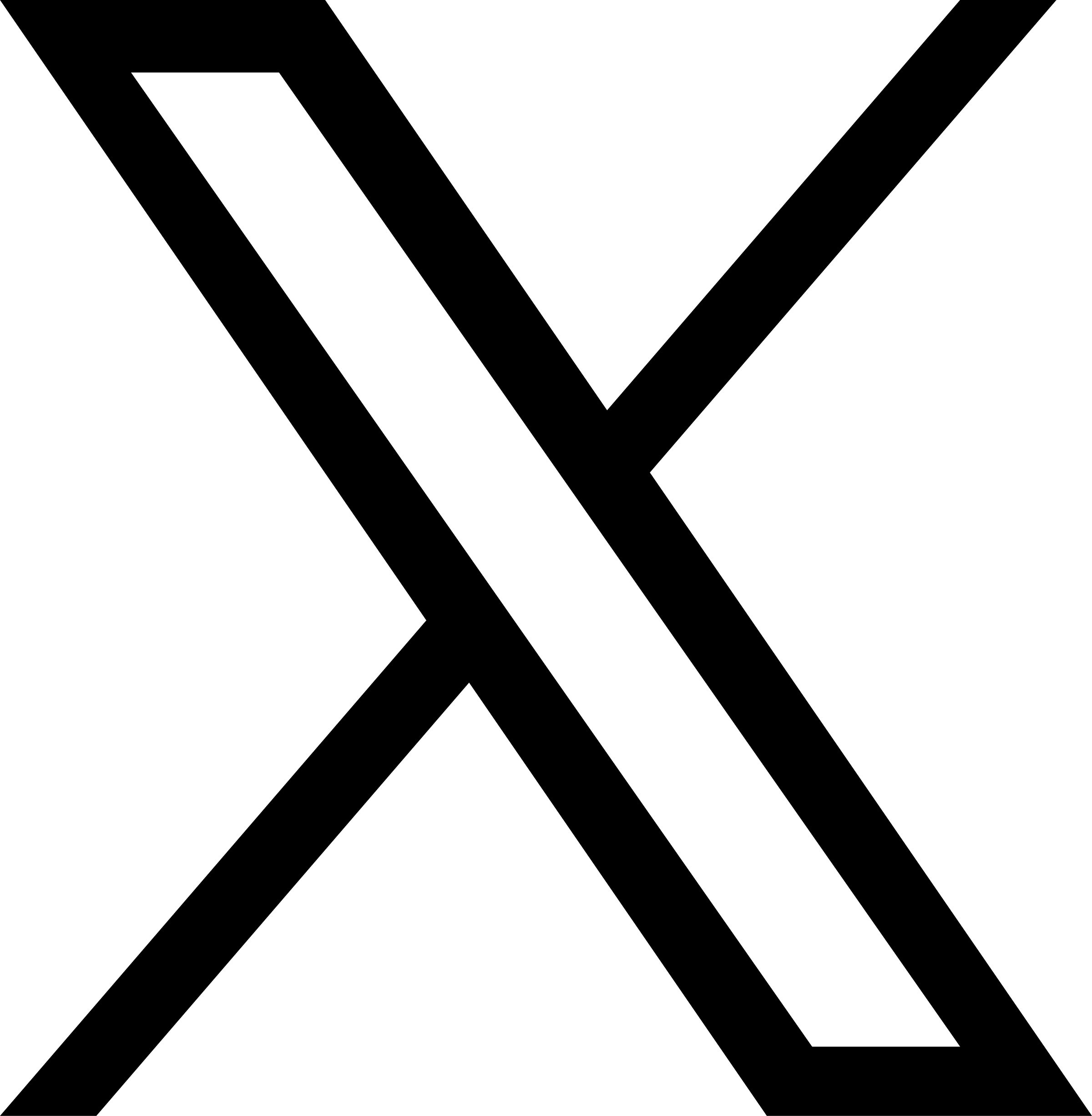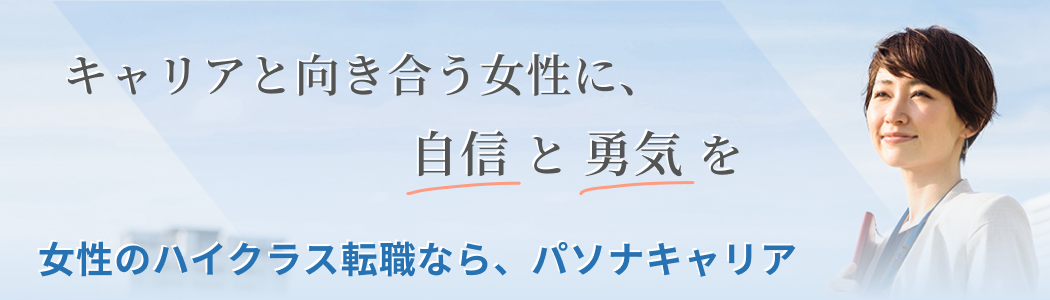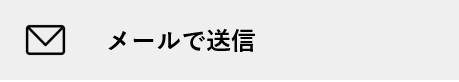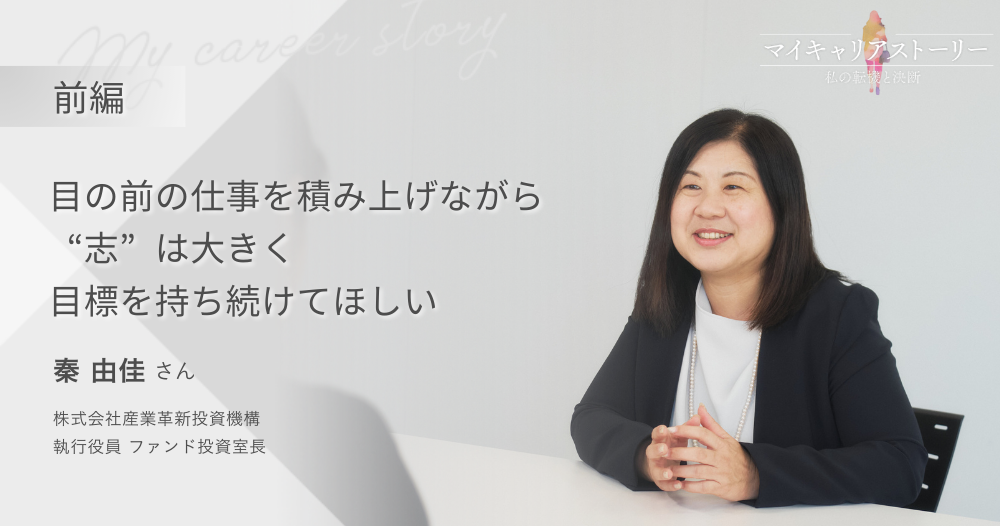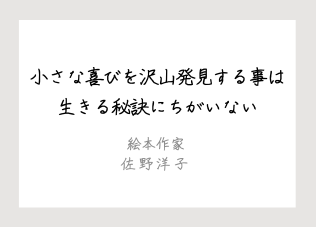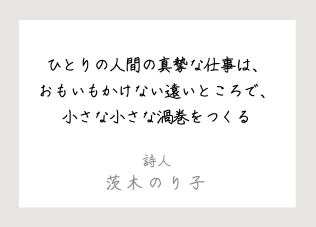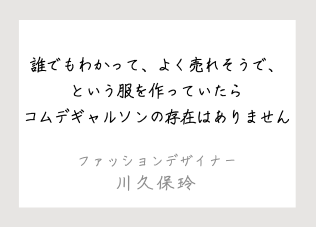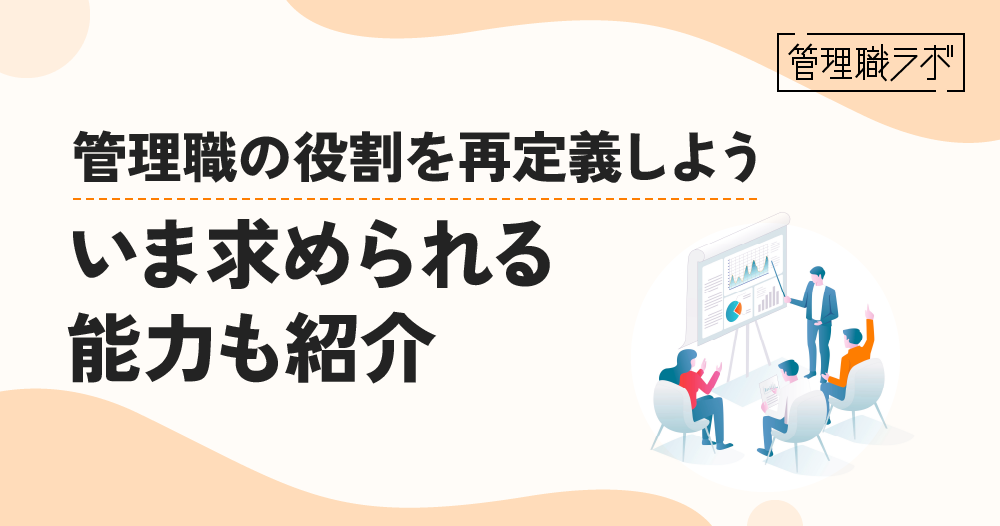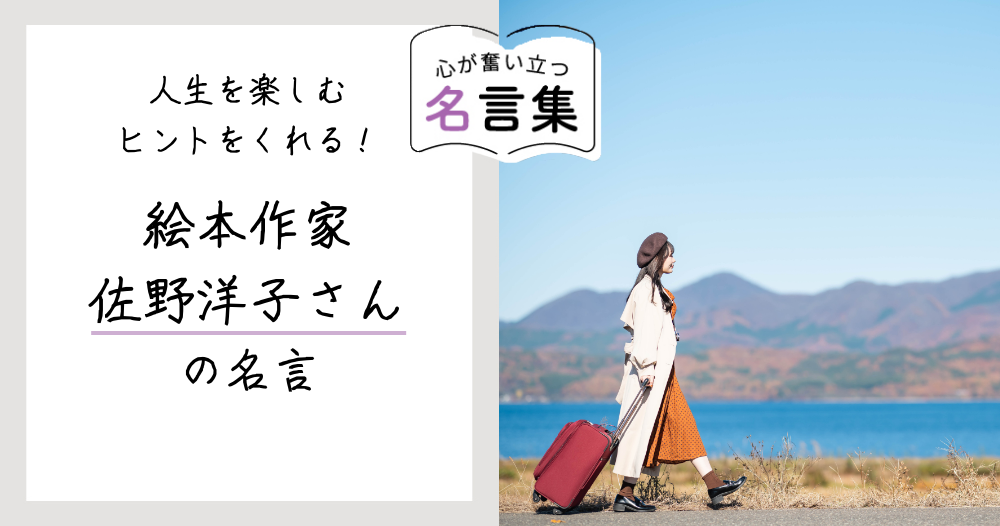『メーカーで感じてきた課題に、コンサルタントとして向き合う』
Mujin Japan コンサルティング部マネージャー 池庄司まり子さん【後編】
誰しも迷うキャリアの決断。管理職として活躍する女性はいつ、何に悩み、どう決断してきたのか。キャリアの分岐点と、決断できた理由を語っていただきます。
今回は前回に引き続き、株式会社Mujin Japanのオートメーションストラテジー本部でマネージャーを務める池庄司まり子さんにお話を伺いました。

池庄司 まり子(いけしょうじ まりこ)さん
株式会社Mujin Japanオートメーションストラテジー本部コンサルティング部マネージャー
新卒で大手自動車メーカーに入社し、生産技術を担当。その後、経営コンサルファームでシニアコンサルタントを経験後、2023年にMujinに入社。2024年4月に設立された日本法人(株)Mujin Japanで製造・物流・小売り等のお客様に向けた生産・SCM戦略や構内物流自動化に関するコンサルティングを担当している。
こちらも
おすすめ
【PIVOT動画】「2026年の転職市場」をプロが超予測
ゼロから組織を作る、ベンチャーの醍醐味があった

- 大手自動車メーカーでの生産技術職を経て、経営コンサルファームに転職。モビリティの知見を活かした交通政策支援などに携わったのち、2023年にMujinへの中途入社を決めました。新卒入社だった1社目を離れたのは、「どんな組織にいても仕事ができるようになりたい」と思ったからでした。ただ、ものづくりから離れたことで、「現場のリアルなデータや技術に根差したコンサルティングができない」ことにもどかしさを感じるようになりました。
- 「改めて、私はものづくりがしたかったんだな、と気づかされました。せっかくコンサルファームで貴重な経験を積めたので、ものづくりの現場に近いところでコンサルティングができる環境はないかと探し始めました。そこで出会ったのがMujinでした」
- まず惹かれたのは、世界唯一の汎用的ロボット知能ソフトウェアを提供するMujinの高い技術力。それらが「実際の工場や物流現場に導入されていて、活用されている実績がある」点も大きな魅力でした。
- 「Mujinのソフトウェアはロボットを自律的に動かし、ティーチレス(ロボットティーチング不要)にできます。 生産技術をしていたときに、そのすごさを実感していたので、そんなソフトウェアを扱えるところに興味を引かれました。
さらに、私が入った23年は、お客様に対峙するコンサルティング専門領域を立ち上げようというタイミングで、組織の立ち上げ期に携われることにもワクワクしました。
当初2~3人でスタートした新組織は2年弱で20名ほどの組織と拡大し、組織が大きく動いていくプロセスを一緒に経験することができました。」
- メーカーとコンサルファームという大企業から、組織規模の小さいロボットベンチャーへの転職。そこに不安はなかったのでしょうか。
- 「前職のコンサルファームには、組織に頼らず仕事をしていこうという独立志向の強い同僚がたくさんいました。次はベンチャーに行く、次は自分で事業を立ち上げる…といった話がぽんぽんと出てくる環境で、私もチャレンジしていかなくちゃ!と刺激をもらいました」
- とは言え、入社当初は想像以上に未整備な環境で驚いたと笑う池庄司さん。最初に任された仕事は人事評価制度を作ることだったそう。面接時に「頑張りが評価される仕組みは、自分のモチベーションになる」と話したことを、上司が覚えていたのだといいます。
- 「大企業にいるときは、制度や仕組みはあるのが当たり前。なかったら文句を言っていたと思います。でも、Mujin では、自分にも関係する評価制度を自分の責任で作っていく。ないことに対して文句は言えませんし、みんなが納得して使っていきたくなるものを作り上げなくてはいけません。
“任せる”という上司のブレない姿勢は、期待に応えたいと思わせてくれますし、組織づくりにここまで関われるのがベンチャーの面白さだなと感じています」
先回りした配慮はせず、丁寧に対話を重ねる

- 現在、Mujin Japanは社員数が約150人(2025年7月時点)となりましたが、1年前までは100人も満たない規模だったそう。組織が急成長を遂げる中でも、様々な属性の社員が安心して働ける環境づくりが進められているといいます。
- 「実は、私はMujinコンサルティングの女性社員第一号なんです。学生時代からずっと、女性であることがマイノリティな環境で過ごしてきて、周りが全員男性、というのがむしろ当たり前でした。でもMujin は、あまりに多様なバックグラウンドの人たちが集まっているので、“女性である”ことを意識することがありません」
- 子育ても介護も、日々の生活も、性別や国籍に関係なく“みんな” の問題だよね、と捉えている。その環境が心地いいと池庄司さんは話します。
- 「マイノリティでいることの難しさは、気を遣われることが、ときにチャンスを奪われることになるということです。例えば、『女性に出張は体力的に厳しいのではないか』など、本人の希望を先回りした“配慮”は、たとえそれが良かれと思ってのものでも、本人の成長機会を奪うことにつながりかねません。
1社目のメーカーでも女性の少ない部署にいましたが、幸運にも近くに女性の先輩がいて、女性だからと言って気遣い過ぎる必要はないと”地慣らし“をしてくれていました。私に対しても分け隔てなく、厳しく言うときは言う、という一貫した態度をとってくれたから、成長できたのだと思っています。これからMujinにも女性社員が増えていくので、今度は私が、かつての先輩のような存在になりたいですね」
- マネージャーとして、メンバー一人ひとりの状況をきちんと理解することも、池庄司さんの大事な役割。そんなときは“配慮”をはき違えないように、丁寧なコミュニケーションが欠かせないと話します。
- 「コンサルタントの仕事はお客様の元に足を運ぶことが多く、出張の機会も多くなりがちです。小さい子どもがいるメンバーとは、具体的にどんな予定であれば家族にとっても本人にとっても都合がいいのかを話し合い、希望があれば、早く帰ってオンラインでできる業務に変更するなどの柔軟性も大切にしています」
「あのときやればよかった」と後悔はしたくない

- Mujinに入るとき、「今だからできる選択をしよう」と考えたという池庄司さん。新しいことに挑戦するときに頭をよぎる「もう遅いのではないか」というストッパーには、これからも抗っていきたいと話します。
- 「大学院時代に留学したときも、メーカーからコンサルファームへ転職したときも、『今からやっても遅いんじゃないか』『年齢的に難しいんじゃないか』と一瞬、尻込みしたんです。でもやってみたら全然そんなことはありませんでした。
もし、挑戦を先送りにして数年後に『やっぱりやりたい』と諦めがつかなかったとしたら、『あのときにやればよかった』『できたはずなのになぜやらなかったのか』と必ず後悔すると思います。
遅いと思ったとしても、何才からでも成長できるはず。だから、私はこれからも、社会や周りの人が漠然と発する“年齢的に難しいよ”というメッセージにどんどん抗っていこうと思っています」
→「前編記事」
~あわせて読みたい記事~ |
取材・執筆:田中 瑠子