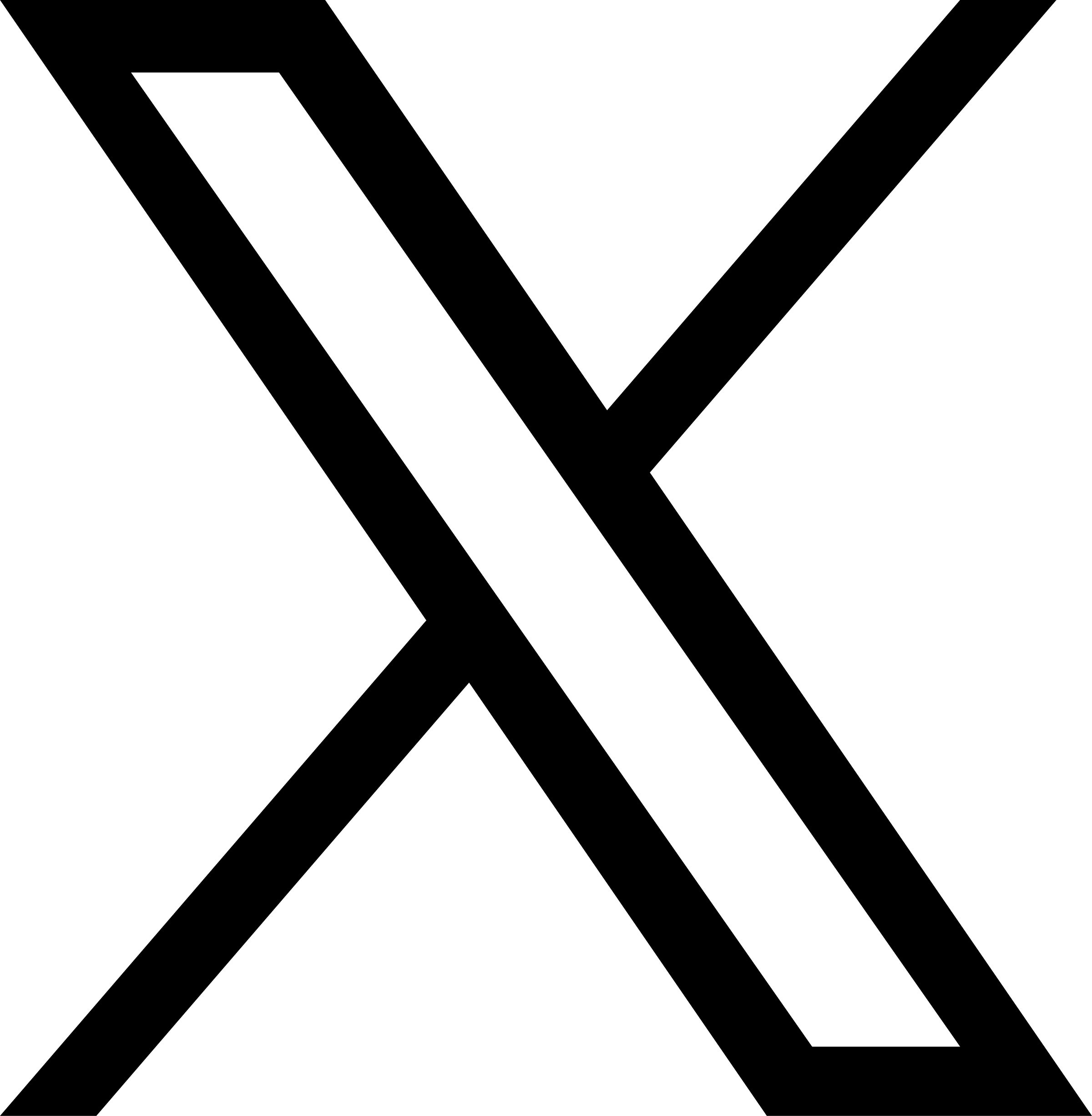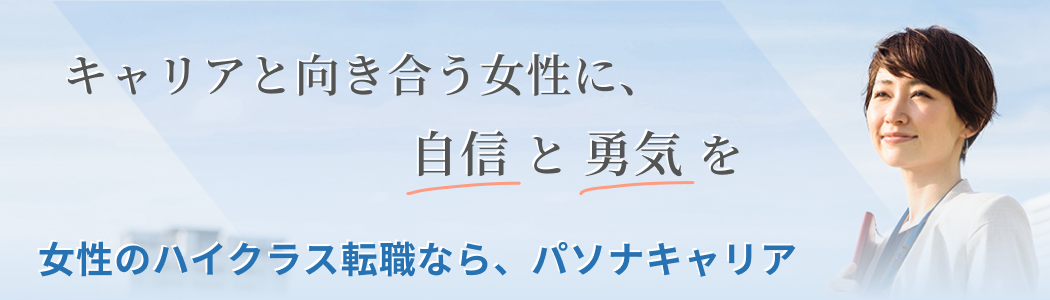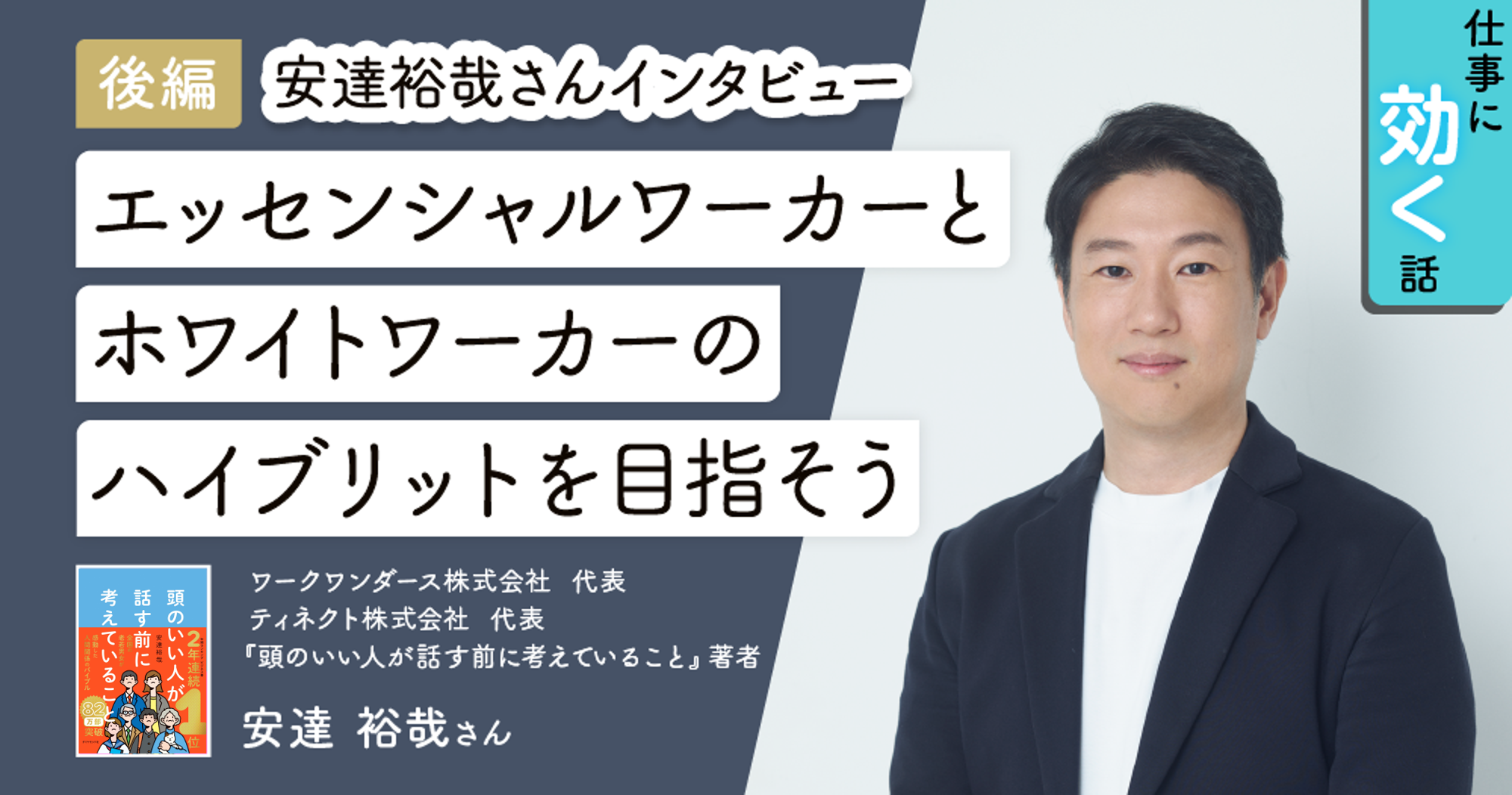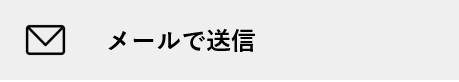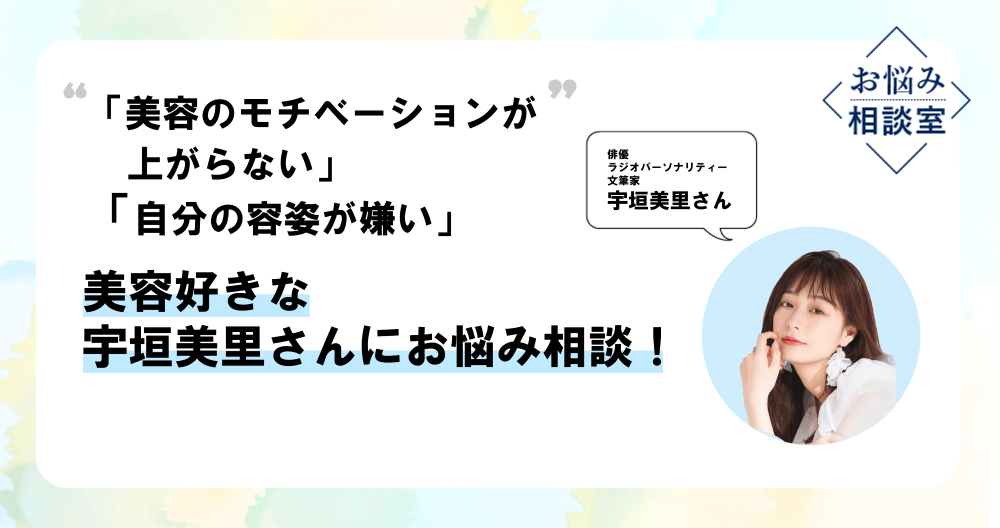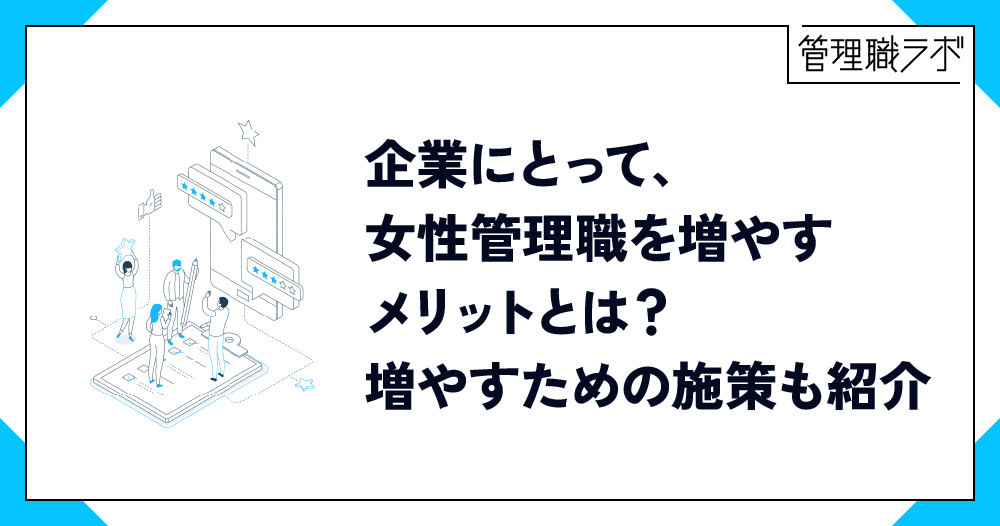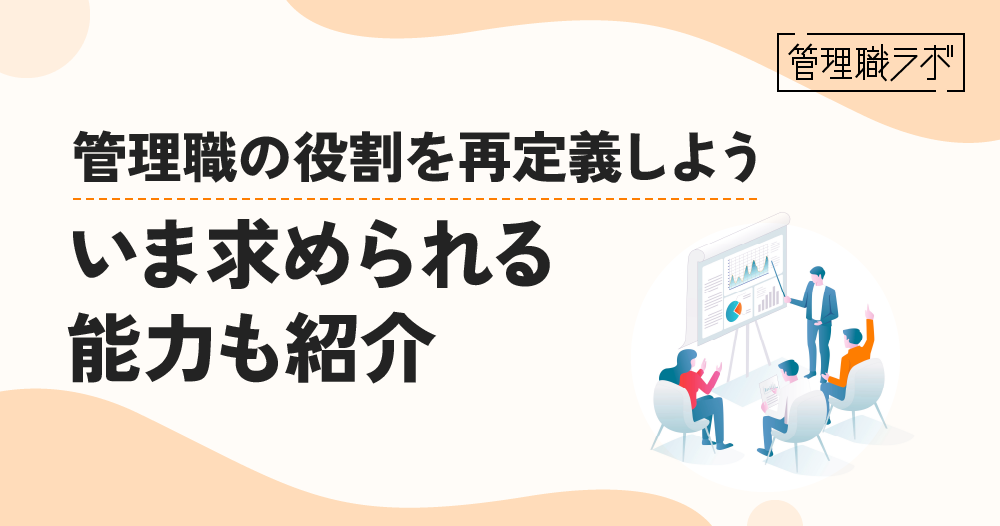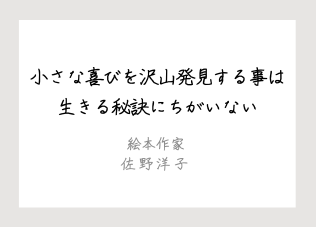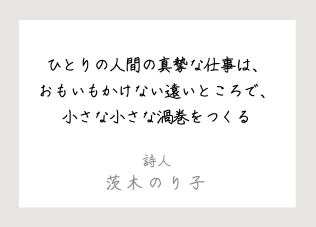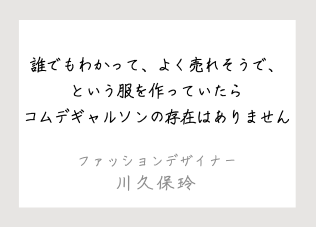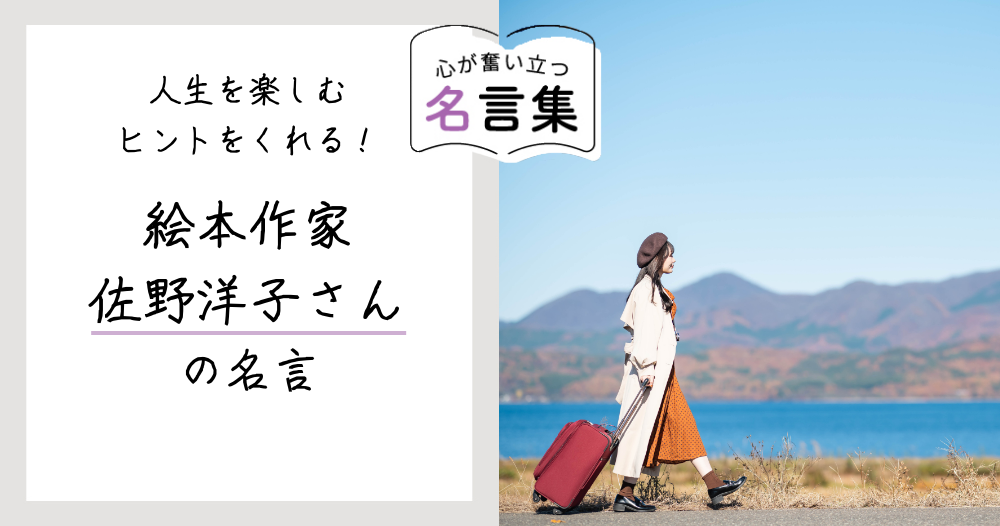生成AIで変わるホワイトカラーの未来──経営者・安達裕哉が語る、生き残る人の条件
生成AIの急速な進化が、オフィスワーカーの仕事に大きな変化をもたらしています。エンジニア、ライター、翻訳者──オフィスで行われてきた多くの業務が、すでにAIに置き換わり始めている現実は受け入れざるを得ません。
では、AIと共存する未来で人間に求められる力とは何か? 生成AI開発・コンサルティングを行うワークワンダースのCEOとして、自身もAI活用を実践しながら、現場のリアルな変化を見つめ続けてきた安達裕哉氏に話を聞きました。生成AIがもたらす働き方の変化、そしてこれからの時代に生き残る人材の条件について語ります。

安達裕哉さん
株式会社ワークワンダースCEO/ティネクト株式会社CEO
1975年生まれ。筑波大学大学院環境科学研究科修了後、デロイト トーマツ コンサルティング(現アビームコンサルティング)に入社。品質マネジメント、人事などの分野でコンサルティングに従事し、その後、監査法人トーマツの中小企業向けコンサルティング部門の立ち上げに参画。大阪支社長、東京支社長を歴任したのちに独立。著書『頭のいい人が話す前に考えていること』(ダイヤモンド社)はベストセラーとなり、2023年・2024年のビジネス書年間ランキングで1位を獲得。
ほとんどの「部下仕事」はAIで代替可能
- ー生成AIが組織や人に与える影響について、どのように実感されていますか?
- 安達:ホワイトカラーの仕事がなくなるかもしれないという危機感を持つ人が増えたと感じています。私も1年前くらいまでは「人間しかできない仕事は全然残るだろう」と思っていました。しかし、この1年間での生成AIの進化のスピードがものすごく速くて、いよいよオフィスワーカーの仕事のほとんどが置き換えられてしまうなと実感しています。
実際に、エンジニアを雇うことを辞めた企業もありますし、記事制作などのライティングの仕事も激減しています。また、私たちの会社でも生成AIによる翻訳アプリケーションの開発を行いました。となると翻訳家の方の仕事も減ってしまう。
ホワイトカラーの方は、仕事の仕方を変えざるを得ないという状況が目の前に迫ってきています。
- ーでは、どのように変わっていくべきなのでしょうか?
- 安達:生成AIを使ってできることは当然自分でできなければなりません。そして生成AIを使うことを前提にした仕事の獲得をしなければならないですね。
例えばライティングの仕事だったら、論理的な文章を書くことは生成AIでできても、記事の企画やタイトル付け、面白い文章を書くことはまだAIには苦手です。また取材などのフェイスtoフェイスの仕事も生成AIにはできません。
また会社の中でも「部下仕事」と呼ばれる管理職の下で行うような仕事はほぼほぼ生成AIで代替できると実感しています。資料をまとめたり、スライドを制作したり、web上で調べたことを集計したり、という仕事です。
極論ですが、肉体的な労働をするか、経営者として仕事をするかしか無い未来が遅かれ早かれやってくると思っています。
生成AIの限界を知り、頭を使う
- ー安達さんご自身は、経営やマネジメントで生成AIをどのように活用されていますか?
- 安達:ほぼ全方位で使っていますが、メールの返信やセミナー資料作成、翻訳、議事録制作、プレスリリース制作、キャッチコピー制作、記事執筆、データ分析などですかね。統計データをAIに読ませて業界研究を行うこともあります。
弊社では、キーワードを入力すればwebをクロールしてレポートしてくれるというAIのアプリケーションも開発しました。キーワードに対して約5分でメールでレポートを送ってくれるという仕組み。従来の調査会社と同じような仕事をしてくれています。
- ー「生成AIに頼りすぎると考える力が衰えるのでは」という心配もあります。
- 安達:大前提として、生成AIが仕事をしてくれるからこそ、人間は頭を使った仕事をしないと社会人としての生き残りが厳しくなってくると感じています。
頭を使った仕事をするためにまずすべきことは、生成AIを使ってみてその限界を知ることが重要です。生成AIを使わない限り、何を任せられて、人間は何をやるべきかがわからないんですよ。自分の仕事を生成AIに替えられないためには、その状態から脱することから始める必要があります。
例えば今日のインタビューも、音声を文字に起こすことや記事の骨組みくらいまでは生成AIに任せられるでしょう。生成AIがなければそれだけで1日かかっていたはずです。生成AIのおかげで浮いた時間を使えば、記事をもっと面白くすることに注力できますよね。このように思えるかどうかが、生成AIを使いこなせる人とそうでない人の違いかなと感じます。
対面での商談、飲み会…生成AI時代だからこそ大切にすべき文化
- ー管理職ならではの生成AIの使い方があれば教えてください。
- 安達:マネジメントの場面で使うとしたら、「こんな発言をしたら相手はどう反応するか」というシミュレーションができるようになってくると思うんですよね。これまでの部下とのやりとりの録画や録音、会社で実施している性格テストなどを生成AIに読ませて相手の人柄を学習させておく。すると、どういう伝え方をすると良いかが予測できるようになると思います。部下への指導の際も、上司へ稟議を通す際も、お客様に営業する際にも使えますよね。
あとは、部下のタスク分析・管理も生成AIを活用できます。
例えば「マーケティングの調査をお願い」と言うだけで仕事に取り掛かれる部下と「図書館でこれを調べた上で、こうまとめてこのタイミングで報告して…」と、タスクを細かく分解しないと動けない部下もいるかと思います。後者はマネジメントの工数がかかるので、仕事の具体的なやり方は生成AIに相談してもらう。
管理職が逐一指示を出す必要がなくなるため、マネジメントの効率化につながると思います。
- ー組織全体で生成AIを使う際に、管理職が持つべき視点はありますか?
- 安達:部下の仕事はアウトプットで判断されるべきであり、途中で生成AIを使っているかどうかは関係ないという視点ですね。
生成AIを使おうか手動で行おうが、できるだけ短い時間で高いクオリティをあげることが正解。最低限のルールとして、情報漏洩やセキュリティ面だけ守れば十分なのではないでしょうか。
生成AIもバリエーションが多様なので、部下の使い方に関して管理職が全て口出しをするのは現実的ではないと感じます。これまでも、管理職がいちいちExcelの使い方に口を出してはきませんでしたよね?
- ー最後に、生成AI時代においても、これからも変わらず必要とされる人間の力を教えてください。
- 安達:物理的な影響力ですね。例えば、一緒にお酒を飲むだとか、握手をするだとか。こういったことは、ロボティクスがもっともっと進化しないと生成AIには実現できません。生成AIが人間のパートナーになることは難しいので、その点は人間の役割。
私の会社でも、営業で必ず一度はお客様に直接お会いすることを徹底しています。そうしないと信頼関係を築きにくいと感じる方もたくさんいます。そういった物理の能力を仕事に活かして、いわゆるエッセンシャルワーカーとホワイトワーカーのハイブリットを目指すようになっていくのだと感じています。
生成AIがいかに高精度な画像を作ってきたとしても、オンラインで会話をする時にも本人の顔が出ていないのは嫌じゃないですか。やっぱり人は生身の人間と話したいものですから。
さらに言うと、お金を持っているのは人間です。商売ができるのは人間なので、人間同士の信頼関係を築かない限りビジネスに繋がりません。そのためにも人間が持つ物理的な影響力を使って人に礼を尽くすことは重要なのではないかと思います。
→「前編記事:管理職が話す前にすべきこと」